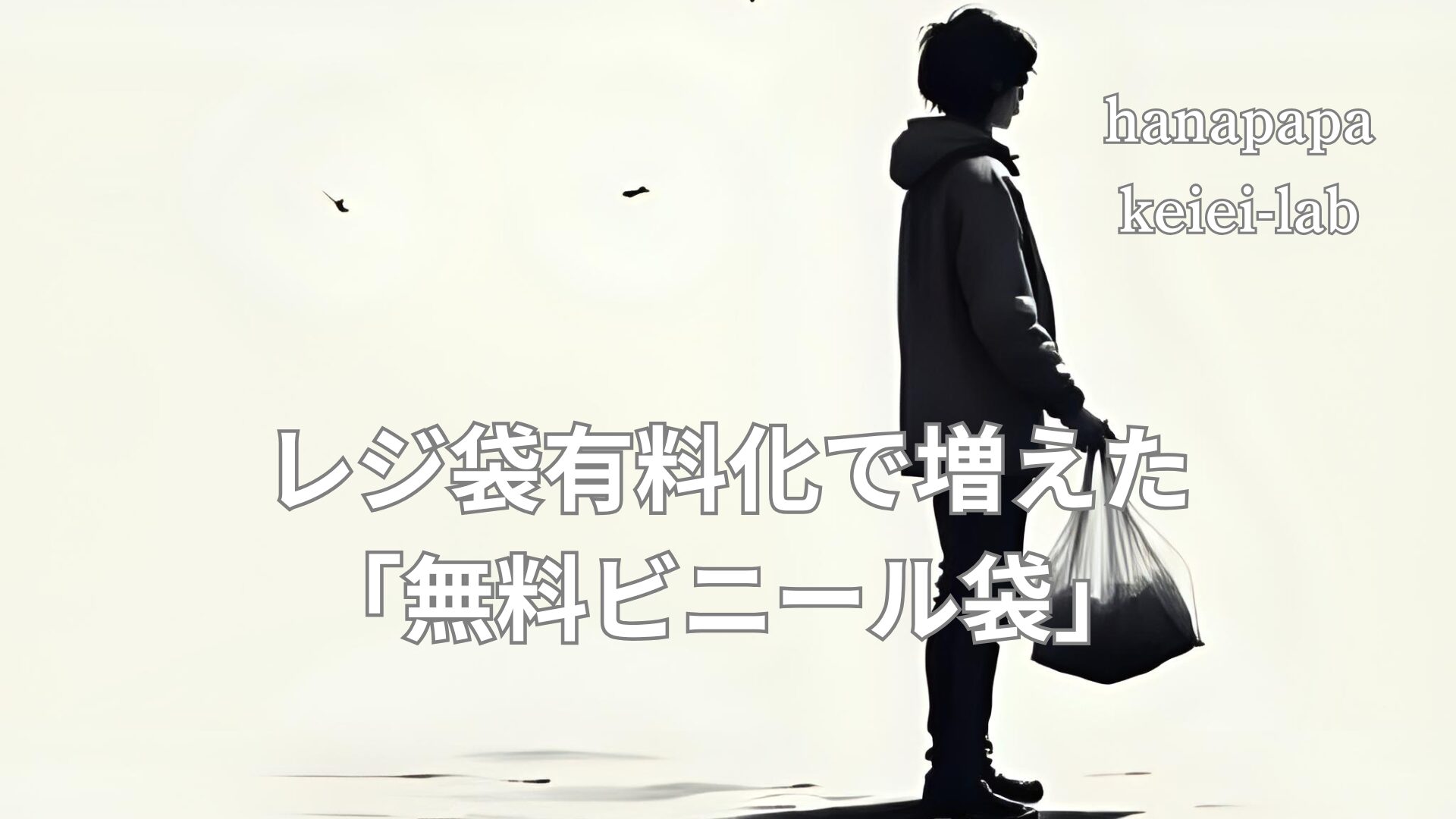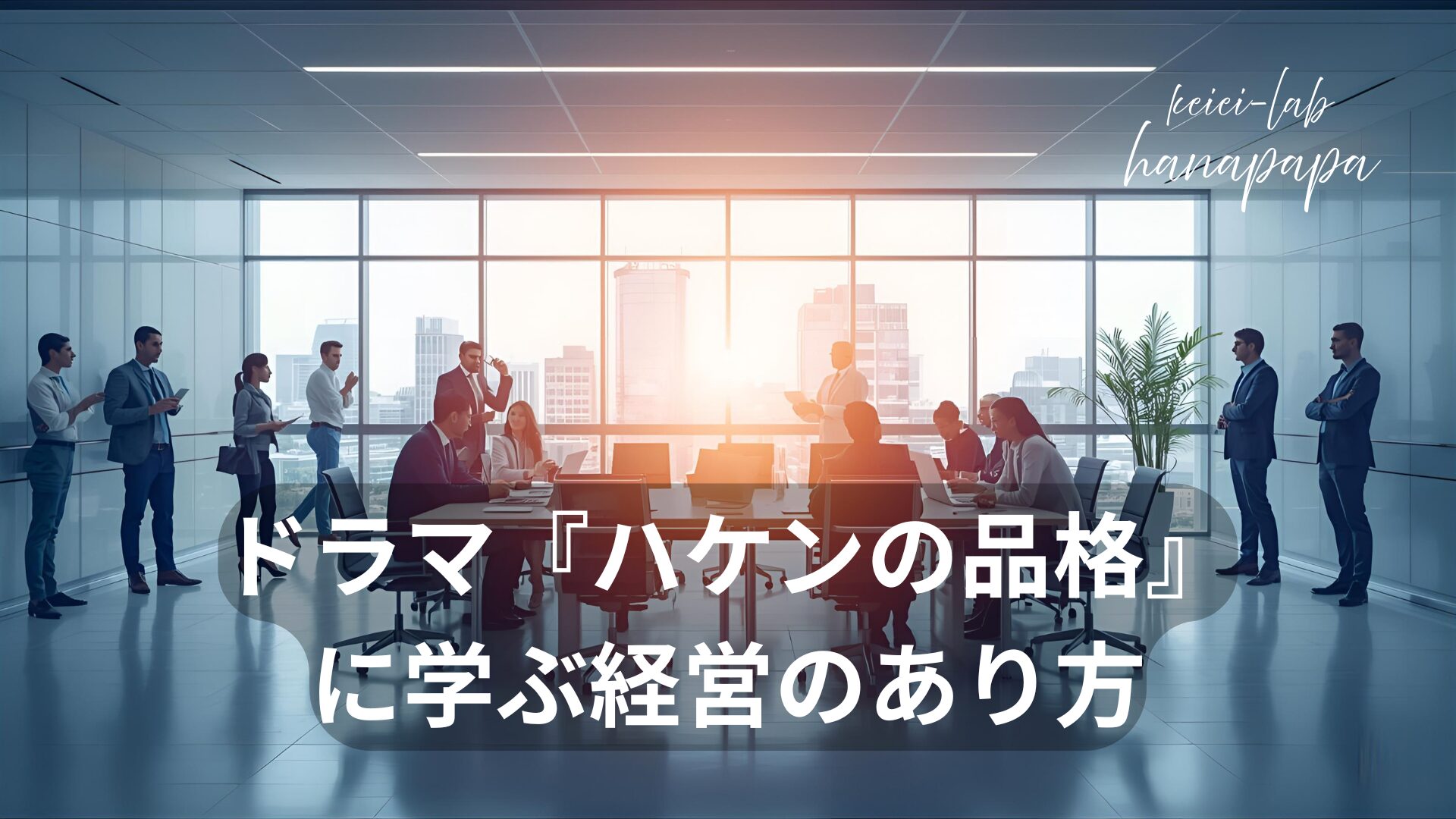【現場エピソード】台風直撃の日に学んだ「店を開け続ける意味」――非常時に見えた信頼と責任
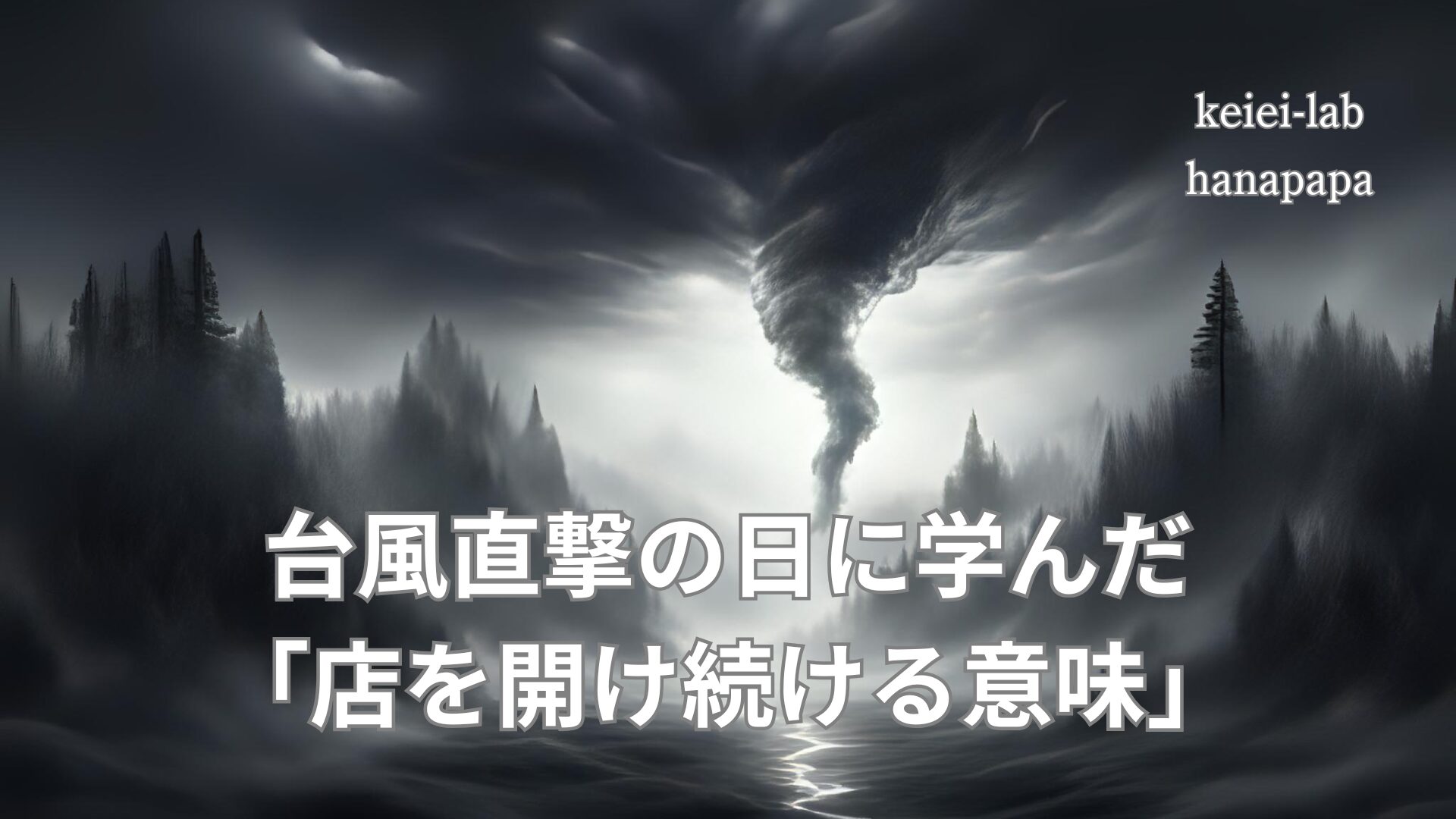
――“誰も来ない日”にも、必ず必要としてくれる人がいる
大型の台風が関東を直撃した日。
街は閑散とし、交通機関も止まり、ほとんどの店舗が次々とシャッターを下ろしていきました。
「今日は誰も来ないだろう」
多くの人がそう思うような状況の中でも、私は店の灯りを消さずにいました。
すると数時間後、
思いがけずお客様が来店し、こう言われたのです。
「どこも閉まってたけど、ここが開いてて助かったよ。」
その瞬間、
「店を開けておく」という行為の意味を、数字ではなく“人の気持ち”で理解した気がしました。
この記事では、
台風当日の現場で感じた「店を開ける決断の重み」と、
営業を続けることで見えた“信頼”の本質についてまとめます。
関東に台風直撃、あの日の記憶
――「開けておくべきか、閉めるべきか」で揺れていた
数年前、関東に大型台風が直撃した日のことです。
いつもは人通りの多い通りも、朝から強い風と雨で真っ白。
信号は揺れ、道路の木々も倒れかけ、
「今日は営業どころではないな」と思わせるほどの荒天でした。
午前中の時点で、近隣のスーパーや個人店舗は次々に休業。
本部からも「安全を最優先に、閉店判断を」と指示がありました。
それでも私は、店舗の前に立ち、
風で飛ばされそうになる店頭の資材などを片付けながら、
「それでも来てくれるお客様がいるかもしれない」と考えていました。
店を開け続けるかどうかの葛藤
そのとき、頭に浮かんだのは、
毎日のように来てくれる常連のお客様の顔。
雨の日も雪の日も必ず来店し、
「いつもありがとう」と声をかけてくれる方々です。
もしかしたら、今日も来てくれるかもしれない
もし閉めていたら、その人たちはどこで買い物をするんだろう
そう思うと、
「営業すること」が“危険”ではなく“責任”のように感じました。
決断:灯りを消さないという選択
結局その日、私は店を開けておくことを選びました。
風の音がうなる中、スタッフと相談しながら
最低限の体制でレジを稼働させ、
安全を最優先にしつつ静かに営業を続けました。
数時間後、
水浸しになった傘を差しながら一人、また一人とお客様が来店。
「どこも閉まってたけど、ここが開いてて助かったよ。」
その言葉を聞いた瞬間、
“店の灯り”が地域の安心そのものになっていることを実感しました。
台風の日、街が止まっても、
小さな明かりをともす店がある。
それが、地域に生きる店舗の使命なのかもしれません。
「買う場所がないから来た」という声
――その一言に、店を続ける理由が詰まっていた
午後になると、雨風はさらに強まり、
街の明かりがどんどん消えていきました。
それでも、傘を差してびしょ濡れになりながら、
数名のお客様がゆっくりと店に入ってこられました。
レジに立っていると、年配の女性がこう言いました。
「どこも閉まってて、買う場所がないから来たのよ。
開いてて本当に助かりました。」
その言葉を聞いた瞬間、
心の中で何かが静かに響きました。
お客様の“日常”を支えているという実感
普段は当たり前に思っていた日々の営業。
しかしこの日、改めて実感しました。
「コンビニが開いていること」そのものが、
お客様の生活を支える“インフラ”になっているということを。
とくにご高齢のお客様や一人暮らしの方にとって、
私たちのような店舗は食と生活の命綱。
「ここが閉まったら、本当に困る。」
そんな言葉を、雨音にかき消されるような声で聞いたとき、
「営業を続けること=地域に灯りをともすこと」だと感じました。
まとめ買いではなく“生きるための買い物”
この日のお客様は、
「特別なものを買いに来た」わけではありません。
- 今日の夕食の材料
- 翌朝のパンや牛乳
- 雨で濡れた体を温めるホットドリンク
それらを手にレジに並ぶ姿を見て、
“日常を取り戻すための買い物”という言葉が頭に浮かびました。
普段なら数分で終わる買い物が、
この日は“生活の安心を取り戻す時間”になっていたのです。
どんなに小さな買い物でも、
それは「安心を買う」行為かもしれない。
その安心を提供できる場所でありたい――。
台風の日のあの声が、今も私の中で残り続けています。
閉める決断の重さ
閉める決断の重さ
――「安全を守る」という判断も、経営の責任
夕方になると、風はさらに激しさを増し、
街の信号が揺れ、雨が斜めに叩きつけるようになっていました。
「このまま営業を続けるのは危険かもしれない。」
スタッフの表情にも疲れが見え始め、
本部からは再び「安全を最優先に閉店を」と指示が届きました。
その時、私は迷いました。
「お客様がまだ来ている」――それでも「スタッフの安全を守らなければ」。
売上よりも命を守る。
この当たり前のようで難しい決断を、
経営者としてどう下すべきか、胸の奥で何度も問いかけました。
“やめる勇気”もまた、経営判断
私たちは「店を開けること」に使命を感じがちです。
しかし同時に、
「いつ閉めるか」も経営の一部だと、この日改めて気づきました。
お客様に安心を届けるためには、
まずスタッフが安心して働ける環境が必要です。
「無理をしてでも店を開ける」ではなく、
「無理をしないことも信頼を守ること」。
営業とは、“続けること”ではなく、
“正しいタイミングで守ること”。
その判断ができるかどうかで、
長期的な経営の信頼性が変わるのだと思います。
灯りが消えた街で感じたこと
閉店後、外に出ると、
いつも明るい街が一瞬にして真っ暗になっていました。
飲食店も、スーパーも、他のコンビニも――。
普段はどの時間帯でも灯っている明かりが、
すべて消えている光景を見て、胸の奥が締めつけられるようでした。
「街全体が止まる」という現実。
その中で、自分たちの店の“明かり”がどれほどの意味を持っていたかを痛感しました。
この経験は、営業をやめた悔しさよりも、
「日常を支える灯りを守る」責任を改めて意識するきっかけになりました。
店を開けている意味を改めて実感
店を開けている意味を改めて実感
――“便利”を超えて、“信頼”を売る商売へ
台風の日を経験して、私は改めて感じました。
私たちが提供しているのは、商品やサービスだけではなく「安心」や「信頼」そのものだということを。
お客様が店のドアを開けた瞬間、
そこに明かりが灯っていること。
人の声が聞こえること。
それだけで「この街はまだ大丈夫だ」と思ってもらえる。
店を開けるという行為は、地域の人たちの“心の灯り”を守ることでもある。
便利さの先にある「信頼」という価値
コンビニは「24時間営業」「すぐ買える」という便利さが強みです。
しかし、本当の意味でお客様に選ばれ続ける店になるには、
便利さの奥にある“人の想い”を感じてもらうことが大切です。
台風の日に営業を続けたことで、
お客様から「助かった」「ありがとう」という言葉を多くいただきました。
その一言ひとことが、数字以上の励ましであり、
「この地域の一員として、ここに存在する意味」を教えてくれました。
商売の本質は「寄り添うこと」
売上は大切です。
しかし、非常時にこそ問われるのは、“どれだけ人に寄り添えるか”。
- 安心して利用できる場所を守ること
- 当たり前を当たり前に提供し続けること
- お客様に「ここがあってよかった」と思ってもらえること
それができる店こそ、どんな時代になっても強い。
商売とは、モノを売ることではなく、
「人の安心を支えること」。
そしてその積み重ねが、地域とともに歩む“信頼”をつくっていく。

あの日の選択は、正しかったのか――。
台風が去ったあと、店の前で立ち止まりながらそう考えました。
でも、お客様の「ありがとう」という声が、その答えをくれた気がします。
“開けていてよかった”ではなく、
“誰かのために開けられた”ことが、何より誇らしかった。