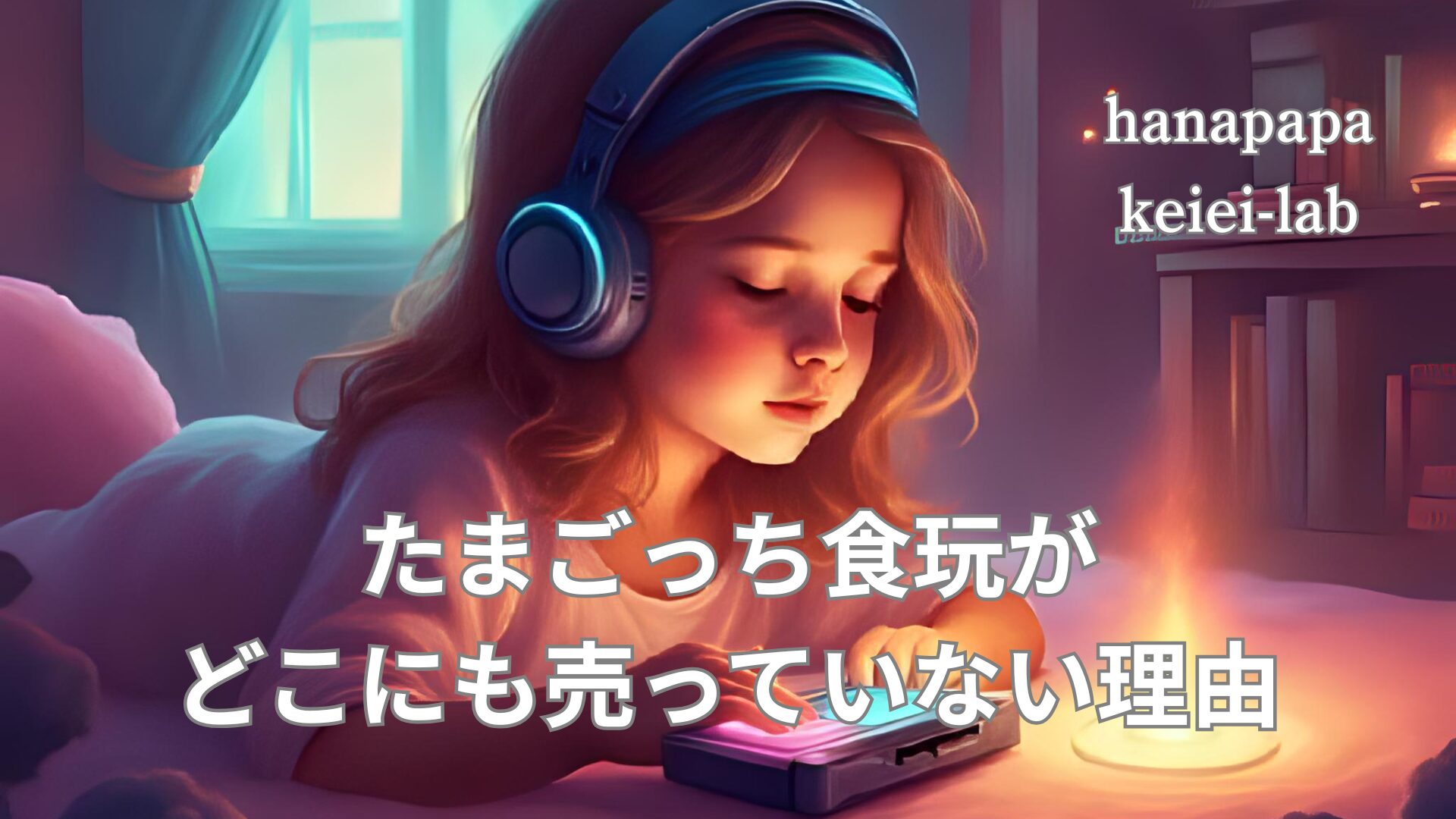【書評】西野亮廣『夢と金』に学ぶ|価格設定と付加価値で変わる商売の本質

――価格設定と付加価値で“商売の本質”が変わる
「値上げは悪なのか?」
「お客様に納得してもらえる“価格”とは何か?」
物価上昇や人件費の高騰が続くいま、
この問いは多くの店舗経営者・販売者にとって避けて通れないテーマです。
西野亮廣さんの著書『夢と金』は、
お金の話を通じて “商売の本質=価値の伝え方” を鋭く問いかけてきます。
単なる値付けのテクニックではなく、
「なぜその価格で売るのか」「お客様にどう感じてもらいたいのか」まで踏み込んで語られており、
経営者として深く考えさせられる一冊でした。
この記事では、本書を通じて得た
価格設定と付加価値の関係性を整理しながら、
コンビニ・小売・サービス業などの現場にも活かせるヒントをまとめます。
「本人が話しかけてくるような言葉」の本
『夢と金』を読んでまず感じたのは、
まるで 西野亮廣さんが目の前で話しかけてくるような臨場感 でした。
テレビやSNSで見慣れた彼の話し方そのままに、
テンポの良い言葉とリアルな表現で綴られている。
まるで講演を聞いているかのような“ライブ感”のある文章です。
この「言葉の温度」が、多くのビジネス書とは違うポイントだと感じました。
一般的な経営書は理屈や理論が中心ですが、
西野さんの言葉は “現場で動く人の感情”に寄り添っている。
たとえば――
「お金は“信用を数値化したもの”である」
「値段とは、あなたの覚悟の見せ方である」
これらのフレーズは、机上の理論ではなく、
舞台・オンラインサロン・絵本事業など、実際に行動してきた人の“実感”から生まれた言葉です。

頭ではわかっているんです。
「ちゃんと想いを伝えなきゃ」って。
でも、いざ目の前にすると…
うまく言葉が出てこないんですよね。

それ、すごくわかる。
気持ちが強いほど、伝えるのって難しくなるもんね。

そう。
だからこそ、西野さんの言葉が心に刺さったんです。
“伝わらないのは、伝えようとしないから。”
この一文に、胸をギュッと掴まれました。
価格設定に“意味”がある
本書で特に印象に残ったのは、西野亮廣さんが語る
「価格設定には必ず意図がある」という一節でした。
たとえば、飛行機の座席には「エコノミー」「ビジネス」「ファーストクラス」があります。
同じ目的地に行くのに、価格は数倍違います。
しかし、それぞれが選ばれる理由は「移動」ではなく、
“どんな体験をしたいか” にあるのです。
つまり、価格とは単なる数字ではなく、
「お客様にどんな価値を感じてもらいたいか」を表現するメッセージ。
値付けの裏には、提供者の“意図”と“覚悟”が反映されています。

高価格帯にクレームを入れるバカ!と西野さんらしいド直球な言葉。笑いました。
現場で実感する「価格の伝わり方」
たとえば、同じ100円コーヒーでも、
「早くて便利な一杯」なのか、「心を落ち着かせる一杯」なのかで意味は変わります。
それを伝えられるかどうかで、同じ価格でも“感じる価値”が違ってくるのです。
価格とは「お客様との約束」であり、
安さではなく“理由のある値付け”が信頼を生む。
この視点を持てば、どんな業種でも価格設定が経営の強みになります。
プレミアムとラグジュアリーの違い
――“体験の深さ”が価格を決める
本書の中で印象的だったのが、西野亮廣さんが語る
「プレミアム」と「ラグジュアリー」の違いです。
この2つの言葉は似ていますが、実はまったく異なる概念です。
💎 プレミアムとは
競合が多い中で、“最上級の体験”を提供する存在。
たとえばベンツやBMWのように、品質・快適さ・安心感といった
「比較されても選ばれる理由」を持っているブランドです。
🕊 ラグジュアリーとは
そもそも比較されない、“唯一無二の存在”。
フェラーリやランボルギーニのように、
「性能」よりも「所有すること」自体が価値になる。
つまり――
- プレミアム=機能的な最高
- ラグジュアリー=存在そのものの価値
コンビニ経営への応用
一見すると、コンビニはプレミアムでもラグジュアリーでもないように見えます。
しかし実際には、両方の要素を持ち合わせています。
- プレミアム要素:清潔な売場・温かい接客・高品質なPB商品
- ラグジュアリー要素:常連客との信頼関係・「あの店に行きたい」と思わせる空気感
つまり、価格競争の中でも、
「誰から買いたいか」=“体験の価値”を提供できる店こそ強い。
ラーメン屋の例に学ぶ「付加価値」
――価格の差ではなく、“感じ方”の差で勝負する
本書で印象に残ったのが、「ラーメン屋の3店舗」の話です。
3軒とも同じ700円のラーメンを出しているのに、
なぜか1軒だけ行列ができ、他の2軒は空いている。
この違いを生み出しているのは、味ではなく「付加価値」だと西野亮廣さんは語ります。
現場への応用:コンビニ・小売でも同じ原理
この考え方は、私たちの現場にもそのまま当てはまります。
同じおにぎり、同じコーヒーでも、
“どこで買うか”でお客様の印象は変わります。
- レジでの「ありがとうございます」の一言
- 商品を丁寧に渡す手の動作
- 目を合わせた笑顔
それらはすべて、商品に付け加えられる“体験のラベル”のようなもの。
価格競争ではなく、「感じのいいお店」「安心して買えるお店」として記憶に残ることが、
長期的なファンづくりにつながります。

売上が安定しているお店ほど、実は「当たり前の接客」がしっかりしている。
商品は真似されても、人の気配りや温度までは真似できません。
それこそが、価格を超える“店の価値”だと思います。
コンビニ経営への応用
――価格よりも「人」と「体験」で選ばれる店に
本書で語られる「価格の意味」や「付加価値」の考え方は、
そのままコンビニ経営に直結します。
同じおにぎり、同じコーヒーを扱っていても、
「どの店で買うか」を決めるのは、価格ではなく“体験”です。
スタッフ育成における「価値づくり」の視点
付加価値を生むのは、商品ではなく人。
だからこそ、現場で働くスタッフ一人ひとりが
“お客様に何を感じてもらいたいか”を理解して働くことが大切です。
具体的には:
- 朝礼で「今日のテーマ(お客様に届けたい気持ち)」を共有する
- 売場を整える目的を“売上のため”でなく“気持ちよく過ごしてもらうため”に変える
- 声かけや挨拶に“店の方針”を込める
これらの小さな行動が、店全体の「価値づくり」になります。

コンビニ業界は商品が均一化されるほど、
最後に残る差は「人」と「空気」だと感じます。
どんなにAIや効率化が進んでも、
“人の温度”を感じる店は、必ず選ばれ続けます。
価格は“数字”でありながら、
お客様の心の中では“感情のラベル”として記憶される。
そして、その感情を動かすのは「人の想い」――。
この考え方を持てば、どんな店舗でも、
価格競争に巻き込まれずに“選ばれる店”をつくることができます。
まとめ:価格とは“想いを伝える手段”
『夢と金』を読み終えて感じたのは、
「価格とは、想いを伝えるための手段である」ということです。
お客様が払うお金は、ただの商品代ではなく、
その店・その人の「想い」と「姿勢」に対する共感の表れ。
安いか高いかではなく、
「この価格には理由がある」と感じてもらえた瞬間、
そこに信頼が生まれ、長く選ばれる店になるのです。
経営の原点に立ち返る
現場で働いていると、どうしても「売上」「コスト」「利益」に意識が向きがちです。
けれど、数字の前にあるのは“人”であり、“想い”です。
- 「お客様に気持ちよく過ごしてもらいたい」
- 「スタッフが誇りを持てるお店にしたい」
- 「地域に必要とされる存在でありたい」
こうした想いがあるからこそ、価格に意味が宿る。
そしてその意味が伝わったとき、
お金は“ありがとう”の形として戻ってくるのだと思います。

この本を通じて感じたのは、「お金」とは信頼のバロメーターだということ。
安さではなく、丁寧さ・誠実さ・温かさ――。
それを価格という形で表現できるお店を、これからもつくっていきたいです。