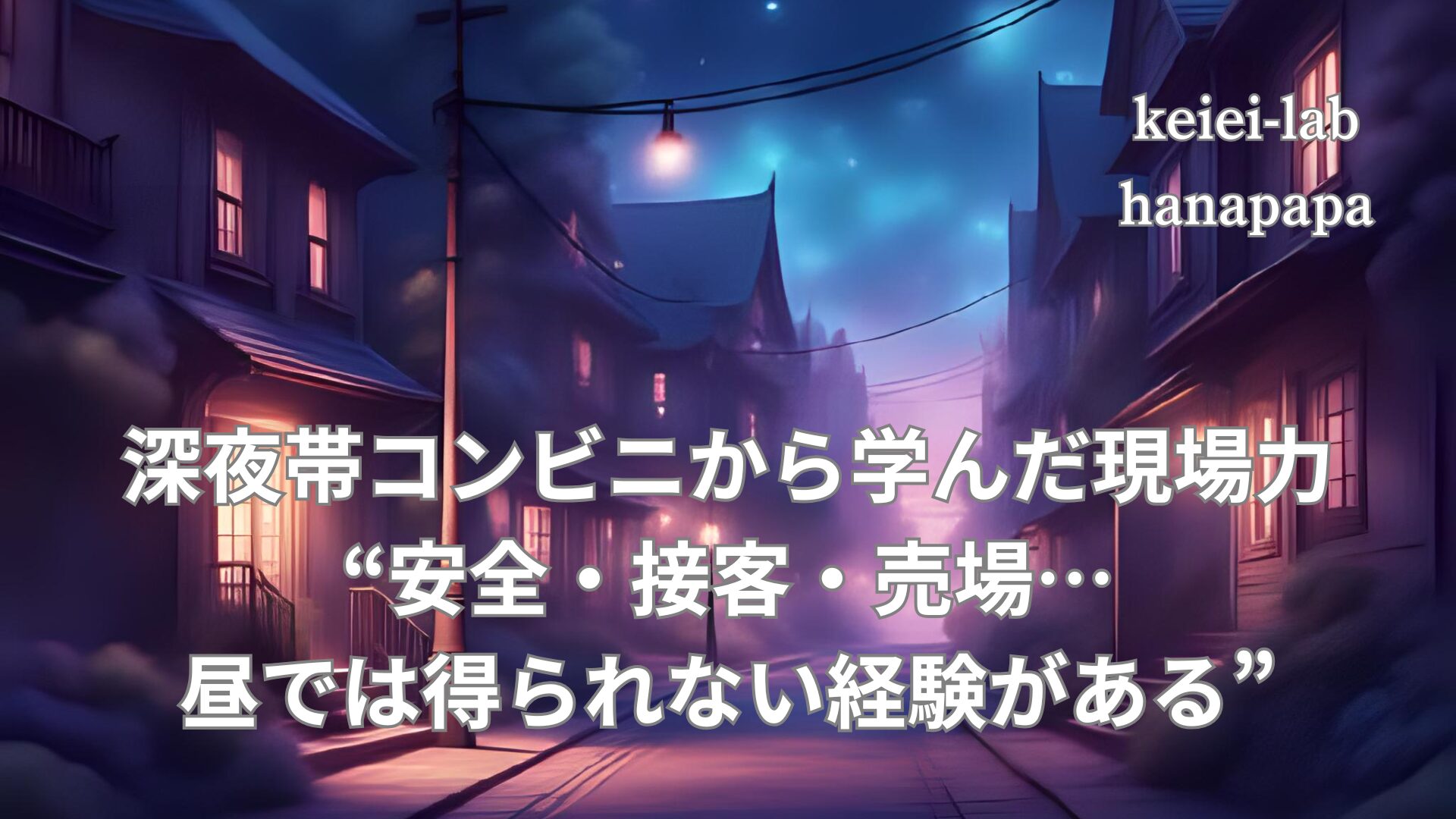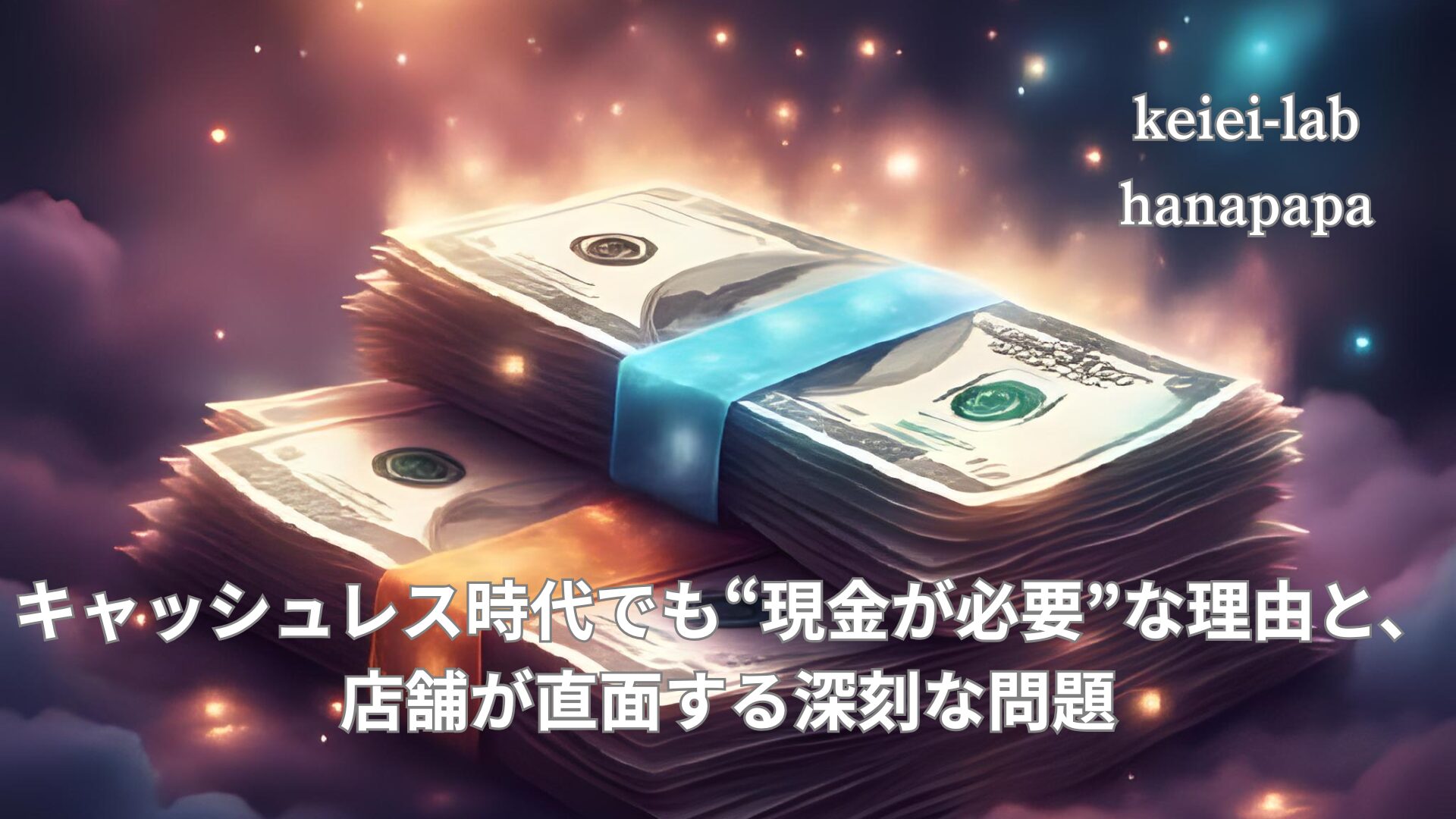【現場エピソード】万引きの本当のリスクは「商品代」ではなく「時間と心」|防犯の本質は“監視”ではなく“関心”【経営lab】
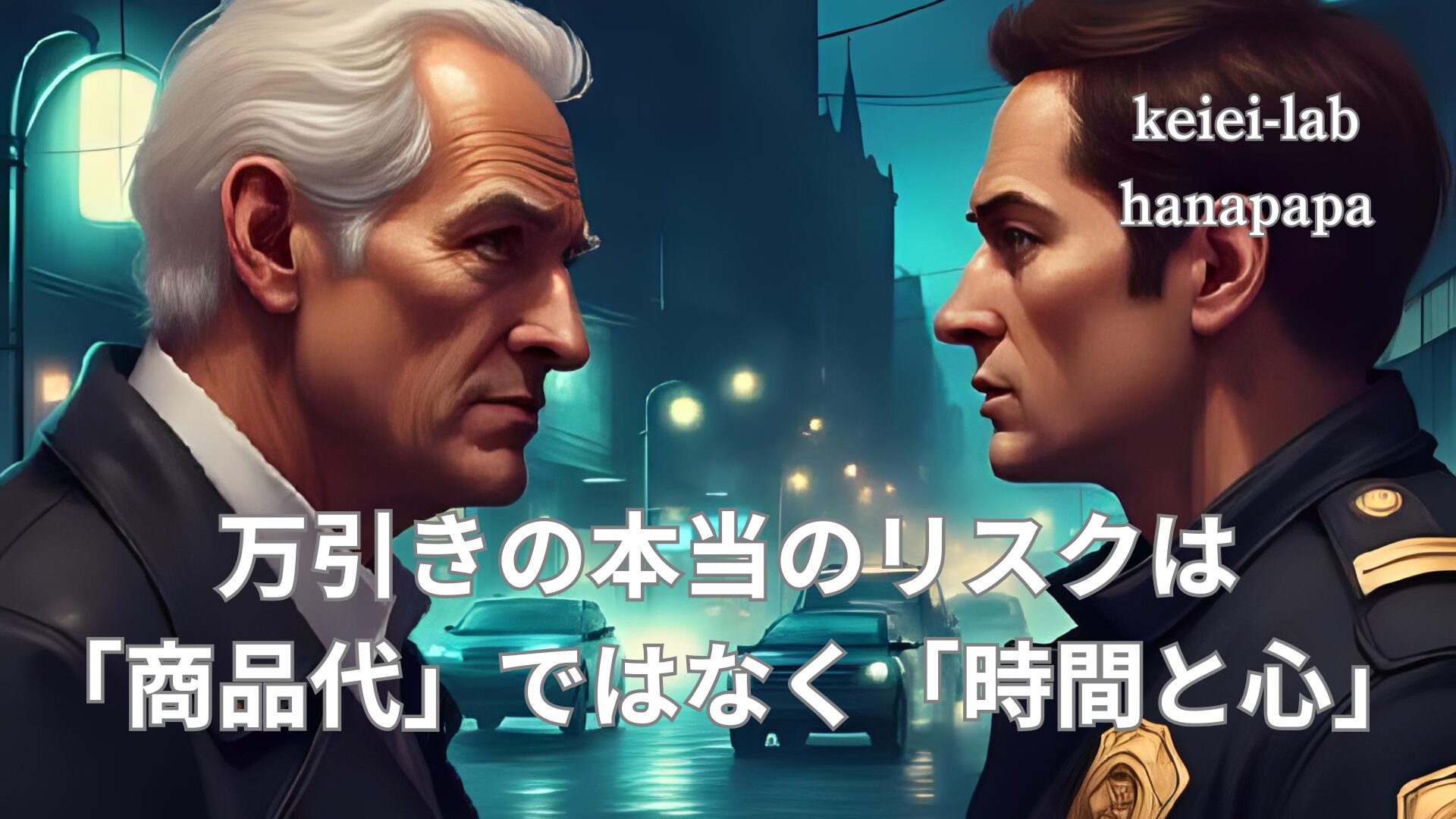
――「また万引きです。」 スタッフからその一言を聞くだけで、胸の奥がズシンと重くなる瞬間があります。
万引きによる損失は、商品代だけではありません。
警察への通報、状況の確認、書類作成――。 一つの対応が終わるまでに、2〜3時間はあっという間に過ぎていきます。 その間、他のお客様へのサービスも止まり、スタッフの心にも大きな疲労が残ります。
つまり万引きがもたらすのは、「お金の損失」ではなく「時間と心のロス」なのです。
この記事では、実際に現場で経験したエピソードをもとに、
万引き被害の“見えない損失”と、防止のために私たちができる日常の工夫についてお話しします。

万引きは「犯罪」というより、「人との関係が壊れる瞬間」。
だからこそ、“信頼を守る努力”を日常から積み重ねたいんです。
ではまず、万引きが発生したときに、実際にどれほどの“時間のロス”が発生するのか。
数字では見えない現場の実情から見ていきましょう。
万引きで一番大きいのは“時間のロス”
商品より重い、“見えない損失”
万引きによる損失と聞くと、多くの人が「商品の被害額」を思い浮かべます。
100円、200円。商品そのものの金額だけを見れば、大きな損害には見えないかもしれません。
しかし、現場に立つ私たちにとって本当に大きいのは、「時間の損失」です。
発覚後は警察への通報、事情聴取、被害届の記入、報告書作成――。
これだけで2〜3時間があっという間に過ぎます。
その間、スタッフはレジに戻れず、他のお客様へのサービスも止まり、売場の空気も重くなります。
“信頼”と“集中力”も同時に失う
時間だけではありません。 万引きが発生すると、スタッフの心にも小さなダメージが残ります。
「もっと早く気づけたのでは?」と自分を責めたり、
「また起きるのでは…」と不安を抱えたまま勤務することもあります。
お客様を信頼して接客するのが私たちの仕事。 しかし、そうした事件の後には、どうしても「疑いの目」で見てしまう瞬間があります。 そしてその小さな違和感が、お客様との信頼関係を少しずつ蝕んでしまうのです。

万引きが残すのは“疑い”という影。
一度失われた信頼を取り戻すには、時間以上の努力が必要なんです。
「時間のロス」は“経営リスク”でもある
スタッフが対応に追われる時間は、そのまま売上の機会損失になります。 ピークタイムに1人欠けるだけで、レジ待ちが長くなり、 結果的にお客様が離れてしまうこともあります。
また、警察対応や防犯報告など、オーナーや店長が拘束される時間も膨大です。
「防犯」は現場任せにできないからこそ、 “時間のリスク”を経営リスクとして管理する意識が必要です。
“心の余白”を奪われるという現実
万引き後の店内は、独特の空気に包まれます。
スタッフもお客様もどこか落ち着かず、店全体の雰囲気が冷たく感じることがあります。
この「空気の変化」こそ、見えない最大のロスです。
売場の明るさ、スタッフの笑顔、声かけのトーン―― どれも心の余裕があるときにこそ保たれるもの。 だから私は、万引き対策とは「警戒」ではなく、 “心の余白を守る仕組みづくり”だと考えています。

店の雰囲気は、商品よりも“心”がつくる。
万引きを防ぐ一番の方法は、“心の余白”をなくさないことなんです。
そしてもうひとつ、現場で見逃せないのが、
「まさかこの人が…」と思うような常連客による万引きです。
ここからは、その現実と対応の難しさについてお話しします。
常連客による万引きという現実
「まさかこの人が…」という瞬間
ある日のことでした。 毎日のように来店される80代の男性。 スタッフもみんな顔なじみで、「いつもありがとうございます」と自然に声をかけるお客様でした。
ところがその日、防犯カメラを確認すると―― 手荷物袋にお菓子をそっと入れる姿が映っていました。 信じられない思いで、胸の奥がギュッと痛くなったのを覚えています。
「まさか、この人が。」 そう思うと、声をかける足が震えました。
「理由」が分かっても、心は晴れない
声をかけると、男性はすぐに認めてくれました。 お金に困っていたわけではなく、「スリルが欲しかった」と。 小さな出来心だったそうですが、その言葉が余計に胸に響きました。
警察に引き渡すのは当然の手続き。 しかし、地域の顔見知りとしての気まずさ、他のお客様への影響―― どちらを考えても、心は重くなります。 被害額は数百円でも、心の傷はその何倍も大きいのです。

万引きは「損失」ではなく「喪失」。
信頼を失うことの痛みは、数字では測れません。
“人を責めず、再発を防ぐ”という難しさ
常連客による万引きは、厳しく対応すれば関係が切れ、 優しすぎれば再発する――非常に難しい問題です。 対応を誤れば、地域の信頼やスタッフの士気にも影響します。
私の店舗では、こうした事例があった際、スタッフ全員で共有ミーティングを行います。 「どう声をかければよかったか」「次に同じことが起きたらどう動くか」―― 責任を追及するのではなく、“気づきと対策”を共有する場にしています。
これは、ただ防犯のためだけではありません。 スタッフが恐れや不信感を抱えたままでは、 お客様への対応にも優しさが戻らないからです。
“信頼を取り戻す店”であるために
その後、男性のご家族が来店され、深く頭を下げられました。 「これからもお店を利用させてください」と言われたとき、 少しだけ心の重さが和らぎました。
信頼は、一度壊れても、努力で少しずつ取り戻せます。 大切なのは、「もう来ないでほしい」ではなく、「また来ても大丈夫」と思える店であること。
私たちの仕事は、モノを売ることだけではなく、
人と人の“関係を守ること”でもあります。

売場の防犯は、信頼の再構築から始まる。
それが、地域で続くお店の強さなんです。
こうしたケースは年々増加傾向にあります。
特に、孤立や習慣化による“常習的な万引き”が増えている現状も見逃せません。
次は、その背景と対策について触れていきます。
繰り返す常習性と高齢者の増加
「悪意」ではなく「孤独」から生まれる万引き
万引きというと「悪い人がやること」という印象を持たれがちですが、 現場にいると、そう単純ではないことに気づきます。
特に最近増えているのが、高齢者による常習的な万引きです。
金銭的に困っているわけでも、商品が必要なわけでもない。 ただ「話しかけてほしかった」「誰かに見てほしかった」―― そんな“孤独のサイン”のような行動に出る方が少なくありません。
実際に、万引き防止カメラの映像を見返すと、 手を伸ばす前に商品棚の前でしばらく立ち止まっている方が多いんです。 その背中には、どこか寂しさが漂っていました。
「いつも買ってくれる人だから」では防げない
常連のお客様だから大丈夫―― そう思ってしまう油断が、万引き被害につながることもあります。
以前、別の店舗であったケースでは、 毎日ウイスキーを買っていた女性が、同じ銘柄を何度も盗んでいたことが分かりました。 理由を尋ねると、「スリルを味わいたかった」「買うよりドキドキする」とのこと。
一見常識的に見える人でも、日々の生活の中で孤立やストレスを抱えていることがあります。 「この人に限って」という思い込みは、 防犯意識を弱め、スタッフの心にもダメージを残します。

“信頼”は大切。でも“油断”とは違う。
現場では、「信じる」と「備える」の両立が必要なんです。
地域全体で防ぐ“孤立型の万引き”
高齢者による万引きは、もはや店舗だけで解決できる問題ではありません。 地域全体で“見守りの目”を増やすことが大切です。
- 地域の見回り会や民生委員と情報共有を行う
- 「最近様子が違う」お客様を見かけたら、声をかける
- スタッフが高齢者対応のポイントを学ぶ
こうした取り組みを続けると、単なる防犯対策ではなく、 「地域の安心を守る活動」になります。 お店が“人を見守る場所”として機能すると、 それ自体が防犯の抑止力になっていくのです。
“防ぐ”よりも、“支える”という発想へ
万引きを完全に防ぐことは難しい。 でも、“支える関係”を築くことで、未然に防げるケースはあります。
「お元気ですか?」と声をかけるだけでも、 人は「見られている」「気にかけてもらっている」と感じるものです。 そうした小さなコミュニケーションが、犯罪を抑止し、信頼を育てます。
結局のところ、私たちが向き合うのは“モノ”ではなく“人”。
店が人を思い、人が店を信頼する――その関係性がある限り、 どんなトラブルもきっと乗り越えられると感じます。

万引き防止の第一歩は、「いらっしゃいませ」よりも「元気でしたか?」。
その一言が、孤立を防ぐ最大のセキュリティです。
では最後に、現場でできる防止策について。
“特別な対策”ではなく、“当たり前を徹底する力”がどれほど大きいかを見ていきましょう。
防止策:当たり前のことを当たり前に
特別な仕組みより、“日常の積み重ね”
万引きを完全に防ぐことは難しい。 けれど、日常の中でリスクを減らすことは十分にできます。
それは、防犯カメラでも張り紙でもなく、人の目と心の積み重ねです。
- 入店時のあいさつ: 顔を見て「こんにちは」と声をかける。
- 混雑時の巡回: 売場の奥にスタッフが立つだけで抑止効果がある。
- 会話の工夫: 「お探しのものありますか?」と一言添える。
どれも特別なことではありませんが、 これを“毎日欠かさず続ける”ことが防犯の基礎体力になります。 人の目が行き届くお店は、自然と雰囲気も明るくなり、 お客様にも「安心できる店だ」と感じてもらえるのです。
“声かけ”は、最強のセキュリティ
スタッフが「いらっしゃいませ」と言うその瞬間、 店は“無言の見守り空間”から“人のいる空間”に変わります。 万引きの多くは、「誰も自分を見ていない」という心理から起きるものです。
だからこそ、ちょっとした声かけが一番の防止策。 防犯対策であると同時に、お客様との関係づくりでもあります。
“防ぐための声”ではなく、“気にかける声”。 それが、店を守る優しい盾になります。

「監視」より「会話」。
店の安全は、人と人の“まなざし”で守られるんです。
“雰囲気づくり”も防犯の一部
お店が静まり返っていたり、スタッフが無表情でいると、 それだけで“スキ”が生まれます。 逆に、笑顔や明るい声が響く売場は、自然と犯罪を遠ざけます。
私は「明るい店は、強い店」と思っています。 どんなに忙しい時でも、笑顔のひとつ、挨拶のひと声―― それが結果的にお店を守る力になるのです。
まとめ:日々の積み重ねが最大の防止策
万引き対策というと、どうしても「商品を守る」イメージが先に立ちます。 けれど実際は、「時間と心を守ること」のほうがはるかに大切です。
スタッフが安心して働ける環境、お客様が気持ちよく買い物できる空間―― そのどちらも、日常の中で築かれていくものです。 「声をかける」「目を配る」「空気を整える」―― この“当たり前”を積み重ねることこそ、最大の防止策だと感じます。

防犯の本質は、「見張る」ではなく「見守る」。
今日も変わらず挨拶をする――
それが一番強く、一番やさしい防止策なんです。