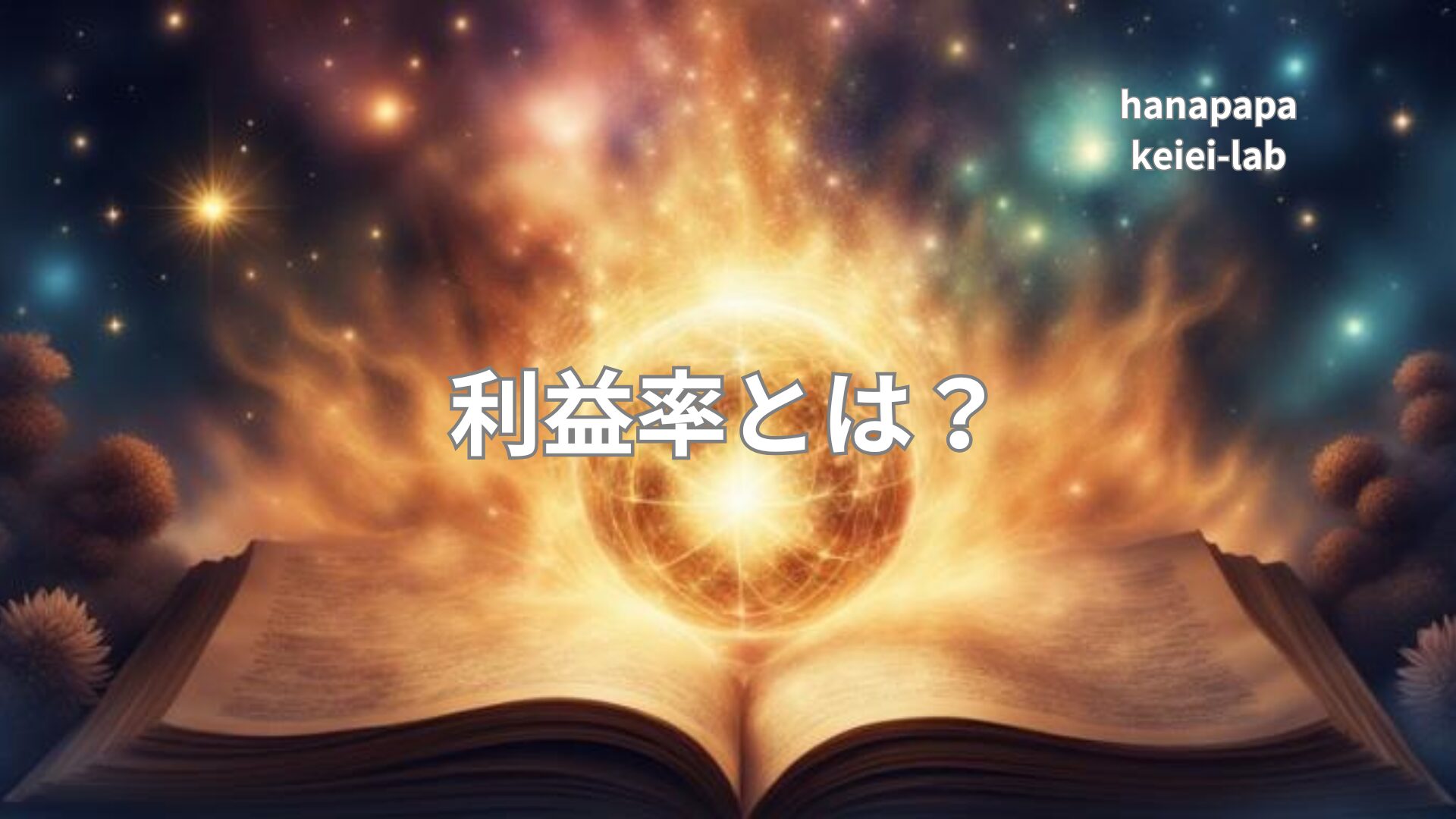【経営の基本】固定費とは?店舗経営で利益を出すために押さえるべき基礎知識【経営lab】

――「売上は上がっているのに、なぜか利益が残らない」。
店舗を経営していると、そんな悩みを感じたことはありませんか?
その原因の多くは、“固定費”のコントロール不足にあります。 固定費は、店舗運営に欠かせない経費でありながら、 気づかないうちに利益を圧迫する“見えない壁”にもなります。
私も以前、売上アップを目指して設備投資や人員強化を進めた結果、 一時的に売上は伸びたものの、固定費が先行してしまい、 実質的な利益はむしろ減ってしまったことがありました。 この経験から痛感したのは、「利益を出すには、まずコストの構造を理解すること」です。
この記事では、
固定費と変動費の違いから、売上とのバランスをとる考え方、 そして経営判断に役立つ実践的な視点までを、現場経験をもとに解説していきます。

現場が好きな人は数字がちょっと苦手、逆に数字が得意な人は現場の感覚にうとい——そんな関係ってありますよね。でも、今回は数字についてもしっかり学んで、どちらかに偏らず、両方を理解できるようにしていきましょう。
ではまず、そもそも固定費とは何か?
変動費との違いを押さえながら、店舗経営の“コスト構造”を見ていきましょう。
固定費とは?変動費との違い
“売上に関係なく発生するコスト”が固定費
固定費とは、売上の増減に関係なく、毎月ほぼ一定額で発生する経費のことです。
店舗を営業している限り、売れても売れなくても支払い続ける必要がある費用ですね。
一方で、販売数や売上に比例して増減する費用を「変動費」と呼びます。
固定費と変動費、この2つを分けて考えることが、経営の第一歩です。
固定費と変動費の具体例
たとえば、コンビニや小売店の場合は次のように分類できます。
| 費用の種類 | 主な内容 | 具体例 |
|---|---|---|
| 固定費 | 売上に関係なく発生する費用 | 家賃、水道光熱費(基本料金)、人件費(社員・固定シフト)、通信費、保険料など |
| 変動費 | 売上や販売量に応じて変わる費用 | 仕入れ原価、販売手数料、包装資材、販促キャンペーン費用など |
このように見ると、固定費は「守るためのコスト」であり、 変動費は「売るためのコスト」だと分かります。 どちらも必要ですが、そのバランスを間違えると利益が圧迫されてしまうのです。
固定費が重くなると、利益は“動きにくくなる”
固定費が多い経営は、一見すると安定しているように見えますが、 売上が下がったときにすぐに赤字化しやすいという弱点があります。 なぜなら、売上が減っても出ていくお金が変わらないからです。
たとえば、月の売上が500万円の店舗で固定費が300万円ある場合―― 売上が10%落ちても、固定費はそのまま300万円。 結果として利益率が一気に下がってしまいます。
変動費が多い経営は、柔軟だけど不安定
逆に、変動費が中心の経営スタイルは、売上の波に合わせて支出を抑えられる反面、 仕入れや外注に頼る部分が多いため、コストコントロールが難しくなります。
つまり、「柔軟さ」と「不安定さ」は表裏一体なんです。
固定費が高すぎても苦しい、変動費が多すぎても読めない。 経営で大切なのは、この2つのバランスを常に意識することです。

固定費と変動費のバランスは“体温”みたいなもの。
高すぎても低すぎても、経営の健康を崩します。
では次に、固定費と売上の関係をもう少し深掘りしてみましょう。
「売上を伸ばすと固定費も増える」――その“天秤のバランス”をどう管理するかが、経営の腕の見せどころです。
売上アップのために固定費も増える
「売上を伸ばす=支出も増える」は自然な流れ
店舗経営では、売上を伸ばそうとすると、どうしても固定費も増えていきます。
これは決して悪いことではありません。 むしろ、成長のためにはある程度の投資が必要です。
たとえば、次のような取り組みを行うときには、必ずコストが発生します。
- 売場を改善する(棚替え・新しい什器の導入)
- 接客品質を高める(研修・マニュアル整備・教育時間の確保)
- 店舗環境を良くする(清掃や照明の見直し、内装リニューアル)
こうした施策は、売上を上げるために必要な「前向きな固定費」です。 ただし、この支出はあくまで“未来への投資”としてコントロールすることが大切です。
固定費の中で最も影響が大きいのは「人件費」
特にコンビニや小売店では、固定費の中でも人件費の割合が非常に高くなります。
人件費は店舗の活力そのものでありながら、同時に経営を圧迫しやすい項目です。
人を増やせば売場の回転が良くなり、サービス品質も向上します。
しかし、売上が思うように伸びなければ、その分だけ固定費率が上昇し、 結果的に利益が削られてしまうリスクがあります。
大切なのは、「人を減らすか」ではなく、
“人を活かす仕組み”を整えることです。 スタッフ教育や役割分担を見直し、限られた人件費の中で最大の成果を出すことが、 長期的な固定費コントロールにつながります。

従業員の人数が多いと、一人ひとりの能力を最大限に引き出すのはなかなか難しいですよね。でも、人数が少ないと、その分しっかり向き合って指導しやすくなります。固定費をしっかり計算したうえで、一人ひとりを丁寧に育てていく――私はそんな形の経営が好きですね。
固定費と売上の関係は“天秤”
固定費が先行すると、利益が圧迫される
売上を上げようと投資を増やすことは悪くありません。
しかし、固定費が先行しすぎると利益が圧迫されるという落とし穴があります。
たとえば、売上アップを見込んで人を増やしたり、設備を導入したりしても、 結果的に思ったほど売上が上がらなければ、その分だけ固定費率は悪化します。
これは、売上と固定費の“天秤のバランス”が崩れた状態です。 片方を上げればもう一方も調整しなければ、経営の安定は保てません。
バランスを保つための3つの視点
では、固定費と売上のバランスを保つには、どうすれば良いのでしょうか? ポイントは、次の3つです。
- ① 投資の目的を明確にする:「なぜお金を使うのか」を明言できる状態で動く。
- ② 成果を“率”で見る:売上高だけでなく、「固定費率(固定費÷売上)」を定期的に確認する。
- ③ 固定費は“増やすため”ではなく、“売上を支えるため”に使う:支出の先に“回収イメージ”を描く。
この3つを意識するだけで、無駄な支出を減らし、 必要な投資にメリハリがつけられるようになります。

まずはスモールスタートが大切だと思います。小さく始めて、しっかりと土台を固めながら、少しずつその土台を広げていく。まるで階層を積み上げるように成長していく、そんな経営方針が理想ですね。
経営者に求められるのは、“コストを見る習慣”
経営判断で難しいのは、「数字を見ること」よりも「数字を習慣化すること」。
月次報告のたびに経費を振り返り、「今月の固定費率は何%だったか?」を確認するだけでも、 経営の精度は確実に上がります。
最初は難しく感じても、数字を追いかける習慣が身につけば、 「どこに投資すべきか」「どこを引き締めるべきか」の感覚が自然と磨かれます。 それが本当の意味での“現場経営力”だと思います。
では最後に、固定費を「削る」ではなく「活かす」ための考え方をまとめましょう。
経営の鍵は、“管理しながら投資する”バランスにあります。
まとめ:固定費は「管理しながら投資する」視点で
固定費は「削る」より「活かす」
固定費は経営において、最もコントロールが難しい項目です。 だからこそ、“悪者扱い”されやすいのも事実です。
しかし、固定費は決して削るだけのコストではありません。 店舗を維持し、スタッフを育て、サービスの質を守るための「基盤への投資」でもあります。
売上を伸ばすことだけに目を向けると、コストが後回しになりがちですが、 固定費の適正化は「利益を生み出す仕組みづくり」そのものです。 管理しながら使う――この感覚を持つことが、経営を長く続けるためのコツです。
「数字を見る」ことは「現場を見る」こと
経営数字というと、どうしても苦手意識を持つ方が多いですが、 数字を見ることは、現場のリアルを知ることでもあります。
たとえば、光熱費が増えているのは「冷蔵設備の劣化」かもしれない。 人件費が上がっているのは「教育の仕組み不足」かもしれない。 数字はすべて、現場からのサインです。
数字を追うことで、感覚的な経営から脱し、 問題の芽を早期に発見できるようになります。 それは決して難しい分析ではなく、“現場に耳を傾ける姿勢”なんです。

数字は「現場の声」を翻訳してくれる言葉。
苦手な人ほど、経営の伸びしろが大きいんです。
固定費の適正化は「未来への余白」を生む
固定費を見直すことの本当の目的は、節約ではありません。 余計な支出を減らすことで、未来に投資できる“余白”を生むことです。
新しいサービスへの挑戦、スタッフへの還元、店舗改善のための余裕―― これらはすべて、固定費を整えた先に生まれるチャンスです。 つまり、経営とは「今を守りながら、未来を育てる」行為そのものなのです。
“数字の経営”から“人の経営”へ
最終的に、経営を支えるのは数字ではなく“人”です。 固定費を理解することで、
「どこに力を入れるか」「誰に任せるか」といった判断も明確になります。
固定費の管理とは、チームの動きや現場の努力を見える化すること。 それは経営者が“人を信頼して任せるためのツール”でもあるのです。

固定費を整えると、チームも整う。
経営の数字は、現場の“信頼の証”なんです。
廃棄を減らせと言われ続ける現場。でも、売上を作るには一定の“攻め”も必要です。
廃棄率を単なるコストとして見るのではなく、売上を伸ばすための投資という視点から整理した共通入口はこちら。
▶ 廃棄率2〜3%が適正な理由