【店舗運営】客単価を上げるには?売れる商品構成と導入の工夫を解説

――“売れる商品構成”でお客様の「もう1品」を引き出す
売上を伸ばす基本式はシンプルで、こうです。
売上 = 客単価 × 客数
客数アップは、立地・天候・周辺イベントに左右されがち。
だから現場で「安定的に伸ばしやすい」のは、客単価のほうです。
とはいえ…
- 単価の高い商品を置いても動かない
- 「セットでどうぞ」を言っても反応が薄い
- 売場が忙しくて、仕掛けが続かない
これ、めちゃくちゃ分かります。

結論:
客単価アップに必要なのは「高い商品」ではなく、お客様の心理に合った商品構成と導線設計です。
“もう1品”が自然に起きる形を作ると、客単価は上がります。
客単価を上げる=「攻め」ですが、攻めるには基準が必要。
廃棄をゼロに寄せすぎると欠品(機会ロス)が増え、攻めすぎるとロスが増える。
このバランスの共通入口は、こちらで整理しています。
売上は「客単価 × 客数」で決まる
――“数”ではなく、“質”で伸ばす発想を
売上を上げるための方程式は、非常にシンプルです。
売上 = 客単価 × 客数。
つまり、来店客数を増やすか、1人あたりの購入金額を上げるかの2択。
ですが、実際の現場では「客数アップ」は天候・立地・周辺イベントなど外的要因に左右されやすく、
安定的に伸ばしやすいのは“客単価”の方です。
例:あるコンビニ店舗のケース
- 平均客単価:560円 →「おにぎり+ドリンク」が定番構成
- 売場改善後:620円(約10%UP)
→ ホットスナックコーナーを入口動線に変更し、レジ前で“もう1品”提案
このように、客数が変わらなくても、
1人あたり60円アップすれば、
1日1,000人来店で +6万円/月+180万円(年換算) の売上増につながります。
…ね、これだけで店の空気が変わります。
🔹「客単価=接点単価」という考え方
私が好きな捉え方がこれです。
客単価が上がる店は、だいたい売場に「きっかけ」があります。
- “ついで買い”を生む売場構成
- “気分買い”を刺激するPOP・見せ方
- “自分ごと化”を促す限定・話題商品
売上を上げるとは、客数を増やすことだけじゃなく、お客様1人ひとりの“買い方”を変えること。
ここに店舗の価値づくりの本質があります。

ブラックサンダー1個売る方法を考えてみては?意外とできそうじゃないですか?

時代のニーズに応える商品を取り入れる
――“今売れる理由”をつくるのが客単価アップの近道
客単価を上げるためにまず考えたいのは、
「今のお客様が、なぜそれを買いたいのか」 という購買動機です。
「今のお客様が、なぜそれを買いたいのか?」
=購買動機を作れる商品を、売場に入れる。
トレンドや社会の変化で、“買う理由”は常に変わっています。
その変化を掴んで売場に反映できると、客単価は自然に伸びます。
時代性を“フック”にした商品展開例
| フック | 商品例 | ねらい |
|---|---|---|
| 災害・備え | 保存食・備蓄水・モバイルバッテリー | “必要性”で買う。リピート率が高い。 |
| 季節 | 冷感グッズ・温感飲料・限定スイーツ | “今だけ”感で購入頻度を高める。 |
| 心理 | 自分へのご褒美系スイーツ・推し活グッズ | “感情価値”で単価を上げる。 |
| 生活 | 時短惣菜・個包装食品 | “便利”でまとめ買いを促す。 |
🔹 導入のポイント(ここが勝負)
- 「世の中で話題になっているもの」を、“お客様の生活目線”で再編集して売場に置く。
- 新しい商品は単発で終わらせず、関連アイテムを並べて“提案型展開”にする。
- 「今、なぜ売れているのか?」をチームで共有する。

最近は“プロテイン”って言葉が入っているだけで、若い世代の反応が全然違いますね。ザバスのような有名ブランドも強いですし、栄養管理系の商品全体が注目されています。健康志向が高まっているのを実感しますね。
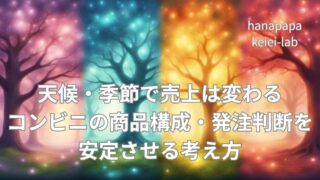
ファン層に刺さる「一番くじ」などの高頻度商品
――“好き”を刺激する仕掛けは、客単価を超えて“来店回数”も伸ばす
売上を支えるのは、1回の購買単価だけではありません。
客単価 × 購買頻度(来店回数)
この両方を同時に押し上げるのが、ファン層向けの“高頻度商品”です。
代表例が「一番くじ」。エンタメ性×限定性のある商品は、強い来店動機になります。
高頻度商品の導入で得られる3つの効果
| 効果 | 内容 |
|---|---|
| ① 集客効果 | ファン層が「発売日」を狙って来店するため、特定日・時間帯の来客数が増える。 |
| ② 客単価アップ | 高単価くじに加え、関連グッズ・お菓子・飲料など“ついで買い”が発生。 |
| ③ 店舗ロイヤルティ向上 | 店員の対応・品出しスピードが評価され、「あの店なら買える」信頼が生まれる。 |
🔹 導入・運用のポイント(やることは3つ)
1️⃣ ターゲットを明確にする
→ 商品テーマが合致する層(学生・社会人・女性・ファミリー)を把握。
→ SNS・チラシなど、発売日前後の訴求で認知を高める。
2️⃣ 関連商品の展開で売上を拡張する
→ 「くじ+キャラクター菓子」「くじ+飲料コラボ」など、関連陳列で購買点数を増やす。
3️⃣ 導入タイミングと在庫管理を最適化する
→ 発売直後は集中販売、ピーク後は在庫を関連棚へ移動して長期販売を狙う。

一番くじって、当たれば一瞬で売り切れるんですけど、外れたときはとんでもない在庫になりますね。動かない商品は本当に、どれだけ時間が経っても動かない…。仕入れの読みの難しさを痛感します。
廃棄を減らせと言われ続ける現場。でも、売上を作るには一定の“攻め”も必要です。
廃棄率を単なるコストとして見るのではなく、売上を伸ばすための投資という視点から整理した共通入口はこちら。
▶ 廃棄率2〜3%が適正な理由

まとめ:フック商品と関連商品の掛け合わせが有効
――“一品で終わらせない売場設計”が客単価を底上げする
客単価を上げるためには、単に高単価商品を置くだけでは不十分です。
大切なのは、「お客様が自然にもう1品手に取ってしまう流れ」をつくること。
その鍵になるのが、
話題性のある “フック商品” と、
それに連動した “関連商品” の組み合わせです。
例:関連展開の具体イメージ
| フック商品 | 関連商品 | 目的・狙い |
|---|---|---|
| 一番くじ | キャラクター菓子・ドリンク | ファン層の“ついで買い”を誘発 |
| 防災グッズ | 保存食・カセットボンベ | “必要性”からの買い足しを促す |
| 季節スイーツ | コーヒー・ギフト袋 | “一緒に楽しむ体験”を提案 |
| 推し活グッズ | ノート・ペン・キーホルダー | “感情の共感”を広げる |
✔ お客様の「目的買い」を「発見買い」に変えることが、
客単価アップの最大ポイントです。
客単価を上げる“売場設計3ステップ”
1️⃣ フックを立てる
→ 目立つ位置に話題性のある商品を配置し、立ち止まるきっかけをつくる。
2️⃣ 関連性で広げる
→ フックの横に“合わせ買い”が想定される商品を配置。
「一緒に使う」「一緒に楽しむ」体験を連想させる。
3️⃣ 体験を提案するPOPで締める
→ 「今ならセットでお得」「季節限定ペア」など、理由のある買い方を演出。

フック商品は“きっかけ”にすぎません。
そこに「関連性」と「ストーリー」を加えると、
1人あたりの買い物が変わります。
現場で工夫できる範囲の積み重ねが、客単価アップの原動力になります。
🔹 仕組み化の重要性(センス任せにしない)
客単価アップが続かない店の共通点は、だいたいこれです。
- 担当者の気分で売場が変わる
- 売れた理由が共有されない
- 次の人に引き継がれない
逆に、伸びる店はこうしています。
- 商品導入時に「関連提案」をセットで決める
- フック商品は週・月単位で入れ替え、売場の“鮮度”を保つ
- 売場写真を共有し、成功パターンを横展開する
客単価アップとは、単発の施策ではなく「設計と習慣」の積み重ねです。
現場で回すためのミニチェックリスト(5分で確認)
- □ 今日の売場に「フック(立ち止まる理由)」はあるか
- □ フックの横に「関連商品」が置かれているか
- □ POPは“商品の説明”ではなく“買う理由”になっているか
- □ 売る商品を増やしすぎて、棚が散っていないか
- □ 攻めるなら、発注と在庫に「基準」があるか
基準がないと、攻めは続きません。




