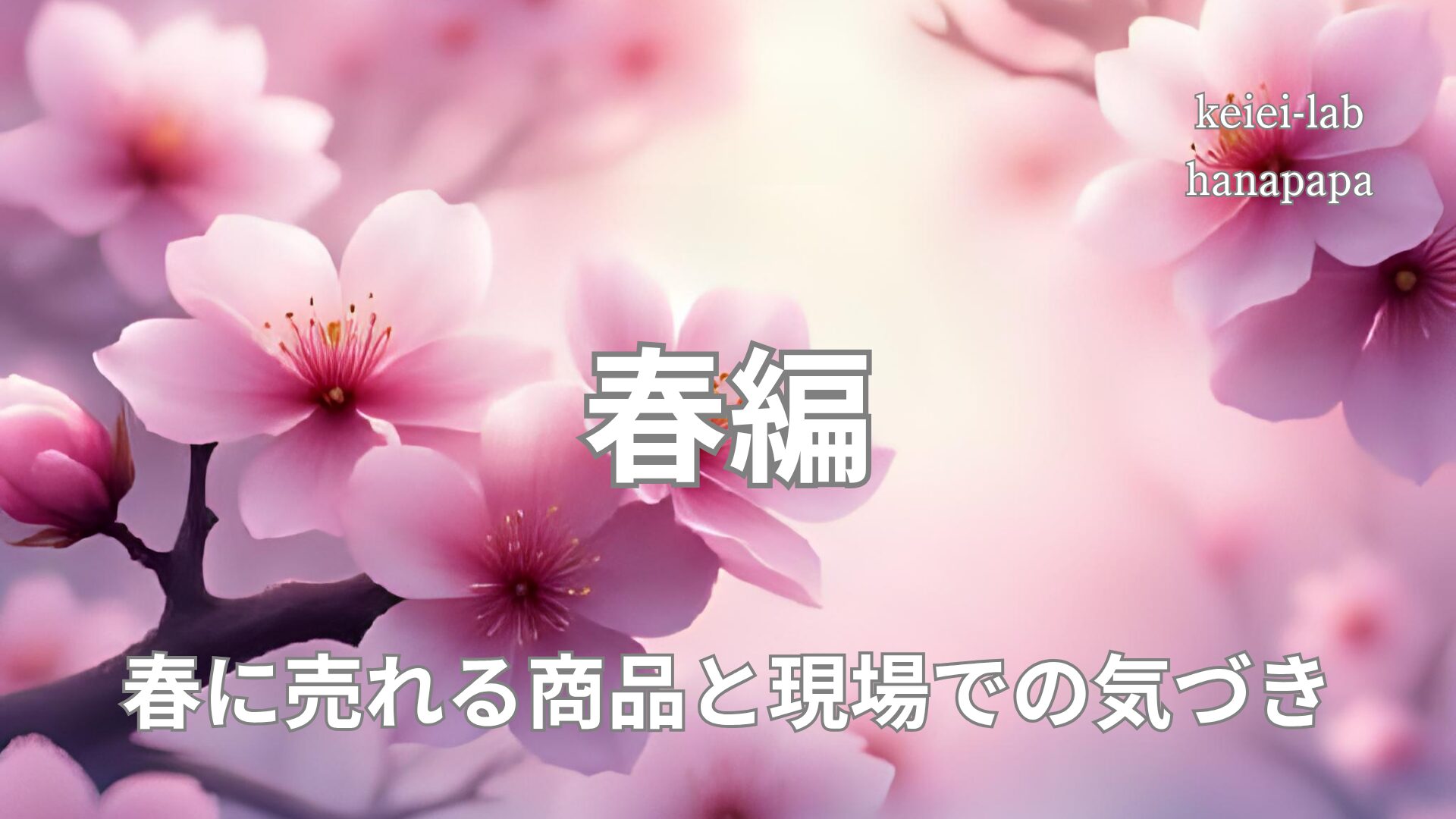【現場エピソード】夏祭り・花火大会で売上急増!現場で学んだ対応とオペレーションの工夫【経営lab】

――夏祭りや花火大会の夜、店内がまるで“戦場”のようになる瞬間、ありませんか?
普段の3倍以上の来客。冷たいドリンクは飛ぶように売れ、氷やビールの補充が追いつかない。
スタッフも汗だくで走り回り、レジ前には長蛇の列。気づけばバックヤードは混乱状態……。
そんな“てんやわんや”の中でも、売上を最大化し、チームを崩さず乗り切るにはどうすればいいのか?
私自身、何度も失敗と試行錯誤を繰り返してきましたが、そこにはある共通点が見えてきました。
それは、「やることを絞る」「動線を整える」「戦略的に“冷やす”」というシンプルな原則です。
今回は、花火大会や盆踊りといった“売上ピーク日”の現場で実践した、
現場スタッフがパニックにならないためのオペレーション設計と、
売上を落とさず満足度を上げる工夫をお伝えします。

花火大会や盆踊りの時期は、会場からの距離に関係なく、大なり小なり影響を受けるお店も多いですよね。お祭りの中心にあるお店だけでなく、少し離れた場所でも変化はあります。そんな時は、ぜひこの記事を参考にしてもらえればと思います。夏祭りの日は「準備7割・当日3割」。
ではまず、“夏祭りオペレーション”の基本中の基本、
「やることを単純化・明確化する」ところから見ていきましょう。
大前提:やることを単純化・明確化する
「売れるから何でもやる」は危険
夏祭りや花火大会の日は、“とにかく売れる”特別な日。
気づけば普段扱わない商品を追加し、店内は一気に混乱します。
でも、売れる日ほど大事なのは、「やることを増やす」ではなく「やることを減らす」ことです。
私も以前は、「せっかくだから焼きそばも」「ついでに氷カップも」と詰め込みすぎて、
結果的にスタッフがパンクし、補充もレジも回らず在庫を余らせてしまった経験があります。
担当を固定して“動線”を断たない
夏祭りのようなピーク時は、「誰が何をやるか」を明確にしておくことが最優先です。
「とりあえず手が空いた人がやる」は、かえって混乱を招きます。
たとえば、以下のように担当を分けるだけで、現場の動きが格段にスムーズになります。
- 補充担当:飲料・酒・氷を切らさない。レジに入らない専任。
- レジ担当:会計に集中。混雑時も袋詰めを手早く。
- バックヤード:氷開封・飲料冷却・補充ループをキープ。
こうして担当を固定することで、
「誰が何をやっているのか分からない」状態がなくなり、
スタッフ同士の声かけも短く、的確になります。

忙しい日ほど、“担当の固定化”がチームを守る。
動線がブレない現場は、ミスも少なく、士気も高いんです。
ムダ動線をなくして“手が届く配置”にする
ピーク日の混乱の多くは、「配置」と「距離」から生まれます。
補充品を取りにいくたびにスタッフが移動していては、
わずかな時間でもロスが積み重なります。
たとえば、氷・飲料・保冷袋をすぐ取れる位置に置くだけで、
1時間あたりの対応数が大きく変わります。
お祭り日は「走らないで届く距離」を意識するだけで、生産性が上がります。
こうして作業を単純化し、担当を明確にすることで、
スタッフが自信を持って動ける環境が整います。
混乱しがちな繁忙期こそ、「単純さは強さ」になるのです。

ここに挙げたことは『そんなの当然でしょ!』と思うかもしれません。でも、分かっていても一つひとつをしっかり準備しておくことで、当日の動きが全然違ってきます。当たり前のことを当たり前にやるのって、本当に大変なんですよね。計画を立ててもトラブルは必ず起きるもの。だからこそ、潰せる問題は今のうちに一つずつ潰していきましょう。
売上の柱は「飲料・お酒・氷」――ここに戦力を集中
“売れる場所”と“売れる瞬間”を見極める
お祭りの日は、通常営業とはまったく違う“波”がやってきます。
特に、売上の7〜8割を占めるのが「飲料・お酒・氷」。
ここを制すれば、その日の売上が決まると言っても過言ではありません。
逆に言えば、ここで在庫切れや補充ミスが起きると、
どれだけ他のカテゴリーを頑張っても全体の数字が落ちてしまうのです。
補充は“専任制”でフェースを守る
飲料・酒・氷の補充担当は、レジや接客に入らず、“専任”で配置します。
理由はシンプル。補充が止まると、フェース(棚前)が崩れ、
お客様の購入テンポが一気に鈍るからです。
- 氷の扱い:店頭には開封済み氷の“保冷用プール”を設置。バックヤードで氷ストックを循環。
- ビール補充:缶押し込みを徹底し、2〜3段目の定番を“常に冷えた状態”で確保。
- 価格表示:氷・ドリンク・ビールはA4札で外からも見える位置に配置。
このように「補充ループを切らさない設計」にしておくと、
お客様が“止まらず買える”流れを維持できます。
つまり、補充=売上維持のインフラなのです。

お祭りの日は、売るより“冷やす”が先。
冷えていれば、勝手に売れる。これが夏商戦の鉄則です。
「冷却」と「見える化」で体感スピードを上げる
お祭りの夜は、時間との勝負。
いかにお客様に「すぐ買える・すぐ冷えてる」と感じてもらえるかが鍵です。
そのために重要なのが、“見える冷却”です。
たとえば、バックヤードにだけ氷を置くのではなく、
お客様の目に入る場所で“開放型クーラーBOX”を設置すると、
「ここで買えば冷えてる」と直感的に伝わります。
- 氷・ドリンクはライトを当てて視認性UP。
- 「冷えてます!」POPは視覚的な購買スイッチに。
- 価格札は“見やすさ優先”で大きく表示。
戦略的に冷却エリアを設計し、スタッフを補充専任にするだけで、
店内の回転率も客単価も大きく変わります。
夏祭りの勝敗は、「いかに冷やせるか」で決まるのです。

夏祭りの時期は、浴衣姿や景色を楽しみながら屋台の前に並ぶのも、ひとつの風情かもしれませんね。でも一方で、効率よく買い物を済ませて花火大会の会場へ向かいたいという方も多くいます。私たちのお店は、そんなお客様の“風情を楽しむ場所”というより、“スピードと快適さ”を提供する場所。屋台ではなく、いつものコンビニだからこそ、素早い対応を心がけたいですね。
ホットスナック/軽食は種類を絞る――スピード≒満足度
“フルラインナップ”が逆効果になる理由
お祭りの日は、どの商品もよく売れるからといって、
すべてのホットスナックを用意するのは逆効果です。
フライヤーの回転が追いつかず、レジ待ちが伸び、結果的にお客様を逃してしまうからです。
私も以前、焼き鳥・唐揚げ・ポテト・アメリカンドッグなど、
通常より種類を増やして臨んだことがありました。
ところが、仕込みに追われ、油が劣化し、肝心のピーク時に供給が止まるという失敗を経験しました。
“選ばせない設計”でスピードを最大化
お祭り当日は、商品の多さよりも「迷わず買える環境」を整えることが重要です。
レジ前でお客様が考え込む時間を減らすことで、列の回転率が上がり、スタッフの負担も軽くなります。
- 注力商品:焼きそば・フランク・おにぎり(定番3種)など、回転率重視の構成に。
- 表示POP:おすすめを3点に限定。「迷ったらコレ!」など誘導ワードを活用。
- 導線短縮:店頭テーブルに「箸・おしぼり・ソース」をまとめ、戻り動線をゼロに。
選択肢を減らすことで、お客様も「すぐ買える」「すぐ受け取れる」と感じ、
“スピード満足度”が上がります。

日常の業務において商品の種類が多いことは、お客様にとって大きなメリットですよね。でも、夏祭りのような繁忙期は、あまりに種類を増やしすぎると作業効率が下がったり、レジの待ち時間が長くなってしまうこともあります。そんな時こそ、種類を絞ってスムーズな提供を心がけるほうが、お客様にとっても、私たちにとっても良い結果につながると思います。
在庫ロスを防ぎ、スタッフの集中を生む
種類を絞ることは、単にスピードを上げるためだけではありません。
スタッフが同じ作業を繰り返すことで“集中状態”に入り、ミスも減り、動きも洗練されていきます。
さらに、仕込み量を絞ることで在庫ロスを防げるため、
繁忙期後の“残り物問題”を減らすことにもつながります。
お客様にとっても、スタッフにとっても、
「迷わない・待たない・疲れない」仕組みこそが、
夏祭り営業の理想のオペレーションなのです。

作業をシンプルにすればするほど、他の場所がどれくらい忙しいのかが見えやすくなりますよね。ちょっと手が空いたときに『あそこ大変そうだから手伝いに行こうかな』と思えるような、そんな助け合いが自然にできる環境が理想だと思います。
では次に、売上を支える“店頭販売”をどう最適化するか。
「見える・届く・すぐ買える」売場設計のコツを紹介します。
店頭販売のコツ:見える・届く・すぐ買える
“見える売場”は買いやすい売場
店頭販売で一番大切なのは、「見えること=気づいてもらえること」。
お祭りの日は、通行客も多く、立ち止まってもらうだけで勝負が決まります。
のぼり旗や提灯、ライト、POPなど、
“動き”と“光”をうまく使うと、通行中の人が自然と視線を向けてくれます。
また、夜間営業では照明を「白」ではなく“暖色寄り”にするだけで、売場が温かく見えます。

この時ばかりは、いつもお店を利用してくださっている方ばかりではありません。『ここにコンビニがあるんだ!』と初めて知る方も多いんです。だからこそ、何がどこにあるのかをわかりやすく伝える工夫が大切です。
“届く距離”にすべてを置く
夏祭りの混雑時は、わずかな動きの差がオペレーションを左右します。
補充や手渡しをスムーズにするために、「手を伸ばせば届く距離」に全てを集約しましょう。
- 陳列:商品・氷・保冷袋・袋類をスタッフの手元1歩圏内に配置。
- 決済:臨時レジやQR決済を導入し、会計動線を短縮。(現金ならお釣りの発生しにくい金額)
- まとめ買い促進:「ビール+氷で◯円OFF」「飲料3本セットでお得!」などを明確表示。
このように“届く距離”に必要な物を置くだけで、
スタッフのストレスが減り、ミスも激減します。
お客様にとっても「すぐ買える」スピード感が生まれます。

「走らないで届く距離」が繁忙期の最強動線。
体力よりも“配置力”が売上を決めるんです。
“すぐ買える設計”で回転率を上げる
お祭りでは、「今すぐ欲しい」が購買の最大モチベーションです。
だからこそ、“買うまでの手間”をゼロにする設計が重要になります。
- すぐ見えるPOP:「冷えてます!」「今すぐ飲めます!」など行動を促す一言を。
- すぐ渡せる動線:レジ前に保冷バッグ・袋を常備。お会計後すぐ渡せる体制を。
- すぐ決められる陳列:売れ筋を“縦1列に並べる”ことで、迷わず選ばせる。
この3ステップを意識するだけで、列の回転が早まり、
スタッフの負担も減り、売上も自然と伸びていきます。
現場では「とにかく売る」よりも、「とにかく詰まらせない」。
この意識で設計することが、繁忙期のオペレーションを支える基本です。
では次に、売場での“声かけ”をどう活かすか。
お客様の足を止め、購買を促す「ひと声」の工夫を見ていきましょう。
声かけスクリプト:お客様の足を止める“ひと声”の工夫
“売り込み”ではなく“気づかせる”
お祭りや花火大会の日、通行客の流れは早く、誰もが「とりあえず急いでいる」状態です。
そんな中で立ち止まってもらうには、ただ「いらっしゃいませ!」と叫ぶだけでは足りません。
大事なのは、お客様の“気づきスイッチ”を押すひと声です。
たとえば、こんな声かけがあります。
- 「冷たいドリンク、すぐ飲めますよ!」
- 「氷、残りわずかです!」
- 「花火の後はこれが一番人気です!」
この3つには共通点があります。
それは“商品の説明”ではなく「お客様の行動や状況」に寄り添った声になっていることです。
“今”を伝える言葉が一番響く
お祭りのような非日常では、お客様は「限定」「今だけ」というワードに敏感に反応します。
だからこそ、声かけには“ライブ感”を意識すると効果的です。
- 「今、冷たいの出たばかりです!」
- 「さっき完売した商品、追加入りました!」
- 「最後の一本ですよ!」
このように“タイミング”を伝えると、
その瞬間に「買う理由」が生まれます。
声のトーンは、明るく・短く・テンポよく。 それだけで売場の空気が一気に活気づきます。

ちょっと男性目線になってしまうかもしれませんが、私の場合、“おしゃれ”とか“美味しそう”というよりも、つい“活気のある場所”に目が行ってしまうんです。気づくと、その勢いに引き寄せられて、そこで買ってしまうことが多いですね。
スタッフ全員で“声のリズム”をそろえる
声かけの力を最大化するには、スタッフ全員の“声のリズム”をそろえること。
バラバラに声を出すより、テンポよく連動したほうが、お客様に安心感が伝わります。
たとえば――
- Aスタッフ:「いらっしゃいませ!」
- Bスタッフ(続けて):「冷たいドリンクいかがですか!」
- Cスタッフ(締めに):「すぐ飲めますよ!」
このように“流れる声かけ”を意識すると、店全体に一体感が生まれます。
お客様の耳に残るのは「明るい店」「元気な店」という印象。
それがそのまま購買意欲につながります。
声をそろえることは、販売促進であると同時に、
スタッフ間のコミュニケーションにもなります。
“声の連携”は、チームの団結を高める最高のトレーニングなのです。

たまにリズムにあわせて業務連絡が飛んできたりするので笑えます。「フランク補充まだですか〜?」「こっちも必死やねん!」
声が届く売場は、人の心も動かします。
次は、当日の“予期せぬトラブル”をどう乗り切るか――
現場で実際に起きたケースから、チームでの対応力を考えてみましょう。
トラブル対応:混乱時こそ“冷静さ”が売上を守る
トラブルは“起きる前提”で準備する
夏祭りや花火大会などのピーク営業では、トラブルは必ず起きます。
POSエラー、氷切れ、想定外の来客、スタッフの体調不良……。
むしろ、トラブルがない方が珍しいほどです。
だからこそ、「起きたらどうするか」ではなく「起きる前提で準備する」ことが大切です。
事前に“想定リスト”を共有しておくだけで、現場の焦りはぐっと減ります。
- 氷切れ時のバックヤード補充動線
- レジトラブル時の臨時会計ルール
- 発注漏れや返品時の連絡フロー
「万が一」が「想定内」に変わるだけで、スタッフの動きに迷いがなくなります。
トラブルの真の敵は“焦り”です。
“焦り”は伝染する、“落ち着き”も伝染する
現場で一人が焦ると、その空気は一瞬で全員に伝わります。
反対に、店長が落ち着いていれば、スタッフも自然と冷静さを取り戻します。
これは、どんなマニュアルよりも効果的な“空気のコントロール”です。
以前、氷の在庫が一時的に切れたことがありました。
店内がざわつく中、私は一度深呼吸してこう言いました。
「今ある氷で10分もたせよう。バックから追加が来る。それまで丁寧に声をかけよう。」
その一言で、スタッフの動きがスッと落ち着き、
混乱は最小限に抑えられました。

店長が慌てると、店全体が慌てる。
店長が落ち着けば、店全体が落ち着く。
現場は、リーダーの“呼吸”で変わります。
トラブル後のフォローで信頼が生まれる
トラブル対応は、終わった後が本当の勝負です。
「大丈夫だった?」「ありがとう、助かったよ。」
この一言が、スタッフのモチベーションを守ります。
また、お客様へのフォローも同じ。
「ご迷惑をおかけしました」だけでなく、
「次回はこのように改善します」と伝えることで、誠意が伝わります。
トラブル対応は、失点ではなく“信頼を得るチャンス”。
対応の姿勢ひとつで、「また来たい店」に変わるのです。
どれだけ忙しくても、焦らず・慌てず・丁寧に。
その姿勢こそが、混乱をチャンスに変える最強のマニュアルです。
トラブルを乗り越えた現場には、学びと絆が生まれます。
では最後に、夏祭り営業を終えて感じた“現場の本質”をまとめましょう。
廃棄を減らせと言われ続ける現場。でも、売上を作るには一定の“攻め”も必要です。
廃棄率を単なるコストとして見るのではなく、売上を伸ばすための投資という視点から整理した共通入口はこちら。
▶ 廃棄率2〜3%が適正な理由

まとめ|“祭りの日”に学ぶ現場オペレーションの本質
忙しさの中にこそ、“原点”がある
お祭りや花火大会の日は、売上も活気もピークを迎えます。
けれど、その裏では、スタッフの汗と判断が積み重なっています。
混乱もトラブルもありますが、そこにこそ現場の原点があると感じます。
「どうすればお客様が喜ぶか」
「どうすればスタッフが動きやすいか」
――その問いを何度も繰り返すことこそ、現場力=経営力を育てる道です。
現場を整えるのは“仕組み”より“人”
オペレーションをどれだけ完璧に組んでも、
最後にお客様の前に立つのは“人”です。
だからこそ、準備や動線も大切ですが、現場を動かすのは「人の気持ち」だと思います。
スタッフが楽しそうに働いている店は、お客様にも伝わります。
逆に、焦りや疲れが出ている店は、それも伝わってしまう。
結局のところ、現場とは“空気をつくる仕事”なんですよね。

現場を支えるのはシステムではなく、人の笑顔。
その笑顔が、お客様を呼び、また次の笑顔を生むんです。
“準備7割、当日3割”が繁忙期成功の鍵
夏祭り営業を何度も経験してきて痛感するのは、
「当日どう動くか」より「前日までにどれだけ整えられるか」ということ。
発注・配置・担当割・声かけスクリプト――
これらを前もって明確にしておくことで、
当日の混乱は8割減ります。
焦らない現場は、笑顔が生まれる現場です。
お祭り営業は“現場力”のリトマス試験紙
忙しい1日を乗り越えたとき、スタッフの顔には疲れではなく達成感があります。
「大変だったけど、楽しかったね。」
その一言が聞けた瞬間、「このチームで良かった」と心から思います。
お祭り営業は特別な日ですが、
実は普段のオペレーションを“凝縮して見せてくれる鏡”でもあります。
準備・チームワーク・声かけ・冷静な判断―― この4つの積み重ねが、毎日の営業にもそのまま活きてくるのです。

祭りの日に強い店は、どんな日にも強い。
現場は1日で育たない。でも、1日で変われるんです。
今日の一言まとめ
- やることを減らすことで、動きは速くなる。
- “冷やす”と“見せる”が売上の7割を決める。
- 声かけは「呼びかけ」ではなく「気づかせ」。
- 焦りは伝染する、落ち着きも伝染する。
- 準備は信頼を生む時間。

とても大変な日ではありますが、楽しみながら業務にあたることのできる環境こそ最強です。