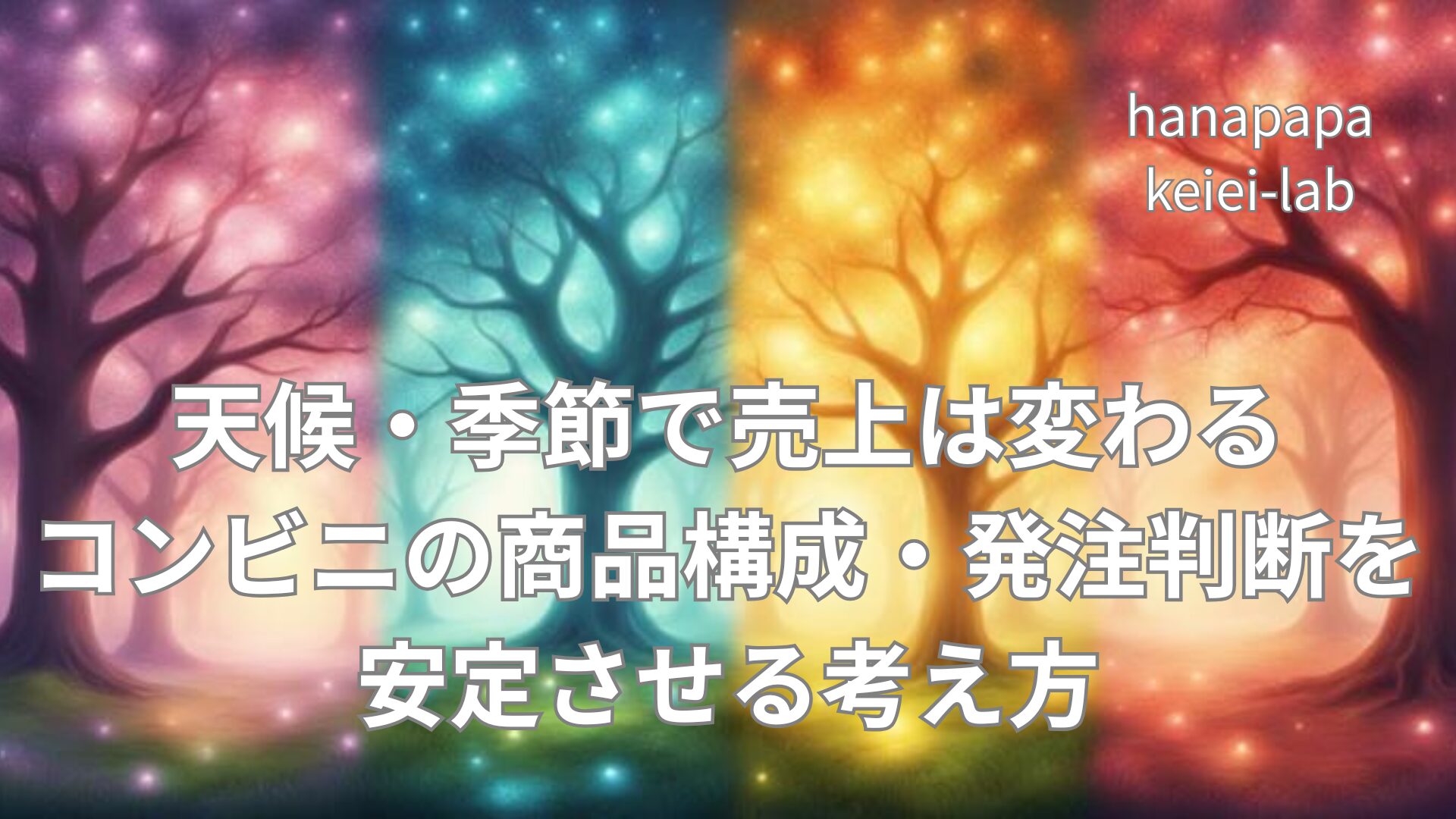年越しそば・餅が売れる理由|習慣需要を活かす売場戦略
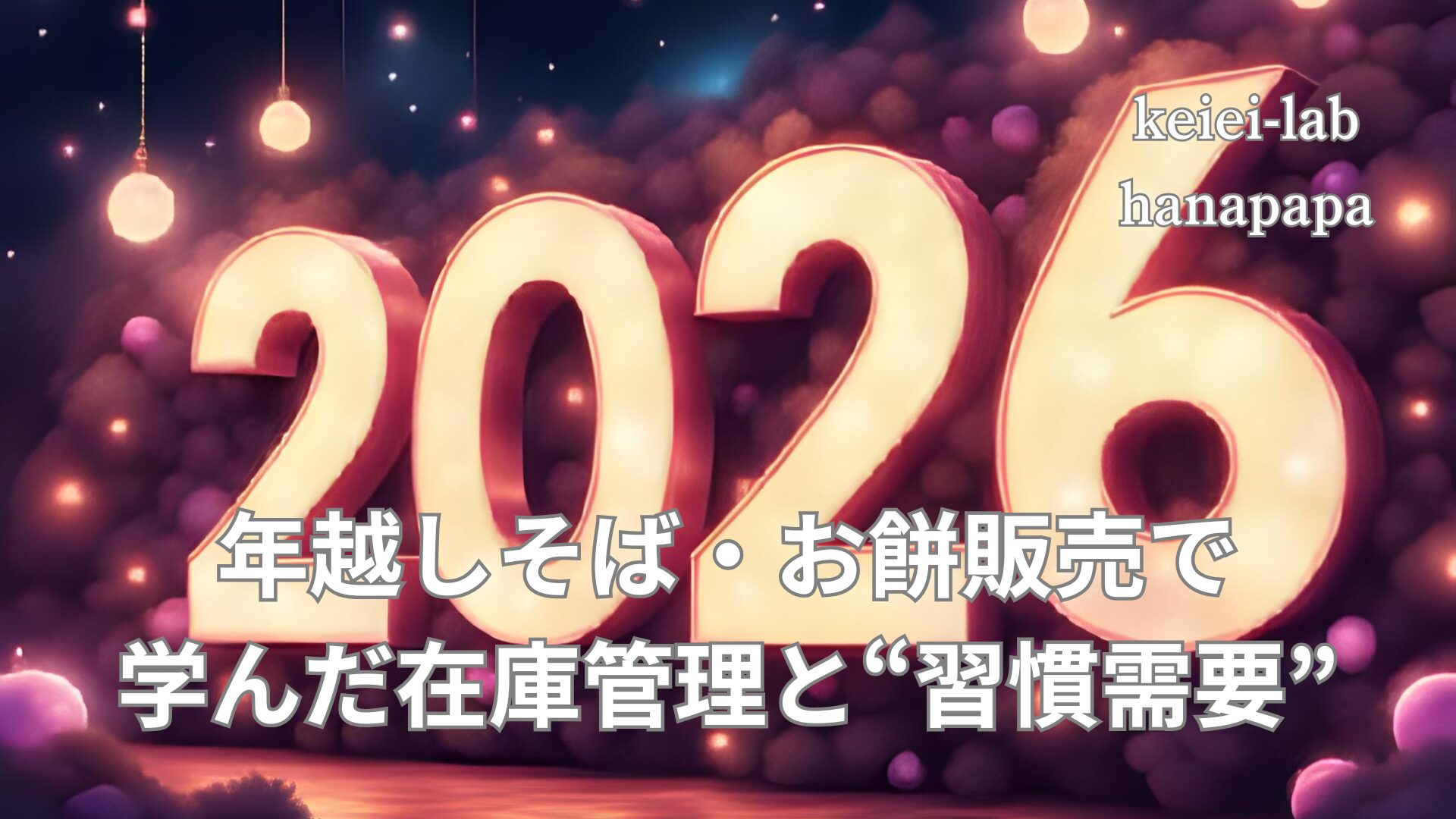
12月はコンビニにとって年間最大の商戦期。 特に「年越しそば」と「お餅」は、年末商材の中でも欠品が許されない最重要商品です。
私自身、コンビニ現場で年越し商戦を何度も経験してきましたが、 この2つの商品から学んだことは、ただのイベント対応ではなく、 “習慣によって支えられた継続需要”を見抜くことの大切さでした。
年末だけでなく、実は1月に入ってからも売れ続けるこれらの商品は、 「年末だから売れる」ではなく、「毎年・毎月の習慣」によって買い続けられる“底堅い商品”なのです。

12月は一年で一番売上が伸びる月。 だからこそ“商品不足”は致命的なんです。 年越しそばもお餅も、売場づくりでは絶対に欠品させないことが本当に重要です。
この記事では、現場で身にしみた 年越し商材の在庫管理術・売場づくりのコツ・「習慣需要」を味方にする方法について、 具体的なエピソードを交えながらお伝えします。
年越しそばの由来と意味|“意味を知ると売場が強くなる”理由
年越しそばは、日本の年末文化に深く根付く「縁起食」です。 お客様が毎年必ず買う理由は、「習慣だから」ではなく、 “そばに込められた意味と願い”があるからです。
売場づくりやPOPにこの意味を少し添えるだけで、 購買率は驚くほど変わります。 まずは、その代表的な由来を整理しておきましょう。
① 長寿・縁結びの願い
そばは細く・長く伸びることから、 「寿命が伸びる」「家族の縁が長く続く」という意味が込められてきました。 昔から“1年の締めくくりにそばを食べる”という文化が続いているのは、 この「長く続く」という縁起の良さがあるためです。
② 厄落としの意味
そばは切れやすい食べ物。 その特性から、「今年1年の災いを断ち切り、翌年に持ち越さない」 という厄落としの意味もあります。
特に年末のそばは、 「今年の区切りをつけて翌年を迎える」 という儀式的な役割を果たします。
③ 金運祈願(縁起物としてのそば)
金銀細工職人が散らばった金粉をそばで集めていたことから、 そばには「金を集める縁起物」という説もあります。
金運アップを願う文化と共に、 年越しそばの“縁起食としての価値”が広まっていきました。
④ 江戸時代からの広がり(庶民文化として定着)
江戸時代の町人文化の中で、 「大晦日にはそばを食べる」という習慣が全国に広まったと言われています。 明治以降も全国区で定着し、現代まで続く年末の風物詩になりました。

そばの“意味”を売場で伝えるだけで、 お客様は“あ、やっぱり買って帰ろう”となるんです。 理由を知ってもらえると購買率が一気に上がります。
▶ 売場づくりにどう活かす?
在庫管理と売場づくりの工夫
年越しそばは年末の最重要商品であり、 「厚めに在庫を持つ」ことが成功の絶対条件です。 ただし、そば自体の在庫だけでは不十分で、 地域性や食文化を考慮した売場演出・関連商品の厚みまで含めて “トータル戦略”で準備することが重要です。
地域ごとに“売れ方が違う”ことを理解する
そばそのものは全国的に食べられていますが、 地域ごとに「そばの食べ方」や「合わせる食材」が大きく異なるため、 売場づくりは必ず“地域性”を前提に考える必要があります。
このように、そば自体は同じでも、 「添える具材」や「出汁の文化」が売上を大きく左右します。

関東にいた頃は“海老天そば”が鉄板でしたが、 地域が変わると“あれ、全然動きが違う…”となるんですよね。 地元の食文化を売場に反映するのはめちゃくちゃ重要です。
麺より“トッピング”の厚みが売り逃しを防ぐ
売場で見落とされやすいのが、 そば本体より“トッピングの厚み”が売上を決めるという点です。
実際の現場では、そばが十分あっても 「天ぷらが足りなくて買わない」 「かまぼこが欠品でお客様が帰る」 というケースが非常に多いです。
このラインが厚くなるだけで、 そばの購買率は一気に向上します。
売場は「年越し感」を出すだけで売れる
年越しそばは“行事食”であるため、 売場に「年越し感」「季節の締めくくり感」を演出することで、 買う理由を自然に後押しできます。
- 赤・金系POPで年末の雰囲気を演出
- そばの前に「大晦日のお供に」「今年もお疲れさまでした」の一言POP
- 天ぷらやかまぼこをそばの真正面に配置

年末って、お客様のほうから“そば買わなきゃ”って気持ちになっているんですよね。 売場で“最後のひと押し”をしてあげるだけで数字が大きく伸びます。
在庫は“余らせる勇気”より“足りない恐怖”が勝る
年越しそばは日持ちがする商品が多いため、 欠品のほうが圧倒的にリスクが高い商品です。
特に12月30日〜31日は動きが読みにくく、 少し読みが外れただけで売り逃しが大量に発生します。
迷ったら、そばと天ぷらだけは「厚め一択」が正解です。
習慣需要のサイクルを理解する
年越しそばやお餅の販売で最も驚かされるのは、 「年末だけで終わらず、1月に入っても売れ続ける」ということです。 これは、年越し商材が単なるイベント商品ではなく、 “習慣によって支えられた定期需要”だからです。
お客様は年末に「家でそばを食べる」「正月は餅を買う」という行動を、 家族の決まりごととして自然に繰り返しています。 一度購入した方が再び来店するという“習慣の連鎖”が起きるため、 年明けも売上が落ちにくいのが特徴です。
① 『年越しそば=年末の儀式』が購買を後押しする
お客様にとって年越しそばは、 「買わなきゃ気持ち悪い」というレベルの儀式化された行動です。
この“儀式性(ルーティン)”が強い商品ほど、 購入が習慣化しているため、売り逃がしが発生しにくくなります。 つまり、売場づくりさえ整っていれば確実に動く商品といえます。

お客様は“年末に買って終わり”じゃないんですよね。 大晦日に食べたら、正月にももう一度買いに来る。 これが習慣需要の一番の強みです。
② 年末だけでなく“1月も売れ続ける”理由がある
多くの店長が見落としがちですが、 年越しそばや餅は1月の売上を支える底堅い商品でもあります。
理由はシンプルで、
- 自宅で食べる回数が増える
- 親族の集まりで食材が必要になる
- 正月に買い足しが発生しやすい
- そば・餅は“日持ち”するためリピートしやすい
この習慣性があるため、 12月末だけでなく1月の発注量も強めに設定しておくことが大切です。
③ 一度買ったお客様は“翌年も来る”という圧倒的強さ
習慣需要の最大のメリットは、 「一度買ったお客様は、翌年も同じ時期に買いに来る」という点です。
これは、単なる“イベント買い”では起こりません。 年越しそば・餅は、家庭内での“年末年始の決まりごと”になっているため、 毎年同じようにリピートされます。
売場がしっかり整っている店舗は、このリピートを自然に獲得できます。 逆に売場が弱い店舗は、習慣需要の恩恵を逃してしまいがちです。

年末年始は本当に“リピーターが積み上がる季節”。 毎年買ってくれるようになると、店全体の底力が上がります。
④ 習慣需要は“売上の安定化”に直結する
習慣需要の商品は、 天候・イベント・曜日に左右されにくく、 売上が安定するメリットがあります。
つまり、年越しそば・餅を単なる季節商品として終わらせず、 “年間の売上を支える商品”として捉えることが必要です。
年越しそば・お餅は、 ただ年末に売るだけではなく、 “翌年の来店につながる商品”でもあります。 このサイクルを理解するだけで、 発注の組み立てや売場づくりの視点が大きく変わります。
学び:年越し商戦は「習慣」を味方につける
年越しそばやお餅の販売から得られる最大の学びは、 これは「イベント商品」ではなく、“習慣によって支えられた継続需要”だということです。
「どうせ12月だけ売れる商品だろう」と限定的に考えてしまうと、 在庫を薄くして機会損失を起こし、せっかくのチャンスを逃す結果になります。 逆に、“習慣が売上を支える商品である”と理解して発注・売場を設計できれば、 翌年以降も安定して売上を積み上げることができます。
① 年越し商戦を“12月だけの勝負”と考えると失敗する
年末だけにフォーカスして発注すると、 どうしても「必要最低限」になりがちで、 12月30〜31日の最重要タイミングで欠品を起こしやすくなります。
また、売上の山場は年末だけではありません。 翌年1月に入っても、そば・餅・つゆ・薬味など “正月の備え買い”が続くため、1月まで売れるロング商材です。
② 習慣需要を理解すると“来年の売上”まで見えてくる
習慣による購買行動は、 “毎年同じタイミングで同じ商品が売れる”という再現性の高さがあります。 だからこそ、今年しっかり売れた商品は来年も同じように売れる可能性が非常に高いのです。
単なるイベント商品と違い、 年越しそばや餅は「文化 × 家庭のルール × 習慣」で買われる商品。 つまり、一度定着すると顧客の来店行動まで安定するという強みに繋がります。

年越し商戦は“その年だけの勝負”じゃないんですよね。 売場が良い店は翌年もお客様が戻ってきてくれる。 習慣需要は“翌年を作る売上”でもあるんです。
③ “習慣”を売場に組み込むことでファンが増える
年越し商戦で学べるのは、 習慣を売場にどう落とし込むかという視点です。
例えば——
- 毎年12月中旬にそばコーナーを前倒しで作る
- つゆ・天ぷら・かまぼこをセット陳列して“安心感”を出す
- 「ここで買うのが毎年の流れ」と思わせる売場導線
こうした“習慣設計”は、 お客様に「今年もここで買おう」と思わせる強力な仕掛けになります。
④ 習慣需要は“長期的な売上の礎”になる
習慣需要を味方につけると、 売上は一時的ではなく年単位で安定化していきます。
年末に買ってくれたお客様が、 次の年末にも、さらにその次も戻ってきてくれる。 これはコンビニ経営において、最も価値のある資産=“顧客の信頼と繰り返し来店”です。
だからこそ、年越しそば・餅のような “習慣で買われる商品”は、 毎年の積み重ねが強い成果につながります。
年越し商戦は、単に“年末のピークを取る”だけではなく、 翌年の売上基盤をつくる最重要シーズンです。 今年しっかり積み重ねた売場設計・在庫運用は、 来年以降の安定した売上に必ずつながります。
まとめ|習慣需要 × 売場戦略が年越し商戦を強化する
年越しそば・お餅は、ただの年末向け商品ではありません。 この記事で見てきたように、「文化」「家庭のルール」「習慣」によって 毎年安定して売れ続ける、非常に強い“習慣需要商品”です。
だからこそ、 ・厚めの在庫 ・地域性を意識した売場 ・トッピングの充実 ・年越し感のある演出 こうした“基本を丁寧に整える”だけで売上が驚くほど伸びていきます。
そしてこの売上は、年末だけで終わらず、 翌年の1月にも続き、さらに来年以降のリピート客を生む資産になります。
年越し商戦で押さえるべきポイント
現場の小さな工夫が、翌年の売上まで作る
冬商戦は、コンビニ運営の中でも “現場の工夫が最も数字に反映される期間”です。 補充のタイミング、売場の作り方、ちょっとしたPOP、関連陳列—— どれも積み重なると、年末だけでなく翌年の売上まで影響します。

年越し商戦は、売った分だけ来年も返ってくる季節。 店としての“積み上げ力”が一番試されるタイミングです。
明日からできる実践チェックリスト
年越し商戦は、準備した分だけ必ず売上に返ってくる季節です。 習慣需要を味方につけ、今年の年末をしっかり取りにいきましょう。
廃棄を減らせと言われ続ける現場。でも、売上を作るには一定の“攻め”も必要です。
廃棄率を単なるコストとして見るのではなく、売上を伸ばすための投資という視点から整理した共通入口はこちら。
▶ 廃棄率2〜3%が適正な理由