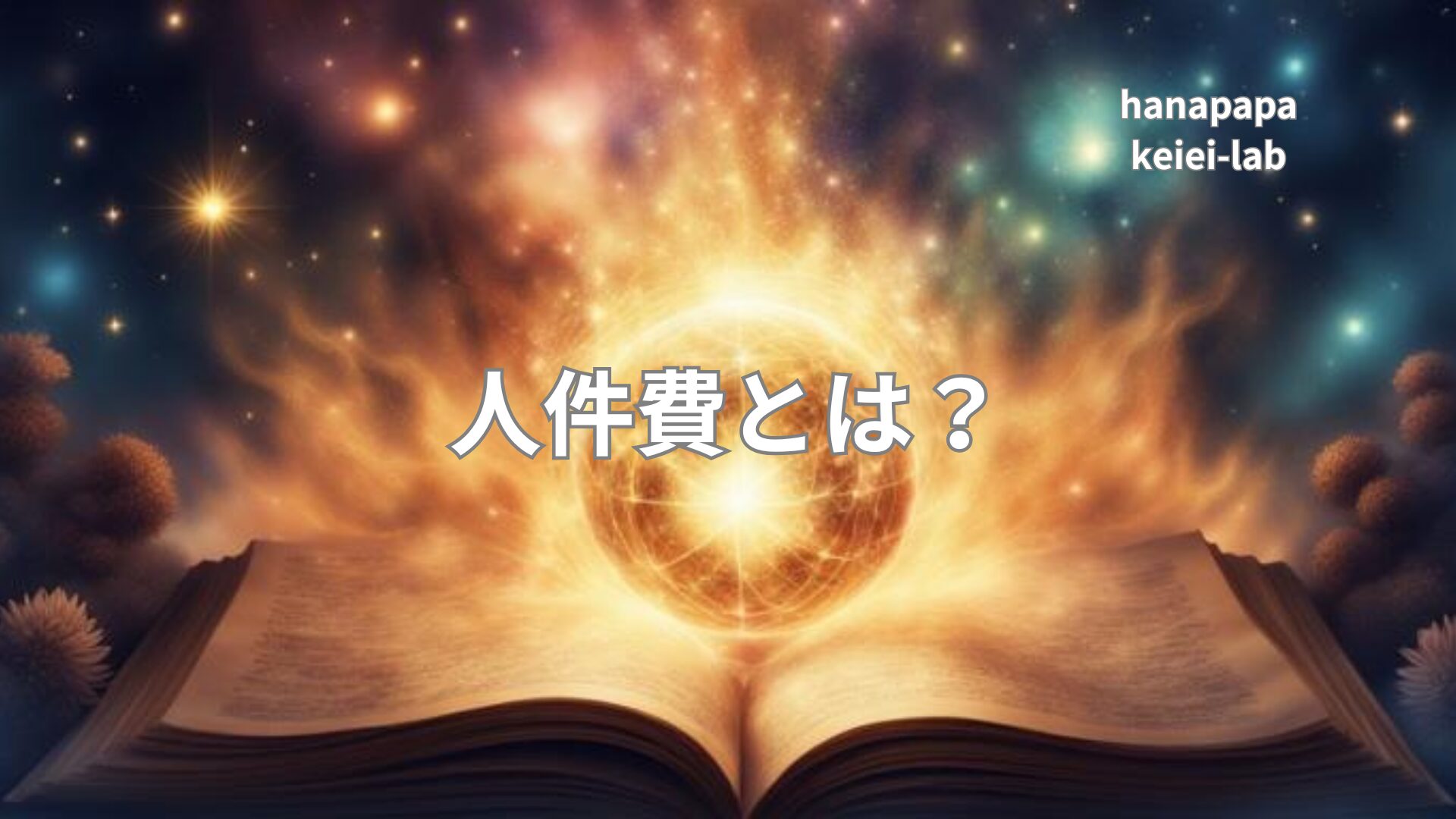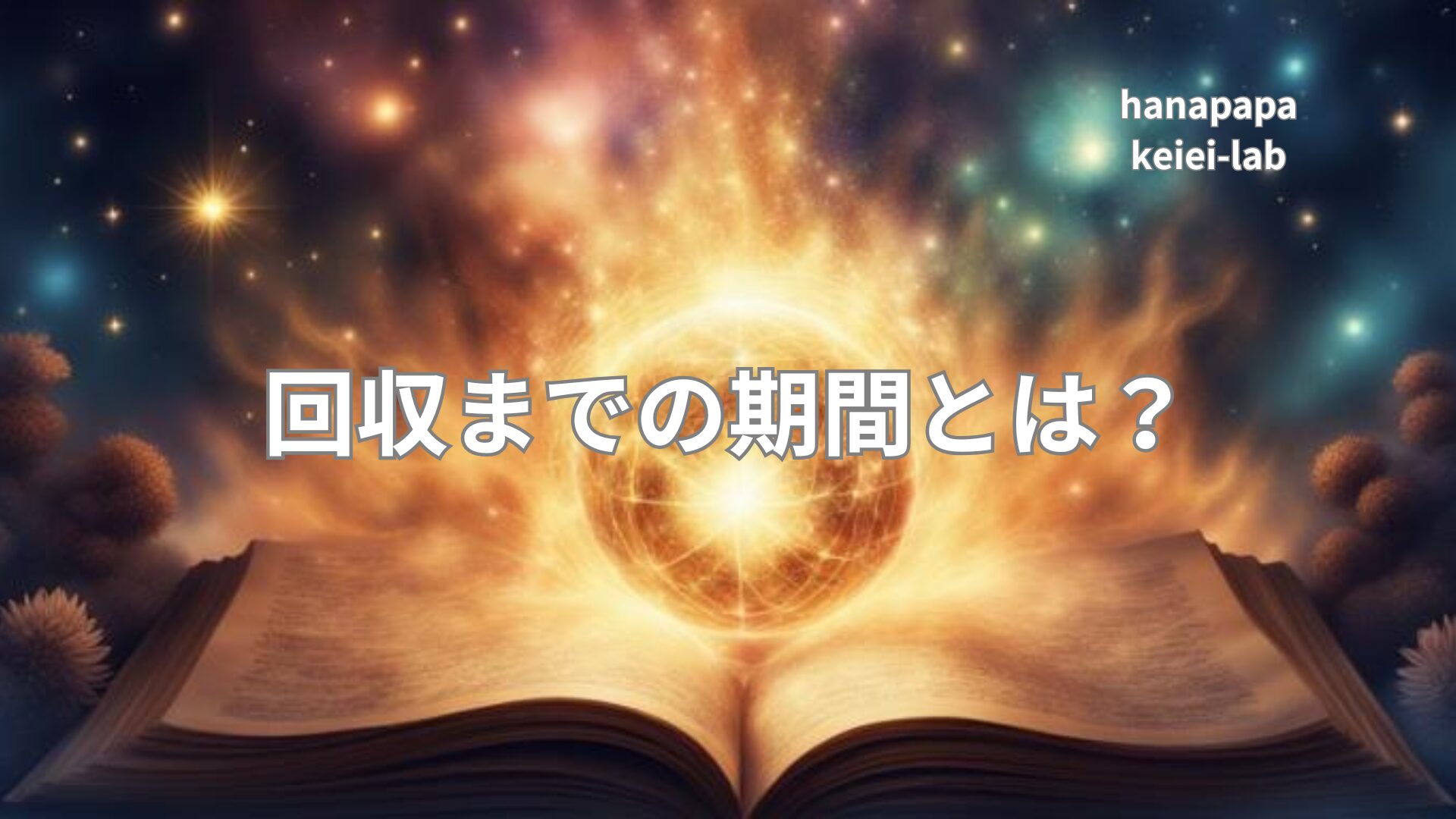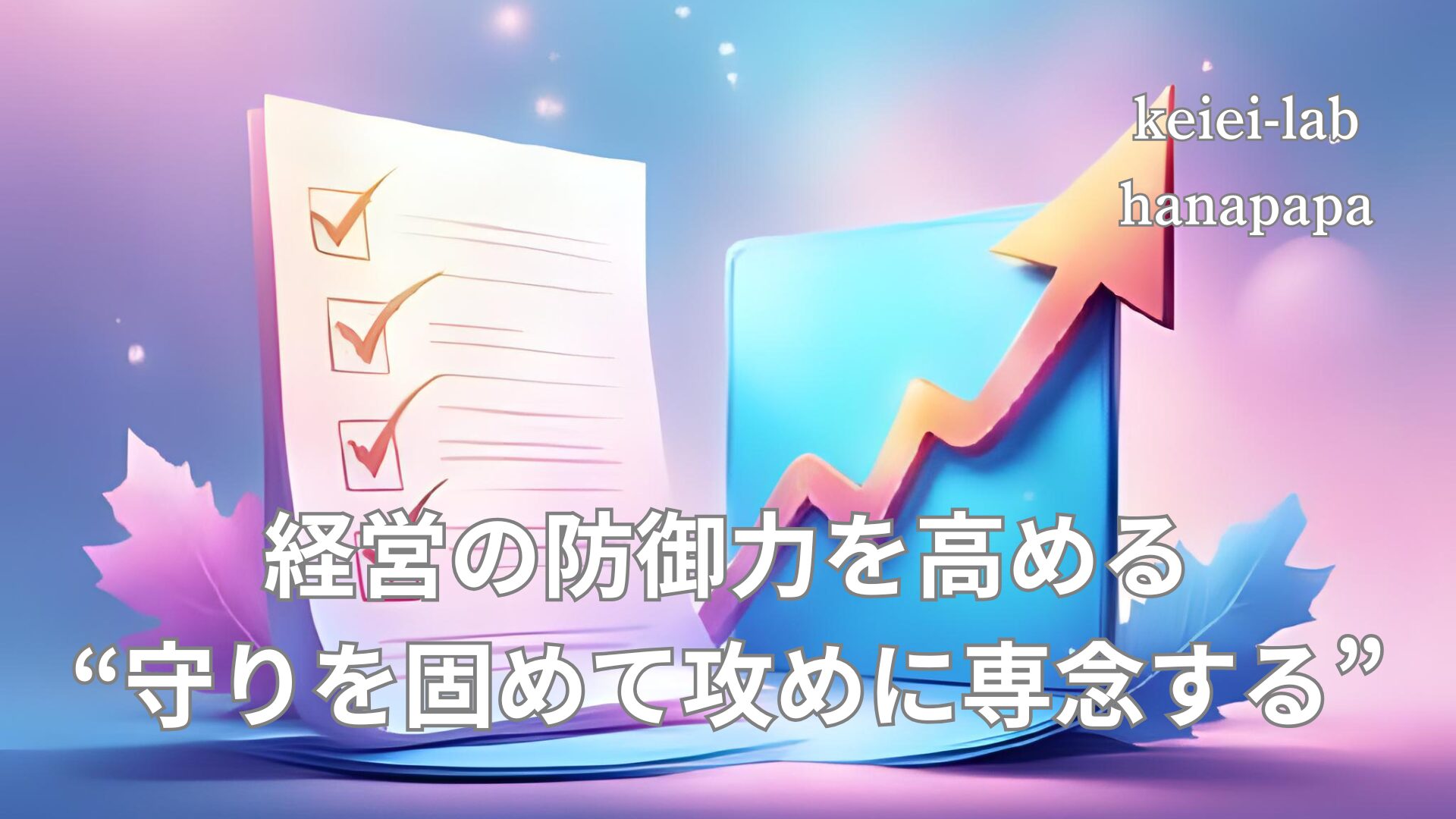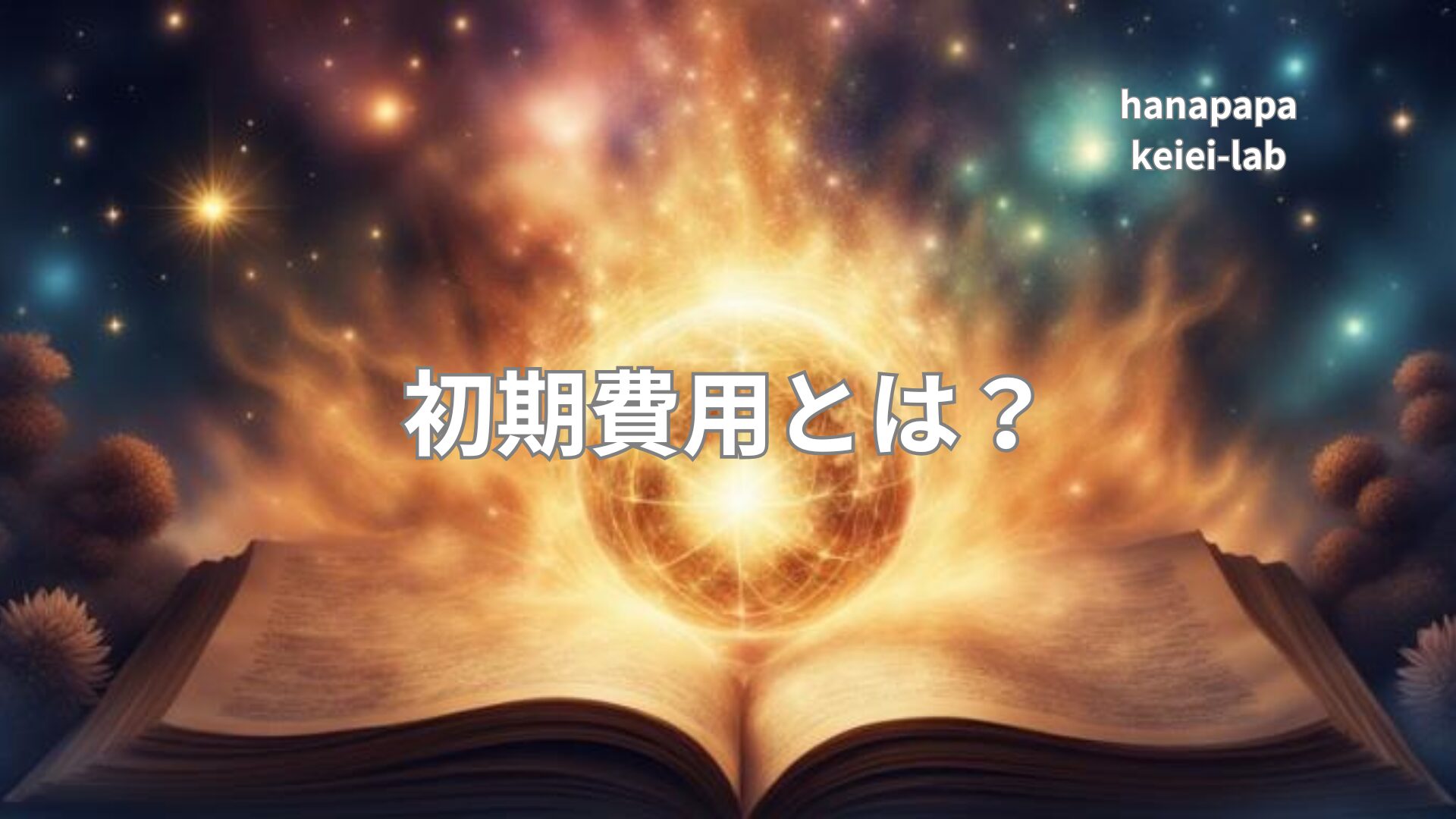【コンビニ経営】生き抜く鍵は「接客力」|人としての価値が選ばれる時代へ

ネット通販が当たり前になった今、
どんな商品でもスマホひとつで手に入る時代になりました。
そんな中で、コンビニが生き抜いていくために本当に必要なのは――
「人としての価値」を提供する力、つまり“接客力”です。
Amazonや楽天、Uber Eatsのように、効率やスピードで勝負することはできません。
しかし、コンビニにはネットでは決して再現できない価値があります。
それは、お客様に安心や温かさを届ける“人の力”です。
「お疲れさまです」「寒いですね」といった何気ない一言、
レジでのちょっとした会話や気づかい――。
それが、また来たいと思ってもらえる「体験」になり、
お客様の心に残る“価値”を生み出します。
便利さだけでは選ばれない時代に、
人と人とのつながりを大切にできるコンビニこそが、生き残る。
私はそう考えています。
コンビニに求められる役割
コンビニの本質的な役割は、「特化型の商品提供」ではなく、
“広く・浅く・必要なものをいつでも提供できること” にあります。
食品をまとめ買いするならスーパー、
日用品を探すならホームセンター、
タバコならタバコ専門店、パンならパン屋――。
それぞれの専門店には品揃えでは到底かないません。
しかしコンビニには、「あの時、あれが欲しかった」を満たす力があります。
たとえば、仕事帰りにのどが渇いた時の飲み物、
朝急いでいる時の軽食、雨が降った時の傘。
私たちの役割は、
その日・その瞬間に“必要なものが最低限揃っている”こと。
それこそが、どんな時代になってもコンビニが求められる理由だと思います。

「この店がここにあってよかった」
「この時間でも空いてて助かった」
「ありがとう」――そんな一言が、本当に励みになりますね。やっててよかったと思う瞬間です。
もちろん、その「最低限揃っている」状態を保つのは簡単ではありません。
限られた売場スペースの中で、どの商品を置き、どれを減らすか――。
そこには、品揃えの幅と限界という現場ならではの判断が常に存在します。
品揃えの幅と限界
スーパーの売場を見れば、同じしょうゆひとつでも種類は豊富で、
減塩タイプ、価格帯、容量違いなど、選択肢は実に多様です。
しかし、コンビニの限られた売場ではそれを再現することはできません。
1〜2種類に絞らざるを得ない――これが現実です。
ただし、ここにこそコンビニの「強み」もあります。
重要なのは、“種類を増やすこと”ではなく、“必要な1本を欠かさないこと”。
お客様がスーパーで買い忘れた調味料を、
「とりあえずコンビニで買える」――この安心感が価値になります。
つまり、私たちは“量”で勝負するのではなく、
お客様の生活リズムに寄り添う「最小限の便利さ」を提供しているのです。
この限られたスペースの中に、
どれだけ「生活の困りごとを解決できる商品」を置けるかが、
コンビニの存在価値を決めるポイントだと感じます。

種類を増やすことは、もちろんお客様のためになります。
でも、売り場全体とのバランスも大事ですよね。
ただ要望に応えるだけでは、本当に多くの人の役には立てないんです。
そして、その“必要な1本”を切らさず提供するために欠かせないのが、
発注精度とAIの活用です。
どの商品を、どれだけ、どのタイミングで入れるのか――。
この判断力が、現場の経験とデータの両方に支えられています。
発注精度とAIの活用
「欲しいときに、欲しいものがある」
――その当たり前を支えているのが、発注の精度です。
コンビニ運営では、品切れを防ぎつつ廃棄を抑えるという
相反する課題と常に向き合っています。
人件費が高騰する中、限られた人員で最適な発注を行うには、
効率化と精度の両立が欠かせません。
近年ではAIの発達により、
天候や曜日、販売履歴などのデータをもとにした精度の高い発注が可能になりました。
AIは非常に優秀なサポートツールです。
しかし――それでも完全に任せきることはできません。
たとえば、突然の冷え込みで中華まんが売れる、
地域の学校行事でおにぎりが一気に動く、
そんな“現場でしか感じ取れない変化”は、まだAIにはわかりません。
だからこそ大切なのは、
現場の肌感覚とAIを組み合わせて、最善の判断を下す力。
データが示す数値をベースに、
「このお客様層なら今日は少し多めに」「この天気なら温かい飲料を増やそう」と
微調整できることが、現場リーダーの腕の見せどころです。
AIが進化しても、最終的に“人の判断”が価値を決める。
その視点を忘れないことが、これからの店舗運営に求められる姿勢だと思います。

発注もAIの進歩で、ずいぶん時間短縮ができるようになりました。
でも、それだけに頼りきるのは危険です。
浮いた時間をどう活かすか――何をなすべきかを考えることこそ大事。
発注の精度も、接客の質も、結局は“人の考える力”で決まると思います。
そして、この“人の判断”がより活きるのが、
24時間営業という現場の強みです。
お客様の生活時間に合わせて常に商品を提供できること――
これこそが、ネット通販にはないコンビニならではの価値といえます。
24時間営業という強み
コンビニの最大の特徴――それは、24時間営業であることです。
この「いつでも開いている」という安心感は、
単なる“便利”を超えて、人々の生活を支える信頼の象徴でもあります。
夜間に利用するお客様の多くは、
「スーパーが閉まっているから」「早く済ませたいから」といった理由で来店されます。
そんなとき、明るい店内と「いらっしゃいませ」の声があるだけで、
少しホッとする瞬間が生まれるものです。
夜勤明けのコーヒー、深夜の軽食、急な発熱時の飲料や薬。
昼間とは違う“切実なニーズ”に応えられるのが、24時間営業の価値です。
そこには、いつでも誰かのために開いている店という
社会的な使命感が息づいています。
もちろん、深夜帯の人件費や光熱費の負担は大きな課題です。
しかし、それでも24時間営業を維持してきた理由は、
お客様の「ここなら安心して立ち寄れる」という信頼を守るため。
それが、他の業態にはないコンビニのブランド価値なのです。

深夜や早朝に働いている方にとって、
「おはようございます」「お疲れさまです」「こんばんは」――
そんな一言が心に響くんですよね。
違う時間帯で頑張っていることに、ちゃんと共感できる接客を大切にしていきたいですね。
こうして築かれてきた“信頼”をさらに強めるために、
これからの時代に欠かせないのが接客力の深化です。
ネット通販との違いを際立たせるためにも、
「人の温かみ」を感じてもらえる接客こそが、コンビニの未来を左右します。
ネット通販との違いと接客力の必要性
利便性だけを求めるなら、Amazonや楽天といったネット通販を利用する人は今後ますます増えていくでしょう。 クリックひとつで翌日には商品が届く便利さは、店舗販売の強みを奪いつつあります。 これからの時代、「ただ便利だから来てもらえる」という前提は崩れていくと思います。
そんな中でコンビニという事業が生き残るためには、人にしか出せない価値を打ち出していく必要があります。 それが接客力です。 単に商品を売るのではなく、お客様にとって「安心感」「気遣い」「ちょっとした会話」が買い物体験の一部となるような場を提供すること。 これがネット通販にはできない価値だと考えます。
例えば、「あの人がいるから今日はあの店に行こう」という動機付け。 これは価格や品揃えだけでは生まれません。 従業員一人ひとりの表情、声掛け、対応の積み重ねによって初めて生まれるものです。 そして一度ファンになったお客様は、少々高くても、多少不便でも、その店を選び続けてくれます。
つまり、これからの時代にコンビニが残っていくためには、従業員一人ひとりが“店舗の顔”としてお客様をファン化していく力が欠かせないのです。 これは大手チェーンでも小規模チェーンでも同じであり、むしろ地域密着型の店舗ほど強みとして発揮できる部分だと思います。
利便性の時代から、「体験価値の時代」へ。 接客を通じた小さな体験の積み重ねこそが、コンビニの未来を支えると私は考えています。

ネット通販にはない“人の価値”を届けること。
それが、どんな時代になってもお客様に選ばれるコンビニのあり方だと、私は思います。
本記事で扱った内容は、コンビニ経営における一つの視点です。 全体の考え方や、現場改善をどう整理するかについては、 以下の記事でまとめています。