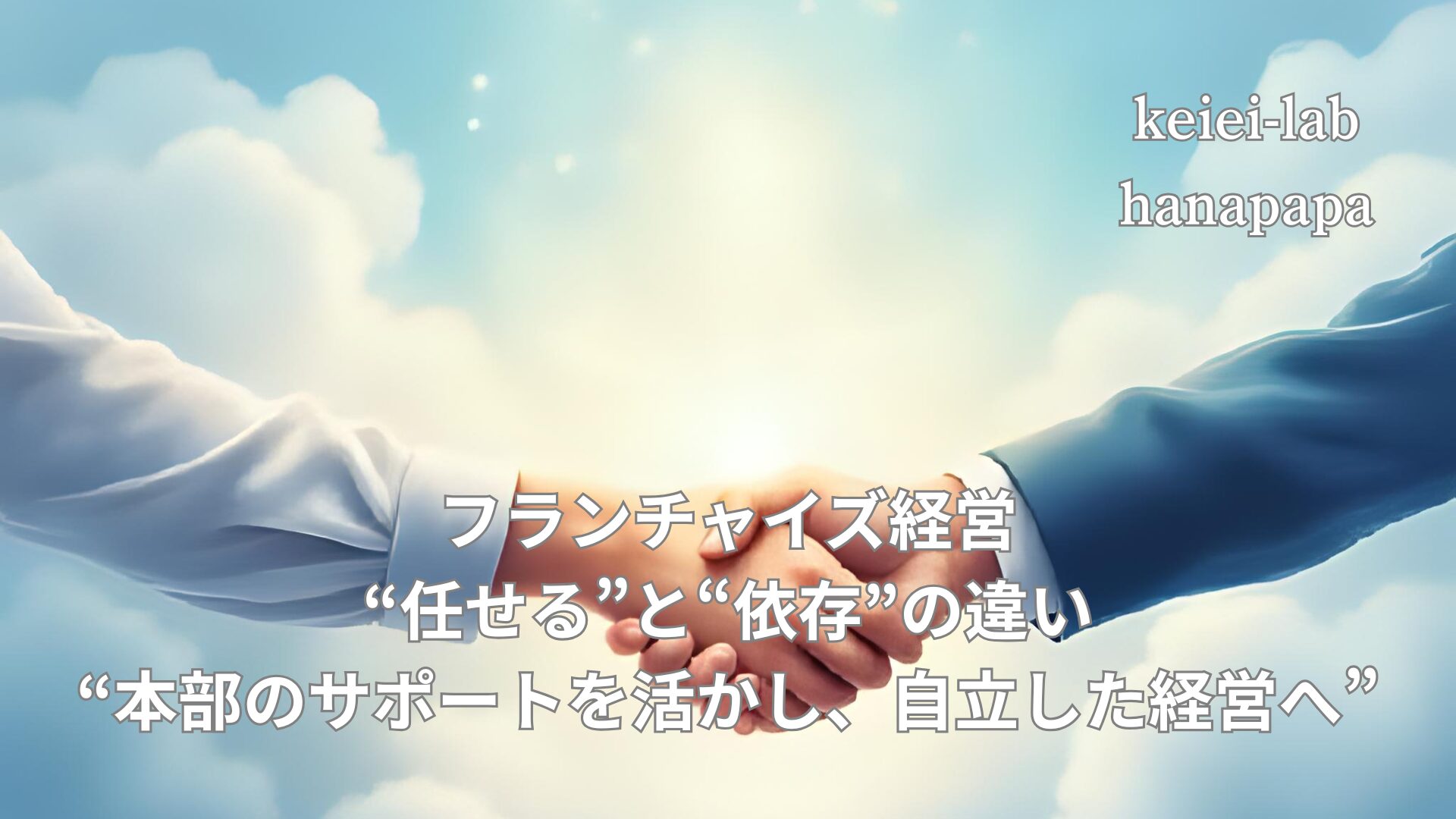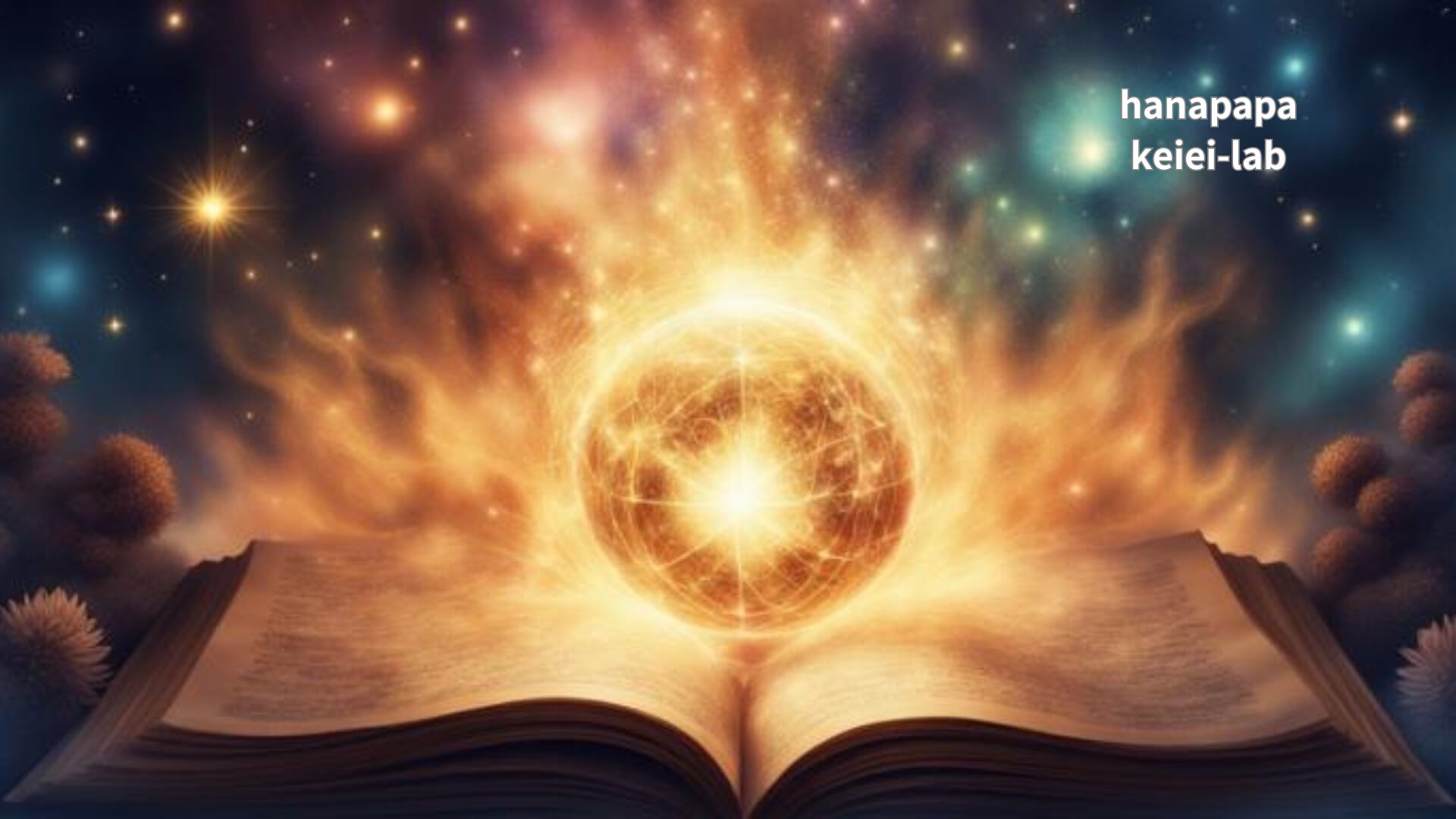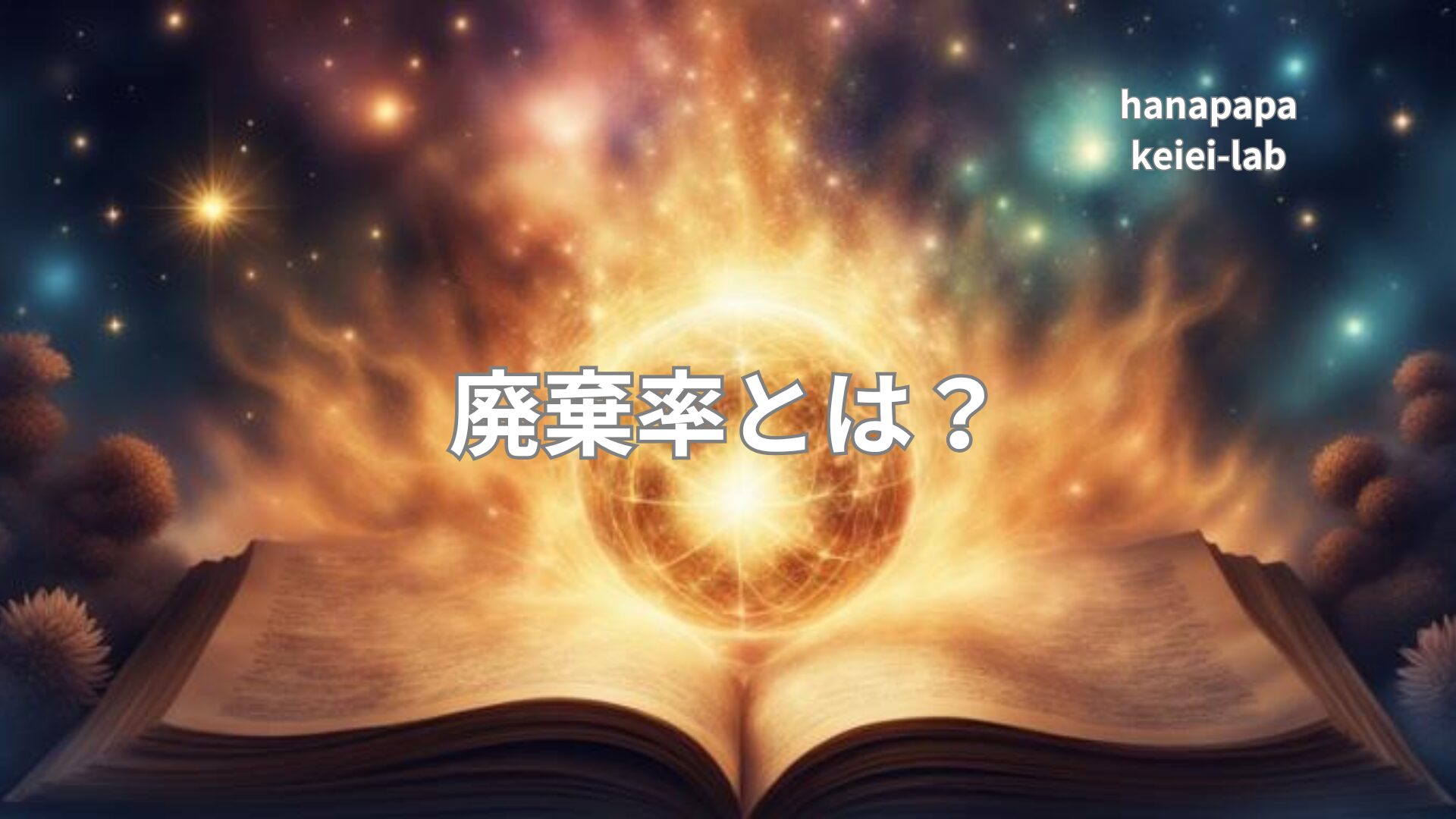本部とのうまい付き合い方|無理なく協力し要望を通す交渉術

「本部とどう付き合えばいいのか…」
そう悩んだ経験、ありませんか?
前回の記事では、「なぜ本部とオーナーの間で意見が食い違うのか?」というテーマで、
その原因が“収益構造の違い”にあることをお伝えしました。
とはいえ、構造を理解しても「じゃあ、どう付き合えばいいのか?」という壁にぶつかる方も多いはず。
本部からの要請をすべて断るわけにもいかず、
かといって何でも従っていては店舗の負担が増す。
この“バランスの取り方”こそ、現場経営者にとって永遠のテーマです。
今回は、前回の内容を踏まえながら、
本部と「うまく協力しつつ、こちらの要望も通す」ための現実的なスタンスを解説していきます。

対立でも服従でもなく、“交渉”がポイント。
本部を動かすのは、感情よりも“数字と姿勢”です。
本部との「ズレ」はなぜ起こるのか?前回記事のおさらい
そもそも“利益が発生するポイント”が違う
本部とオーナーは、同じ売上を見ていても「利益が生まれるタイミング」が異なります。
この違いこそが、日常のさまざまな場面で意見の食い違いを生む原因です。
たとえば——
- 本部:「新商品の発注数を増やして売上を伸ばしましょう!」
- オーナー:「在庫が多すぎて廃棄が心配です…」
どちらも“店舗の成果”を考えているのに、
見ている数字が違うため、優先する判断基準が噛み合いません。

“ズレ”の原因は、気持ちの問題ではなく“構造の違い”。
本部は仕入れで、オーナーは販売で利益が出る。
まずはそこを理解するだけで、話が通じやすくなります。
お互いの立場を知らないままだと、誤解が深まる
本部が「売上アップ」を重視するのは、組織上のKPI(評価基準)が“発注金額”や“納入量”に基づいているためです。
一方で、オーナー側は“廃棄率”や“粗利率”を重視して経営を見ています。
つまり、お互いの立場の前提が違うのです。
この前提を共有しないまま議論を重ねると、
「押し売りだ」「協力的じゃない」といった誤解が生まれてしまいます。
無理のない範囲で付き合い、時には“戦略的な無理”もする
「全部付き合う」でも「全部断る」でもない
本部からの提案やキャンペーンは、時に負担を感じることもあります。
しかし、すべてを拒否すると信頼関係が弱まり、すべてを受け入れると店舗が疲弊する。
この両極の間にある“中間のスタンス”が、実は最も効果的です。
たとえば——
- 売れ筋商品の重点展開にはしっかり協力
- 反対に、深夜帯や低回転商品の発注は抑える
このように、協力度合いにメリハリをつけることが、現場を守りつつ信頼も保つポイントです。

“全部やる”より、“やるところを選ぶ”。
本部と付き合ううえで大切なのは、力の入れどころと抜きどころです。
本部の評価軸を理解すれば“協力”が戦略になる
本部の担当者(SVや社員)は、
「発注数量」「販売伸長率」「キャンペーン参加率」などのKPI(評価基準)で成果を測られています。
つまり、本部にとっては「ある程度の協力姿勢」が、評価や信頼の尺度になるのです。
だからこそ、
- 重点商品だけは発注を増やす
- キャンペーン初日は協力して盛り上げる
- そのうえで「この時間帯は在庫を絞りたい」と相談する
といった“部分的協力”を見せることで、
「理解のあるオーナー」として評価されやすくなり、交渉が通りやすくなるのです。
「戦略的な無理」でチャンスを作る
時には、あえて“戦略的に協力する”場面を作るのも有効です。
たとえば——
- 新商品のキャンペーン初週だけ多めに発注して売場を強化
- 季節イベントで本部の提案を一度受け入れる
- その代わりに「次回は売場変更を相談したい」と要望をセットで伝える
このように「一度協力する代わりに、次の交渉材料を得る」姿勢が、
長期的な関係づくりにおいて“実利のある無理”になります。

“協力する=従う”ではありません。
未来の交渉を見据えた“戦略的な一手”と考えると、付き合い方が変わります。
本部社員の立場を理解しつつ、こちらの要望も通す
本部社員も「評価を受ける立場」で動いている
本部のSV(スーパーバイザー)や社員も、私たちと同じように“評価される立場”にあります。
彼らの成果は、主に以下のようなKPI(評価指標)で判断されています。
- キャンペーン達成率
- 発注数量・販売伸長率
- 加盟店の協力度(対応状況)
つまり、彼らも「自分の数字」を追いながら現場を回っているわけです。
この構造を理解していないと、「なぜそこまで推してくるのか?」が見えにくくなります。

本部の人も“現場を知らない押しつけ役”ではなく、“上から評価される立場”。
立場を知ることで、交渉の切り口が見えてきます。
「協力」と「要望」をセットにする
本部の立場を理解したうえで、“協力する姿勢”と“要望の提示”を同時に出すのが最も効果的です。
たとえば——
- 「今週のキャンペーンには協力します。その代わり、深夜帯は発注を抑えたいです」
- 「重点商品の展開を強化します。その分、発注数量は時間帯で調整させてください」
- 「イベントには前向きに参加します。ただし、翌週は棚替え提案を検討したいです」
このように、“Win-Winの形”を具体的に見せることで、本部も受け入れやすくなるのです。
単に「やります」「できません」ではなく、
「どこまで・どうすれば可能か」をセットで提示するのが交渉の基本です。
「あえて協力する案件」を選び、信頼を積み上げる
すべての案件に同じ熱量で対応する必要はありません。
しかし、「これは店にもプラスになる」「次の交渉材料にできる」と思う案件には、あえて協力するのも戦略です。
例:
- 季節イベントの初週だけ協力して売場強化
- 推奨商品を一時的に拡販してデータを共有
- 協力後、「この取り組みのおかげで売上が伸びました」と報告
このように、「やった成果を見せて信頼を積む」ことで、次の交渉が格段にやりやすくなります。

“交渉”は信頼の積み重ね。
一度“応えてくれた”という実績が、本部の態度を変えるんです。
まとめ:対立ではなく“交渉のスタンス”で向き合う
本部と店舗は「上下関係」ではなく「パートナー関係」
本部と店舗の関係は、決して「指示する側」と「従う側」ではありません。
お互いに利益を共有し、店舗運営を良くしていく“パートナー”です。
現場の実績や数字を伝えることも、交渉の一部。
本部からの提案に対して「なぜ難しいのか」「どうすればできるのか」を冷静に伝えることで、
感情的な対立ではなく、建設的な対話が生まれます。

“言われた通りに動く”から、“一緒に考える”へ。
現場の意見が伝わるのは、強さではなく“伝え方”です。
意見のズレは「交渉の材料」に変えられる
意見が食い違うのは自然なこと。
むしろ、そのズレを「交渉の材料」として活用することで、より良い方向へ導けます。
たとえば、
- 「このデータを見ると、〇〇時間帯の発注は減らす方が効率的です」
- 「キャンペーン強化には賛成ですが、陳列をこう変えるとより効果が出そうです」
このように、自店のデータをもとに提案を返すスタンスが、本部との信頼を深めます。
「ただ反対する」から「提案で返す」へ──この姿勢が、関係構築の分岐点です。
現場の意見を“通すタイミング”を見極める
交渉で大切なのは、何を言うかだけでなく“いつ言うか”です。
本部の担当者も繁忙期や新商品リリース前などは余裕がなく、提案を受け止めにくいことがあります。
逆に、結果が出た直後や、キャンペーン成功時に「改善提案」を伝えると、
「この店舗は協力的で信頼できる」と認識されやすくなります。

“タイミングを読む”のも交渉の一部。
数字が出た直後は、本部も耳を傾けやすいですよ。
🧩 最終まとめ
本部との関係を「従うか・拒むか」で考える時代は終わりました。
これからは、数字と信頼をもとに“交渉で動かす”時代です。
無理のない範囲で協力しつつ、必要な場面では戦略的に要望を伝える。
その積み重ねが、店舗の自由度を高め、長期的な安定経営につながります。

“本部とどう付き合うか”は、現場力を試される経営スキル。
数字で語り、姿勢で信頼を積む──それが、無理のない最強の付き合い方です。
本記事で扱った“本部との付き合い方”は、 コンビニ現場の改善や仕組み設計の一部です。 現場改善をPDCAで回す全体像は、以下の記事で整理しています。