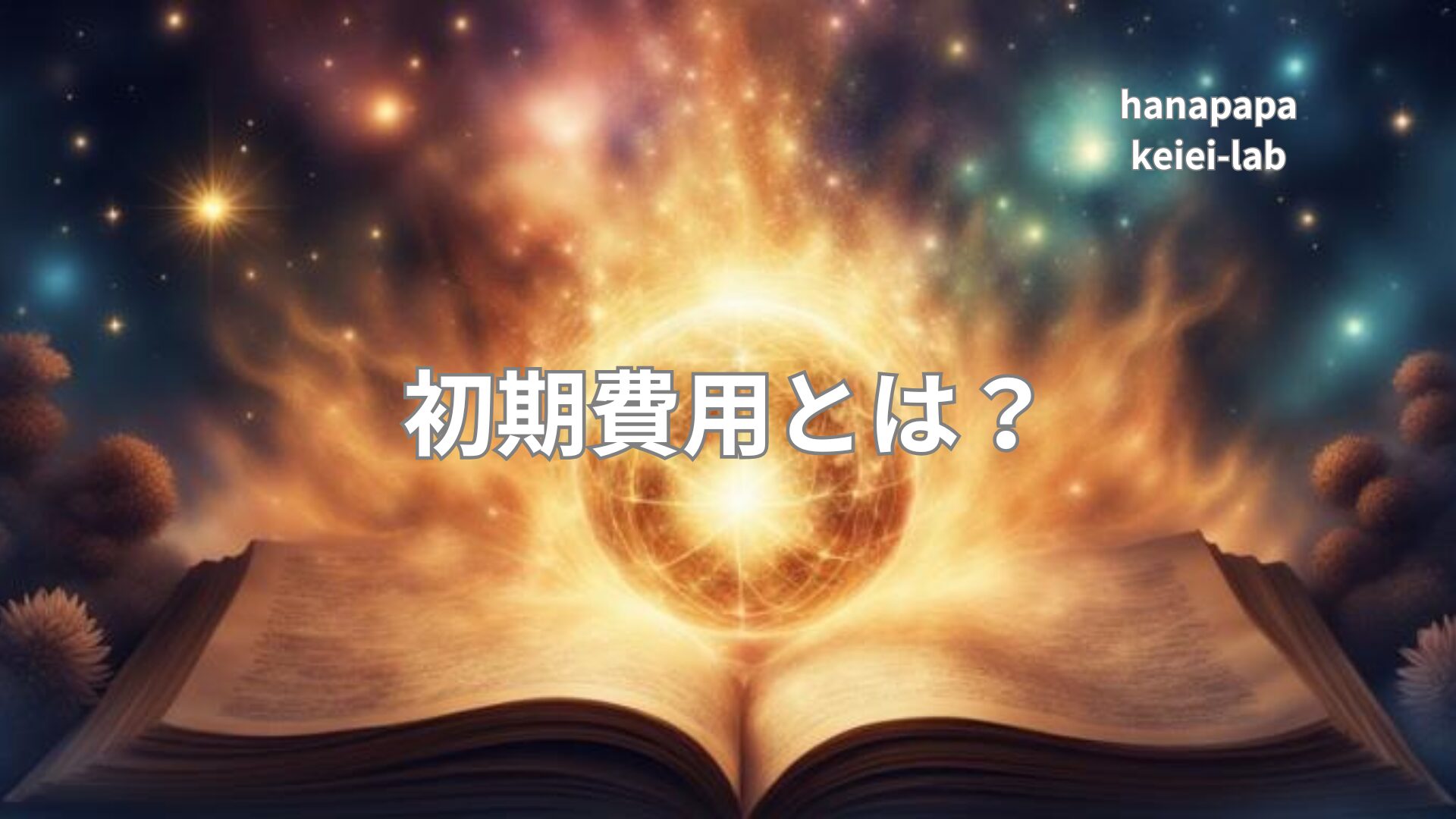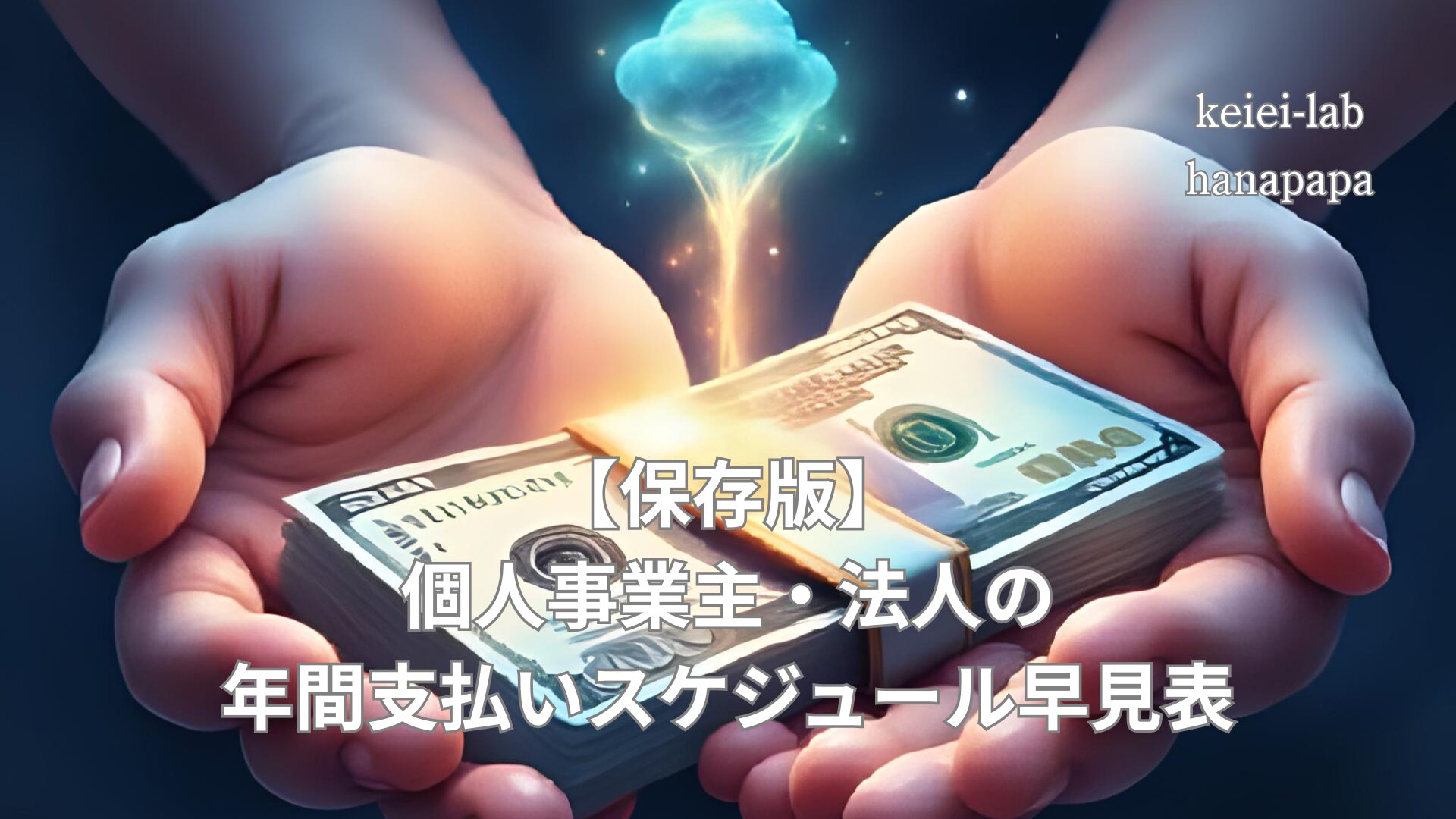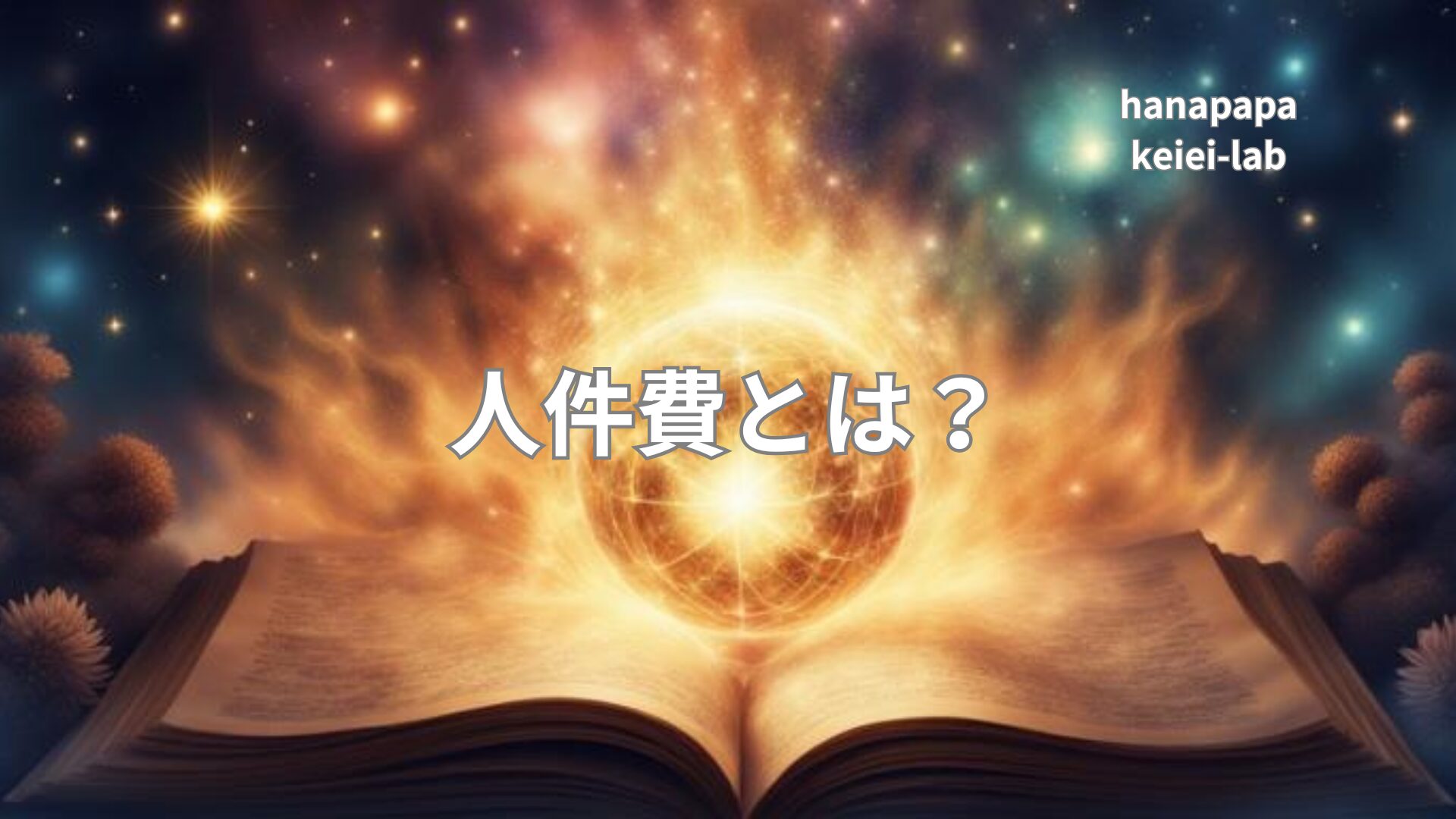走行距離課税で物流コストはどう変わる?小売業への影響と店舗が取るべき対策

近年、ガソリン税収の減少や道路インフラ維持費の増大を背景に、政府が新たな財源として 「走行距離課税」の導入を検討し始めています。 この議論はまだ試験段階ではあるものの、物流業界・小売業に与える影響は決して小さくありません。
商品が店頭に届くまでには、
「生産地 → 工場 → 倉庫 → 店舗」という長いサプライチェーンが存在します。
そのすべての工程で走行距離が発生し、燃料・人件費・配送費の上昇と直結しています。
もし走行距離課税が導入されれば、物流コストはさらに増加し、
商品の値上げ・利益率の低下・配送頻度の見直しなど、店舗運営に直結した課題が浮き彫りになります。

現場にいるとよく分かりますが、物流コストの上昇は本当に“静かな圧迫”なんです。
じわじわ効いてきて、最終的には商品の値付けや在庫戦略に影響が出てきます。
とはいえ、ただ不安を抱えていても何も変わりません。
大切なのは、走行距離課税が導入される前に、どんな影響があり、どう備えるべきかを理解しておくことです。
本記事では、走行距離課税の背景から小売業への影響、そして現場でできる具体的な対策まで、
店舗経営者の視点で詳しく解説していきます。
「値上げの波に飲まれないために、今できることは何か?」 そのヒントを、この記事から持ち帰っていただければ幸いです。
走行距離課税が検討される背景
走行距離課税(走行税)が話題になり始めた理由は、単なる増税ではなく、 日本の税収構造そのものが揺らいでいるためです。 特に、ガソリン税に依存してきた財源が不安定になり、道路の維持管理費を賄えなくなりつつあります。
税収構造の変化
道路整備の財源として長年支えてきたのが「ガソリン税」です。 しかし、燃費性能の向上・車離れ・物流効率化などの要因により、 ガソリンの消費量自体が右肩下がりとなり、税収は減り続けています。
道路は全国に張り巡らされているため、少子高齢化が進む中で、 インフラ維持に必要な費用はむしろ増える方向。 そのため政府は、“燃料に課す税ではなく、走った距離に応じた税”へと 財源構造の転換を模索しています。
EV普及とガソリン税減収
走行距離課税が加速して議論されている最大の理由のひとつがEV(電気自動車)の普及です。
EVはガソリンを使わないため、ガソリン税を支払いません。 つまり、EVが増えれば増えるほど、従来の税体系では 「道路を使うのに負担をしていない」という不公平感が発生してしまいます。
こうした背景から、海外ではすでに走行距離課税の導入事例が広がっており、 日本でも「公平性を保つための新しい仕組み」として検討が始まったのです。

EVの普及は時代の流れ。でも税収がないと道路を維持できません。
“使った分だけ負担する”という仕組みは、今後ますます議論されていきそうですね。
インフラ維持費の増大
日本の道路インフラは高度経済成長期に一気に整備されたため、 現在は老朽化のピークを迎えています。
舗装の補修、橋梁の補強、トンネルの安全対策など、多額の維持費が必要な中、 ガソリン税収は逆に減少するという「逆風」が続いています。
こうした構造問題を解決する手段として、
「実際にどれだけ走ったか」に応じて税負担を決める 走行距離課税が注目され始めました。
背景から見える「小売への波及」
ここまで見てきた背景は、物流コストが上がる未来を示唆しています。
道路維持が必要 → 税負担が必要 → 走行距離で課税 → 配送コストに直結。
この流れは避けられず、小売業界にも確実に届きます。
特にコンビニ・スーパーのように日配品の配送頻度が高い業態では、 課税の影響は商品価格・仕入れ・利益率にストレートに響きます。

現場で働くほど感じますが、物流コストの変化って本当に敏感なんです。
税制が変われば、確実に「売場」と「利益」に影響が出ます。
走行距離課税が物流コストに与える影響
走行距離課税が導入された場合、最も影響を受けるのが物流コストです。 なぜなら、配送車両が走る距離の多さや配送回数の多さは、小売業の特徴ともいえるからです。
コンビニやスーパーなどの小売業は、商品供給のほとんどを毎日の配送に依存しており、 この構造そのものが走行距離課税との相性が悪いと言えます。
配送コストへの直接的な影響
配送トラックは毎日決まったルートを走行し、店舗へ商品を届けています。 その「走った距離」がそのまま税額に上乗せされれば、 1回1回の配送コストが確実に増加します。
特に日配品や弁当・惣菜など、鮮度が重要で配送頻度が高い商材では、 配送コストの上昇は利益を直撃し、店舗運営への負担が大きくなります。
商品価格・利益率への波及
物流コストの増加は、最終的に商品の販売価格に波及します。 メーカー → 卸 → 物流 → 小売まで、すべての段階でコストが上がるため、 自然と値上げ圧力が強くなります。
ただし、小売側が必ずしもそのまま価格転嫁できるとは限りません。 価格競争が激しい業界では、店舗側が吸収せざるを得ないケースも多く、 その結果として利益率の低下につながります。

値上げしたいけど、簡単にはできない…これが現場の本音です。
ちょっとした物流コストの変化でも、粗利をかなり圧迫します。
地方・都市部で異なる負担
走行距離課税の影響は、店舗の立地によって大きく変動します。
- 都市部:配送距離が短いため負担は比較的少なめ
- 地方:距離が長く、複数店舗を巡回するケースも多いため負担増が大きい
さらに、山間部や離島を含む地域では、物流手段そのものが限られており、 配送コストが極端に上がりやすい構造になっています。
物流業界の人材不足とのダブルパンチ
走行距離課税の議論と同時に深刻化しているのが、ドライバー不足です。 2024年問題以降、労働時間規制によりドライバーの人件費は上昇傾向にあり、 そのコストが物流費に反映されています。
そこに走行距離課税が重なれば、 「人件費+走行距離課税」という二重のコスト要因が発生します。
これは物流企業にとっても負担となり、 最終的には小売業がそのコストを受ける形になります。

ドライバーさんの人手不足は現場でも実感します。
そこに課税が加われば、配送費はさらに上がるのは避けられませんね…。
影響のまとめ(小売視点)
小売業が受ける影響をまとめると、以下の通りです。
- 配送のたびに課税 → コスト増
- 商品価格への波及 → 値上げ or 利益率低下
- 地方ほど負担増 → 地域格差の広がり
- 物流人材不足と合わさり、さらなるコスト圧力
つまり、走行距離課税は物流業界だけの問題ではなく、
「小売の現場に直結する構造的な課題」といえます。
小売業が今から取るべき現実的な対策
走行距離課税はまだ検討段階にあるものの、物流コストが上昇トレンドにあることは間違いありません。 だからこそ、課税が始まる前から「コスト増を見据えた店舗運営」に取り組むことが重要です。
ここでは、現場で今日から実践できる“現実的”かつ“効果の出やすい”対策をまとめました。
配送頻度の最適化(ムダな配送を減らす)
最初に取り組むべきは、配送頻度の見直しです。 とくに日配品・パン・デイリー・チルドといったカテゴリーは、配送が多く物流コストがかかりやすい領域です。
以下の対策が有効です:
- 発注精度を上げて「過剰在庫」を防ぐ
- 売れ行きに合わせて“ピーク以外の配送量”を調整
- 定番商品のフェース管理で在庫圧縮
- 曜日別の需要変動に応じて配送量を最適化
配送回数が減れば、その分だけ走行距離課税の負担も軽減できます。

コンビニの場合配送料は本部持ちでしょうが、だからといって蔑ろにして良いというわけではありません。あくまでも共存の関係なので無視できません。
売場の効率化(フェース管理/死に筋カット)
売場が非効率だと、発注にもムダが生まれ、結果として配送量の増加につながります。 そのため、売場効率の改善は物流コスト対策として非常に重要です。
具体的には:
- フェースが増えすぎている商品を適正に戻す
- 死に筋商品を大胆に削減して在庫量を圧縮
- 売場に合わない商品を入れ替え、回転率を上げる
- 売上が低迷しているカテゴリーの縮小
フェース管理と死に筋カットは、廃棄削減にも直結し、利益改善にも大きく貢献します。

売場改善はコスパ最強の施策です。
物流コスト対策でもあり、利益改善にもつながる“一石二鳥”の取り組みですよ。
地域特性に合わせた商品構成
走行距離課税は、都市部よりも地方の方が負担が大きくなりやすいという特徴があります。 だからこそ、地域特性に合わせた商品構成が必要です。
例えば、地方店舗では輸送コストが高いため、以下のような戦略が効果的です:
- ローカル商品(地元メーカー)の導入を増やす
- 配送頻度の少ないカテゴリーを強化する
- 季節・曜日による売れ行きの差をデータで最適化
- 売れにくい商品は在庫を圧縮して滞留を防ぐ
「売れる商品を絞る」という発想が、物流コスト対策に直結してきます。
物流依存度を減らす取り組み(店舗側で完結できる工夫)
走行距離課税が導入されれば、物流依存の高さそのものがリスクになります。 そこで、小売店舗側でできる「物流に頼らない工夫」が重要です。
例えば、以下のような取り組みがあります:
- 店内調理・簡易加工の強化(焼きたてパン、カットフルーツ等)
- 地元メーカー・直納業者との取引を増やす
- 廃棄を減らすことで仕入量を抑える
- ストック型商品の比率を増やす
特に「地元・近距離」のサプライヤーを使うことで、走行距離が短くなり、物流負担も軽減されます。

小売は“仕入れが命”です。
どこから仕入れるか、何を仕入れるかだけで物流コストはかなり変わります。
対策全体のまとめ
走行距離課税を見据えて小売が取るべき対策は、以下の3つに集約できます。
- ①ムダな配送を減らす
- ②売場効率を最大化し、必要量だけ仕入れる
- ③地域・店舗特性に応じた商品戦略を取る
これらはすべて、現場がすぐに取り組める“実務的な施策”です。 物流コストの上昇が続く時代だからこそ、小売は早めの手を打っておく必要があります。
生活者(お客様)にも起こる変化と影響
走行距離課税は、物流業界や小売業だけの話ではありません。
最終的には「生活者一人ひとりの暮らし」に影響が出てきます。
ここでは、お客様側の視点から起こり得る変化を整理してみましょう。
商品の値上がりで「なんとなく高くなった」が増える
まず考えられるのが、商品の値上がりです。
走行距離課税による物流コスト増加は、少しずつ仕入れ価格や販売価格に反映されていきます。
ただし、値札に「走行距離課税分」と書かれるわけではありません。
お客様からすると、
- 前よりちょっと高くなった気がする
- いつの間にか、100円じゃ買えなくなっている
- 気づいたら“お得感”のある商品が減っている
といった、じわじわとした“体感値上げ”として映る可能性が高いです。
選べる商品の減少(ラインナップの見直し)
物流コストが増えれば増えるほど、「売れない商品」を置いておく余裕がなくなります。
その結果として、店舗側は次のような判断を迫られます。
- 回転の悪い商品を入れ替える
- 類似商品が多いカテゴリーを絞り込む
- 売れ行きの弱いサイズ・フレーバーを削減する
これは、お客様から見ると 「前はあった商品がなくなった」 「お気に入りの味が消えてしまった」
という形で現れます。

店側も本当は残してあげたいんです。
でも“動かない商品”を置き続けるのは、これからますます難しくなっていくと思います。
地域によって変わる負担格差
走行距離課税は、地域によって影響の大きさに差が出ます。
特に、次のようなエリアでは負担が増えやすくなります。
- 物流拠点から距離のある地方・郊外エリア
- 山間部や離島など、配送ルートが限られる地域
- 人口が少なく、1店舗あたりの売上が小さい地域
同じチェーン店であっても、都市部と地方で価格差が広がる可能性も否定できません。
「どこに住んでいるか」で負担の感じ方が変わってくるのが、この税制の難しいところです。
生活防衛としてお客様が取り始める行動
価格が上がり、選べる商品が減ってくると、お客様も当然生活防衛の行動を取るようになります。
- 特売商品や値引きシールをより意識して選ぶ
- まいにち買いから“まとめ買い”へのシフト
- ネット通販・宅配サービスとの併用
- プライベートブランド(PB)商品の利用増
つまり、お客様の選択眼はこれまで以上にシビアになり、 「本当に価値を感じる商品・お店」だけが選ばれる時代になっていきます。

だからこそ、私たち店舗側は“なんとなく置いている商品”を減らし、
「ここで買いたい」と思ってもらえる売場づくりがますます重要になっていきます。
走行距離課税時代に、小売経営者が持つべき視点
ここまで見てきたように、走行距離課税は物流コストを通じて、
小売業・お客様・地域社会にじわじわと影響を与えていきます。
では、こうした変化の中で、小売経営者はどのような視点を持つべきでしょうか。
「値上げ」ではなく「価値の再設計」として捉える
まず大切なのは、価格の見直しを単なる“値上げ”として終わらせないことです。
物流コストが上がる以上、利益を守るために価格改定が必要になる場面も出てきます。
その際に意識したいのが、「値段」ではなく「価値」を一緒に見直すという発想です。
- 量や内容、サービスを見直し“選ばれる理由”を明確にする
- ただ高くするのではなく、満足度を上げる工夫を同時に行う
- 「なぜこの価格なのか」を説明できる状態をつくる
価格だけが先行して上がってしまうと、お客様の不信感につながります。
一方で、価値が伝われば、多少の価格上昇は受け入れていただける余地が生まれます。
お客様と正直に向き合うコミュニケーション
価格や商品の変化が続くと、お客様の中には不安や不満を感じる方も増えてきます。
だからこそ、店舗としてのコミュニケーションの質が問われるようになります。
例えば:
- 店頭POPで「原材料・物流費の高騰」に触れつつ、努力している点も伝える
- スタッフが「この商品、本当におすすめですよ」と自信を持って勧められる環境をつくる
- 常連様との会話で、さりげなく価格や商品の変化について説明する
小さな一言、ささやかな対話でも、
「ちゃんと考えてくれているお店なんだな」と感じてもらえれば、信頼関係は深まります。

値上げそのものより、“説明がないこと”に不信感を持たれることが多いです。
だからこそ、正直に、丁寧に、お客様と向き合うことが大切だと思っています。
「物流コスト」を言い訳にしない現場改善
もちろん、外部環境の変化はどうにもならない部分もあります。
しかし、そこで「物流コストが上がったから仕方ない」と諦めてしまうと、 現場から改善の芽がなくなってしまいます。
むしろ、走行距離課税の議論をきっかけに、
- 発注・在庫管理の見直し
- 売場づくりの改善
- 人件費・光熱費など、他コストとのバランス調整
といった、「自分たちで変えられる部分」に意識を向けることが重要です。
まとめ:走行距離課税の時代を生き抜くために
走行距離課税は、まだ具体的な導入時期や制度設計が固まっているわけではありません。
しかし、物流コストが上がり続ける流れそのものは、すでに現実として進行中です。
本記事でお伝えしてきたポイントを、あらためて整理すると次の通りです。
走行距離課税そのものは、一店舗の力ではどうにもできません。
しかし、「その影響を最小限に抑える工夫」と、 「変化の中でも選ばれる店づくり」は、現場の努力でいくらでも積み上げていくことができます。

これからの時代、“ただ仕入れて売るだけ”では厳しくなっていきます。
だからこそ、一緒に「考えて動く店づくり」をしていきましょう。
今日できる小さな一歩からでも、必ず未来は変わります。
本記事が、走行距離課税や物流コストのニュースを見たときに、
「うちの店はどうするべきか?」を考えるきっかけになれば嬉しく思います。
本記事で扱った内容は、コンビニ経営における一つの視点です。 全体の考え方や、現場改善をどう整理するかについては、 以下の記事でまとめています。