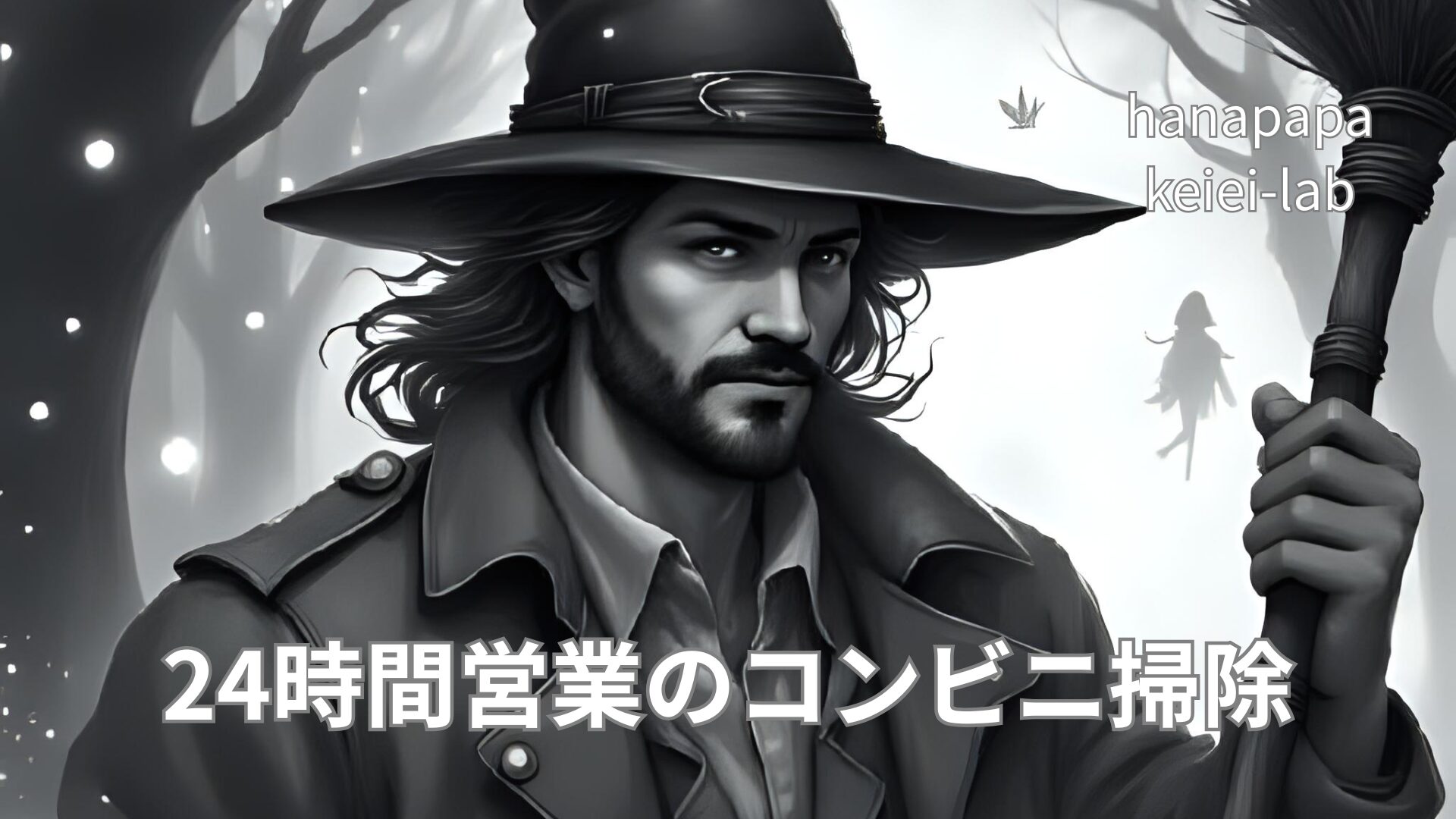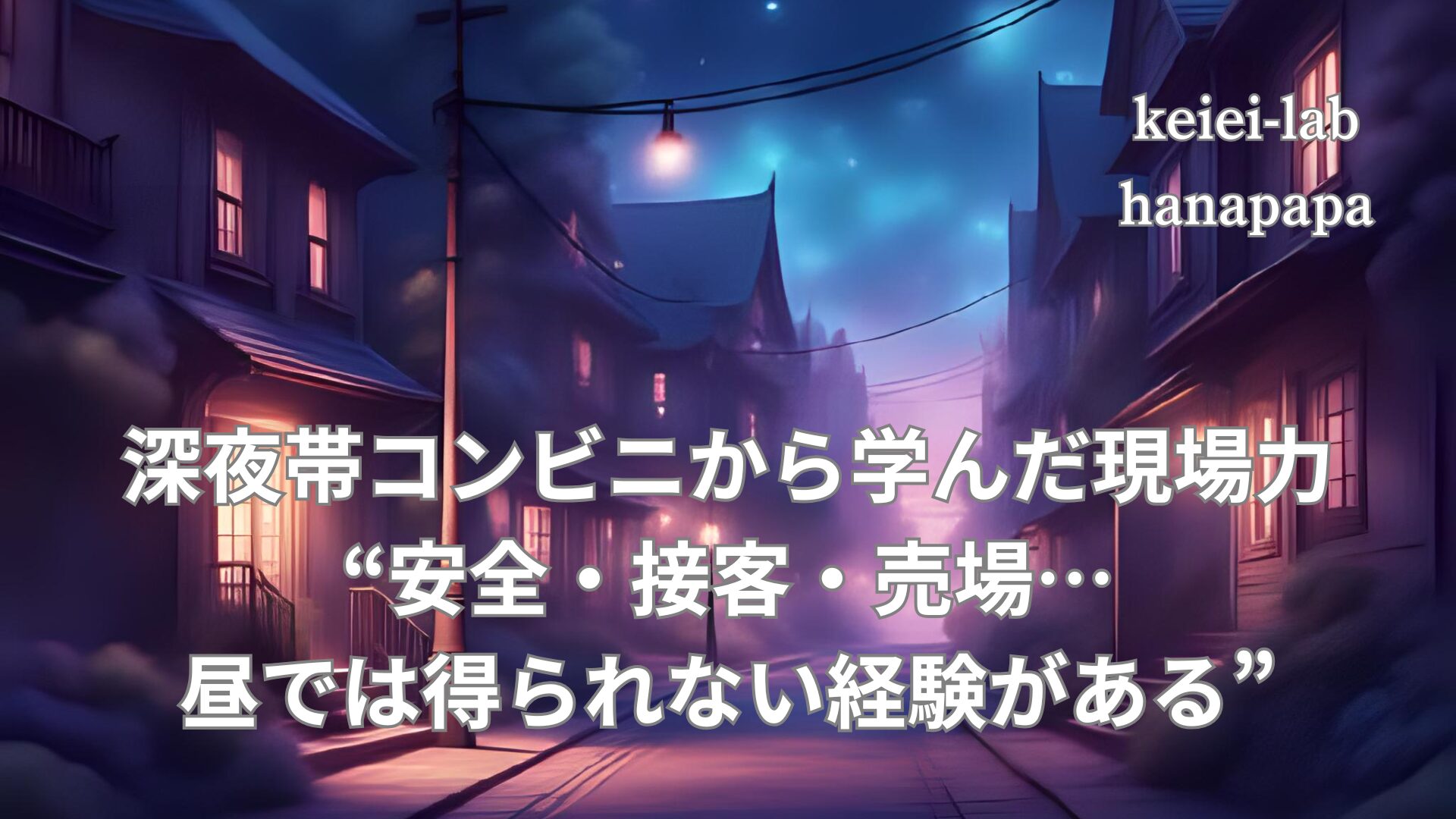【店舗運営】母の日・父の日は“気づき需要”で売上をつくる|コンビニが選ばれる理由と売場づくり

今のイベント需要は「計画買い」よりも「気づき買い」が主流。
コンビニはこの“気づいた瞬間に買える強さ”で圧倒的に優位です。
年賀状やお盆のような「昔ながらの行事需要」が年々減少する中で、 私たち小売業の現場では、お客様の買い物行動が大きく変わってきました。
その中でも、母の日・父の日は以前と比べて“計画的に準備する人が減っている”という特徴があります。 逆に言えば、当日になってから「今日だった!」「何か渡したい」と思い出すケースが増えているのです。
この変化は、昔ながらのギフト文化の衰退ではなく、 “ライフスタイルが変わったことで生まれた購買タイミングのズレ”と言えます。

母の日・父の日は「忘れられている」わけではなく、 “思い出すタイミングが遅くなっている”だけなんです。
そして、この“タイミングのズレ”こそ、 コンビニが最も力を発揮できるポイントでもあります。
本記事では、母の日・父の日需要を通して見えてきた ・イベント需要の変化 ・コンビニが果たすべき役割 ・現場から見える改善ポイント を、はなぱぱ目線でまとめていきます。
イベント需要の変化|“盛り上がるイベント”と“薄れるイベント”の二極化
ここ数年、イベント需要は大きく二極化しています。 正月・クリスマスのような「トップクラスに認知度が高く、習慣として根付いているイベント」は、今も根強い需要があります。 一方で、バレンタインや節分(恵方巻)、年賀状といった季節行事は、以前よりも勢いが弱まっています。
例えば年賀状は、この10年で利用者が半分ほどに減少。 メールやLINEなどの普及により「わざわざ出さない」人が増えています。 お盆も同様で、墓参りの習慣自体が薄れつつあります。 背景には「墓の管理サービス」の普及があり、現地に行かなくても常に清掃・整備された状態が維持されるようになったことも大きな要因です。
では、母の日・父の日はどちら側なのかというと…… 認知度は高いのに、準備する人が減ってきている“中間イベント” に分類されます。
「行事離れ」ではなく、“準備タイミングの変化”が起きている
母の日・父の日の需要が落ち着いてきている背景には、 昔と比べて「準備にかける時間」が大きく変わったことがあります。
- ネット注文が増え、事前予約の文化が薄れた
- スマホやLINEで連絡する文化が普及し、年賀状のような事前準備が減った
- 共働き世帯が増えて、イベント準備にかける余裕が減った
- “忙しいから当日でいいや”という価値観が浸透している
この数年の生活スタイルの変化により、 季節イベントは「事前に計画して買う」よりも、 “当日気づいて買う” 行動が際立って増えています。

現場でも「今日母の日か!」「帰りにちょっと買っていくか」という声、本当に増えました。
イベント需要が減る=売上が減る、ではない
イベント全体の需要が落ちると、 一見「小売全体の売上が減るのでは?」と思われがちですが、 実はそう単純ではありません。
むしろ、需要が変化することで、 “どの業態が購入タイミングを取りやすいか” が変わります。
母の日・父の日の市場では今、 スーパーや専門店のように「早い時間に閉まる店」よりも、 “24時間開いていてすぐに買えるコンビニ”に優位性が移っています。
つまり—— イベント需要は減るのではなく、“どこで買われるか”が変わった。 これが現場で感じる一番大きな変化です。

イベントは弱くなったのではなく、“買われる時間帯”が変わっただけ。
ここに気づける店は繁忙期でなくても売上を作れる。
小売業での影響|“計画買いから当日買いへ”のシフトが店舗の役割を変える
イベント需要が落ち着いてきているということは、当然ながら小売全体の売上構造にも影響します。 スーパーやデパートでは、母の日・父の日に合わせた特設コーナーの縮小や、販売期間の短縮が目立つようになりました。
つまり、「イベントそのものの魅力が薄れた」のではなく、 “まとめて買う習慣”が弱くなったのです。
昔は「母の日ギフト=事前に買いに行く」という行動が一般的でしたが、 現在は生活スタイルの変化により、次のような行動が増えています。
- 忙しくて買いに行けず、当日思い出す
- ネット注文が増え、店舗に行く回数が減った
- 家族イベントの準備に時間を割かなくなった
- “忘れたらその時に買う”というライトな価値観の広がり
こうした変化が、小売全体の売上の波を変えているのです。

現場でも「今日だった!」という声の多さに驚きます。 計画買いより当日買いが主流になってきています。
“計画買いの減少”はピンチではなく、業態ごとにチャンスがある
スーパーや専門店のように、 「事前に決めて買う」行動を前提とした業態では売上が伸びにくい一方、 当日買いが増えるということは、 “すぐ買える店が選ばれる” という消費行動の変化でもあります。
逆に言えば、 24時間営業・深夜早朝対応・小ロットのギフトが置けるコンビニは、 母の日・父の日の需要が減るどころか、 新しい需要を獲得できるポジションにいます。
実際に現場でも、次のような動きがよく見られます。
- 「今日母の日だよ」と思い出して立ち寄る
- 帰省前に小さなプレゼントを買う
- 遠方の家族へLINEギフトと一緒に“手渡し用”を買う
- 職場で急に思い出してコンビニへ走る
このように、 計画買いの減少=売上ダウンではなく、 “買われるタイミングと場所が変わった” と捉える方が、今の小売トレンドを正確に反映しています。

昔はカーネーション+和菓子のような“定番ギフト”が売れましたが、
今は「小さくてすぐ渡せるもの」へ需要がシフトしています。
コンビニの強み|“気づいたときに買える”は最大の価値
イベント需要が「当日買い」へシフトしている今、 もっとも強みを発揮するのがコンビニです。 その理由はシンプルで、 “気づいた瞬間に買える店” だからです。
スーパーは閉店時間があるため、 「帰りに買おうと思っていたのに閉まっていた」というケースは多くあります。 しかしコンビニなら、早朝でも深夜でも買える。 この“不便にならない仕組み”こそ、現代のイベント需要にぴったりハマっているのです。
思い出した瞬間に寄れる=強力な購入導線になる
現場で働いていると、こんなお客様をよく見かけます。
- 会社で「今日母の日だよ」と聞いて急いで買いに来る
- 帰省前に小さなプレゼントを手に取る
- 仕事終わりに「何か渡したい」と思い立つ
- 深夜の帰宅前に、花の代わりにスイーツを買って帰る
これらはすべて、コンビニの「即時性」×「アクセスの良さ」によって生まれる購買です。 “気づいたときにすぐ行動できる”環境を提供できるのは、コンビニならではの強みです。

毎年のように、当日夜に「何かありますか…?」と聞かれるお客様がいます。 こういう方こそ、コンビニの潜在需要なんです。
コンビニが用意すべき“当日買い向けギフト”
当日買いの特徴は、 「高額ではなく、すぐ渡せて気持ちが伝わるもの」 が求められる点です。
具体的には、次のようなアイテムがよく動きます。
- 小さめのカーネーションやミニブーケ
- 菓子折り・スイーツギフト(1,000円以内)
- コーヒー・紅茶のギフトパック
- ハンカチ・靴下・簡易ギフト
- “一言メッセージカード”との組み合わせ
すぐ渡せる小さなギフトを揃えておくことで、 「忘れてた!でも助かった!」 というお客様を気持ちよく受け止めることができます。
これらは単に売れるだけではなく、 “この店は頼りになる”という評価を生み、 結果的にリピート率の向上につながります。
コンビニの役割は“母の日・父の日を諦めさせない店”になること
母の日・父の日のような中規模イベントでは、 「準備できなかった=もう何もしない」という選択を取る人も少なくありません。
しかしコンビニが“当日でも渡せる小さなギフト”を置くことで、 「諦める人」を「行動する人」に変える役割を果たすことができます。
これは売上以上に、 お客様の人生の節目に関わる大切な価値提供でもあります。

奥様に何か買って行かないとトラブルになりますよ。
大量販売ではなく「信頼感」の積み重ねが店の価値になる
母の日・父の日におけるコンビニの取り組みは、 決してスーパーのように大規模な売上を狙うものではありません。 事実、売場スペースが限られている以上、 大量のギフト商品を展開することは現実的ではありません。
しかし、だからこそコンビニには “別の価値”を発揮できる立ち位置があります。
「あえて手を出さない」のも戦略だが、チャンスを見逃さない姿勢が重要
コンビニ経営では、仕入れや売場の使い方ひとつで結果が変わります。 母の日・父の日のような中規模イベントの場合、 「無理に大量展開して廃棄を増やす」という判断を避けるのは賢明です。
ですが、“何もしない”という選択肢ではなく、 小さく・軽く・売れるものだけ を展開することで、 コンビニならではの強みを活かすことができます。
その狙いは、 売上よりも“信頼感”を積み上げること。

「ここなら当日でも何とかなる」 この“安心感”は、売上よりも大きな資産です。
“ちょうどよい手軽さ”が信頼を生む
実際、母の日・父の日の現場を見ていると、 お客様が求めているのは 「豪華すぎるギフト」ではなく「ちょっとした気持ちが伝わるもの」 です。
たとえば——
- ミニブーケ
- 小さめのお菓子ギフト
- 紅茶・コーヒーのギフトパック
- メッセージカード
こうした“軽いギフト”を置いておくだけで、 お客様の中では次のような印象が生まれます。
「この店は気が利く」「困ったときに頼れる」 → 結果として日常利用の頻度が増える
この“信頼の積み重ね”こそ、 長期的なロイヤルカスタマー(常連)を生み出す源泉になります。
コンビニの役割は「お客様の生活リズムを支える店」になること
母の日や父の日は年に一度ですが、 “信頼感”は毎日の店づくりで積み上がります。
- ちょっとしたプレゼントが買える
- 忘れても当日フォローできる
- 忙しい人でも恥ずかしくないラインナップがある
こうした便利さが、コンビニの強さをさらに際立たせます。
つまり、コンビニが母の日・父の日で狙うべき価値は 短期の売上ではなく「この店は頼りになる」という評価 です。
まとめ|母の日・父の日は“売上”よりも“信頼”を積み上げるチャンス
母の日・父の日の需要は、昔ほど大きくはありません。 しかし、その背景には「イベント自体が弱くなった」というよりも、 お客様の準備タイミングが変化したという事実があります。
今の時代は、計画買いよりも “当日気づいて行動する” “今必要だから買う” という買い方が主流です。
つまり、コンビニにとってはチャンスであり、 大きなイベントよりも“小さな気づき”を拾える業態として、 本来の強さが発揮できる場面でもあります。

“今日だった!” この一言を救える店は、お客様の信頼を一気に獲得できます。
コンビニがやるべきことは“大きく売る”ではなく“期待に応える準備”
母の日・父の日において、コンビニが狙うべきなのは 大きな売上ではありません。 むしろ、次の3つを意識した“信頼の積み上げ”です。
- ① 当日でも渡せる小さなギフトを置く
- ② ミニブーケ・スイーツ・メッセージカードなど軽い導線を作る
- ③ 忘れた人を救う売場を整えておく
この3つを整えるだけで、 「この店は助かる」「ここなら安心」という “信頼のストック”が積み上がります。
信頼のストックは、イベント当日だけでなく、 日々の来店頻度やリピート率にも確実に影響を与えます。
小さな価値提供が“常連”を育てる
母の日・父の日は、年間イベントの中でとびきり売れる日ではありません。 しかし、“小さな困りごと”を解決できる店は、 お客様の日常の中で特別な存在になります。
・ちょっとしたギフトが買える ・困ったときに助けてくれる ・当日に思い出しても大丈夫 こうした積み重ねが、日常の買い物行動にも良い影響を与えます。
最後に:今日の準備が、来年の売上を作る
母の日・父の日は年に一度ですが、 そこで積み上げた「信頼」は一年中効き続けます。
売場を少し整えるだけで、 ミニブーケを数本置くだけで、 メッセージカードをレジ横に置くだけで、 お客様にとっての“選ばれる理由”になります。

今日の5分の準備が、 来週の、来月の、そして来年の売上につながります。
これからのイベント対応は、派手な在庫や大掛かりな演出よりも、 「必要なときに、必要なものがある店」 を目指すことで、確実に結果がついてきます。
廃棄を減らせと言われ続ける現場。でも、売上を作るには一定の“攻め”も必要です。
廃棄率を単なるコストとして見るのではなく、売上を伸ばすための投資という視点から整理した共通入口はこちら。
▶ 廃棄率2〜3%が適正な理由