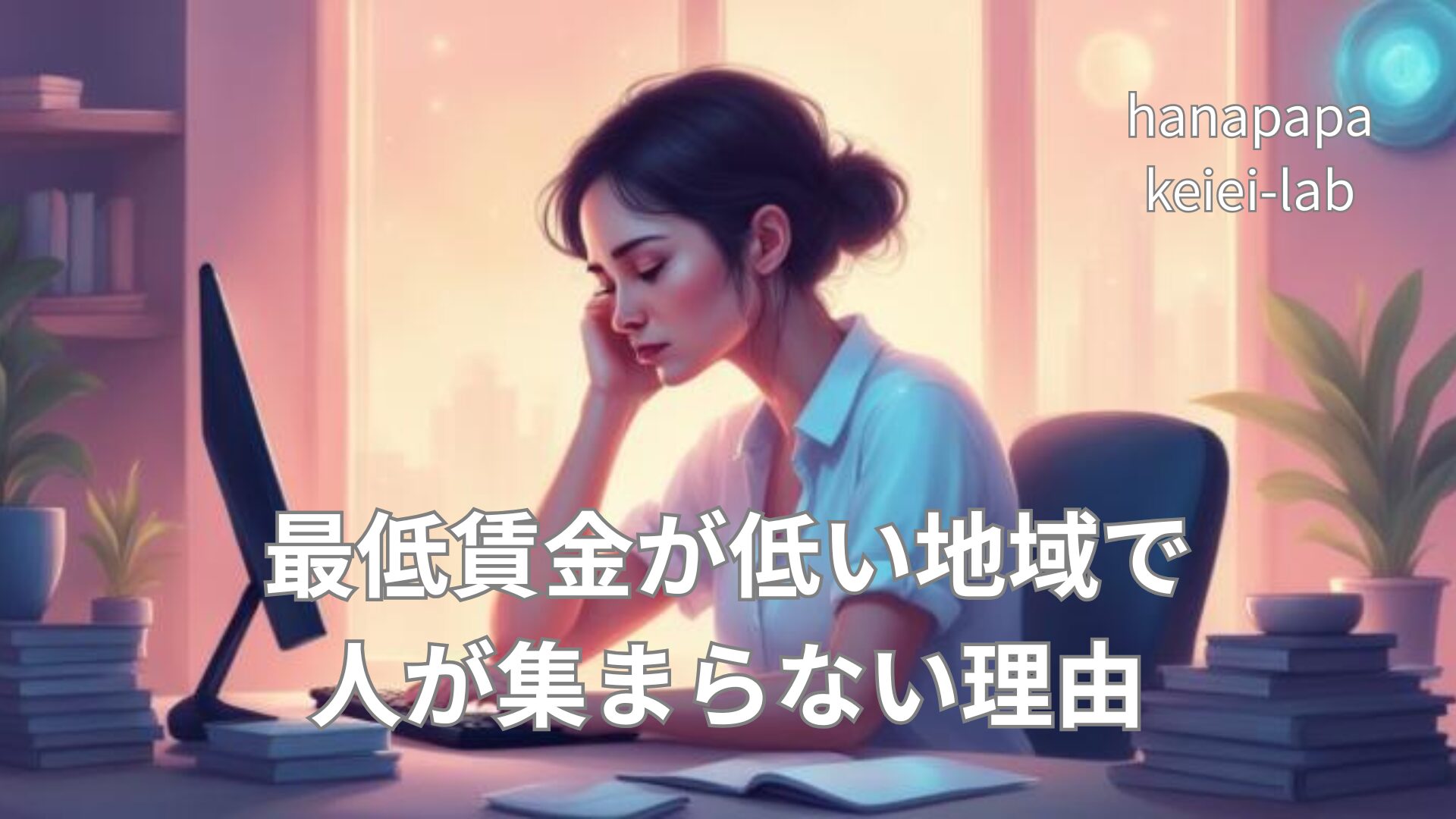【人材育成】怒れない時代に、スタッフを“正しく注意”する方法|信頼で導くマネジメント

――「怒らずに伝える」よりも、「信頼して伝える」へ
「注意したいけど、何をどう言っても“パワハラ”になる気がする」
「でも放っておいたら、店の空気が乱れる……」
そんなジレンマを抱えたことはありませんか?
特に今の時代、店長やリーダーは“怒れない上司”になることを求められています。
一方で、現場では「言わなければ伝わらない」「伝え方を間違えれば関係が壊れる」という難しさもあります。
実際、スタッフを育てる中で最も難しいのは、
「叱ること」ではなく「信頼を壊さずに注意すること」。
本記事では、
私自身が現場で経験した“注意の伝え方を変えるだけでスタッフが変わった”具体例をもとに、
ハラスメントにならない「信頼型の指導」の進め方をお伝えします。
指導したいけど、何でも「ハラスメント」になる時代
――「伝える勇気」が試される現場へ
「少し強く言っただけで“パワハラ”と言われるかもしれない」
「注意しなければ仕事が回らない。でも、言い方ひとつで信頼が崩れる…」
今、こうした葛藤を抱える店長やリーダーが増えています。
以前なら、「叱る」「指摘する」は当たり前でした。
しかし今は、“感情をぶつける指導”が許されない時代。
一方で、“何も言わないリーダー”もまた現場を弱くしてしまいます。
つまり、私たちは今、「言えない」「伝わらない」時代の真ん中にいるのです。

私自身も「見て覚えろ」世代なので、難しさを抱えながらこの問題と向き合っています。
指導が「悪」ではなくなった時代のすれ違い
現場でよく起こるのが、
「言ってもいいこと」と「言ってはいけないこと」の境界が曖昧になるケース。
たとえば――
- 「もっと早く動け」と言えば“威圧的”
- 「もう少し考えて」と言えば“否定的”
- 「次はこうしてみよう」と言っても、“責められている”と受け取られる
リーダー側は「指導のつもり」で伝えていても、
スタッフ側が「否定された」と感じることで、ハラスメント認定のリスクが生まれます。
これは“言葉の問題”というより、
「信頼関係ができていない状態で伝えている」ことが根本原因です。
今の時代に求められる“信頼型の指導”
これからのマネジメントに必要なのは、
「叱らない指導」ではなく、「信頼して伝える指導」です。
ハラスメントを恐れて“何も言わない”のではなく、
信頼をベースに「伝える勇気」を持つこと。
- 怒るのではなく、「理由」を伝える
- 責めるのではなく、「一緒に考える」
- 命令するのではなく、「提案する」
この3つの姿勢があるだけで、
注意や指導は“攻撃”から“対話”に変わります。

言葉を選ぶのではなく、良い信頼関係を築いておくこと。

「怒ることをやめた」だけでは、チームは動きません。
必要なのは、“信頼して伝える勇気”。
スタッフが「この人は自分の味方だ」と思える関係を築けたとき、
注意は“指導”に変わり、チームは前に進みます。
感情のままに注意してしまうと逆効果
――怒るより、“理解する”ことが先にある
たとえば、出勤して店の様子を見たときに、
「昨日教えたことができていない」「また同じミスをしている」
そんな光景を目にすると、つい口から出てしまう言葉があります。
「なんでできてないんだ!」
その瞬間、リーダーとしての冷静さよりも、
“怒り”や“焦り”が先に出てしまう――。
誰にでもある自然な反応ですが、これは最も避けるべき対応です。
指導の前提は「性善説」であること
リーダーとしてまず意識すべきは、
「できない=怠けている」と決めつけないこと。
私はこれを“性善説マネジメント”と呼んでいます。
たとえば、こう考え直してみましょう。
- 「忙しくて確認の時間が取れなかったのかもしれない」
- 「ミスが出るほど負荷が高かったのかもしれない」
- 「前回の指示が伝わりきっていなかったのかもしれない」
まずこの“理解のクッション”を置くことで、
相手に対しての言葉も、表情も、自然と柔らかくなります。
状況を把握してから、冷静に話す
感情を抑えるための第一歩は、「情報の整理」です。
怒る前に、次の3点を確認しましょう。
| 確認項目 | 目的 |
|---|---|
| ① その時の時間帯・客数 | 業務量が多すぎなかったかを把握する |
| ② 顧客層や接客内容 | 想定外の対応に時間がかかっていないか確認する |
| ③ スタッフ構成 | 突発的な欠勤やフォロー不足がなかったかを確認する |
これらを把握した上で初めて、
「本人に話すタイミング」を考えるのが理想です。
感情の勢いのまま話すよりも、
5分後・休憩後・翌日でも構いません。
一呼吸置くだけで、“怒り”は“冷静な伝達”に変わります。

伝えたい相手の感情が穏やかなタイミングが良いと思います。自分が落ち着いていても相手が忙しいタイミングだと伝わり方に誤解がうまれやすいです。
💬 言葉の“入り口”を変えるだけで結果が変わる
話を始めるとき、NGなのはこの一言です。
「なんでやってないの?」
この言葉には“責め”のニュアンスがあり、
相手は反射的に防御態勢に入ります。
代わりに、こう切り出してみてください。
「今日はいつもと違うことがあった?」
「昨日より忙しかったかな?」
たったこれだけで、
相手は“話を聞いてくれている”と感じ、
自然と原因を自分から話し始めます。
この“入り口の言葉”が変わるだけで、
注意の時間が「対立」から「共有」に変わるのです。
実践ワーク:感情をコントロールする3ステップ
| ステップ | 内容 | ポイント |
|---|---|---|
| ① 事実を確認する | 状況や背景を先に把握する | 「なぜ起きたか」を感情抜きで理解 |
| ② 感情を整える | 深呼吸・5分間待つ | 感情をクールダウンしてから話す |
| ③ 対話で伝える | “怒る”ではなく“共有する” | 相手の意見も聞きながら進める |

注意することは「正す」ことではなく、「理解を深める」こと。
伝え方を間違えれば、どんな正しい指摘も届きません。
一度、怒りを手放して“なぜ起きたか”に目を向けると、
スタッフは“直す理由”を自分で見つけ始めます。
まとめ:怒らない指導=感情を整理する技術
| 課題 | 対応法 |
|---|---|
| 感情で注意してしまう | 状況を整理して一呼吸おく |
| 指導がきつくなる | 性善説で相手の背景を想定する |
| 会話がぎこちなくなる | 「質問」から始める対話に切り替える |
指導か、改善か――判断の前に「材料を集める」
――“叱る”より“見抜く”ができるリーダーへ
指導の場面で最も多い失敗は、
「状況を見切る前に“言ってしまう”」ことです。
「この子はやる気がない」
「何度言っても変わらない」
そう感じた瞬間に注意してしまう――。
しかし、その判断は本当に正しいでしょうか?
現場では、本人の努力不足ではなく、
仕組みや環境に原因があるケースが少なくありません。
判断の前に「情報」を集める
信頼型マネジメントでは、
“指導”と“改善”を見極めるために、
まず「観察」と「対話」で情報を集めることを優先します。
たとえば、スタッフの動きに気になる点があったとき、
いきなり注意するのではなく、こう整理します。
| 観察ポイント | 確認内容 | 見極めの意図 |
|---|---|---|
| ① 状況 | その時間帯や客数はどうだったか? | 環境要因か、個人要因かを区別する |
| ② 作業量 | 業務が集中していなかったか? | 負荷の偏りを見抜く |
| ③ 周囲の連携 | 他メンバーの動きに問題はなかったか? | チーム全体のバランスを確認する |
| ④ 本人の表情・様子 | 焦り・疲労・沈黙が見られないか? | 感情面の変化を読み取る |
この“観察の4視点”を押さえておくだけで、
指導すべき内容が「人」なのか、「仕組み」なのかが見えてきます。
“言葉の前に、状況を見てから話す”が信頼をつくる
あるスタッフがミスをしたとき、
その場で強く叱ったら関係がぎくしゃくした――そんな経験はありませんか?
多くの場合、本人はすでに“ミスを自覚”しています。
そこにさらに「なんで!」と重ねると、
相手の意識は「反省」ではなく「防御」に変わります。
逆に、「あのときどう感じた?」と声をかけるだけで、
相手の中から“自己分析と改善意識”が生まれます。
これは、心理学でいう「自己決定理論」に基づく考え方。
「自分で気づいたこと」こそが最も行動に影響を与えるのです。
指導が必要なのか、それとも仕組みを直すのか
観察と対話を丁寧に重ねていくと、
「指導すべきはこの人」ではなく、
「改善すべきはこの仕組み」だと見えてくることがあります。
たとえば――
- レジ誤差が続く → 金額チェックの手順が複雑すぎた
- 品出しが遅い → 通路の配置が悪く、作業動線が遠かった
- あいさつが減った → 人手不足で、接客に余裕がなかった
これらを「人の問題」として注意しても、再発します。
しかし「仕組み」として見直せば、改善は継続します。

仕組みを作っているのは経営者側なので、仕組みを疑いたくない気持ちはわかります。でも関係が悪くなる時って、だいたい仕組みに問題がありますよね。
見る・聴く・考える――信頼型リーダーの3ステップ
| ステップ | 行動 | 狙い |
|---|---|---|
| ① 見る(観察) | 状況を客観的に捉える | 「感情ではなく事実」で判断する |
| ② 聴く(対話) | 本人の意見を聞く | 相手に主体性を取り戻させる |
| ③ 考える(改善) | 人・環境・仕組みのどこに原因があるかを見極める | 本質的な対策を取る |
この3ステップを習慣化すると、
“怒る上司”から“考えるリーダー”へと成長していきます。
判断力を高めるための3つの習慣
| 習慣 | 内容 | 効果 |
|---|---|---|
| ① 1日1回、現場を“俯瞰して見る”時間を作る | 感情ではなく事実を整理する | 冷静な判断ができる |
| ② スタッフに“どう思う?”と聞く | 本人の意見を先に引き出す | 改善の方向性が具体化する |
| ③ ミスを“仕組みの鏡”として捉える | 人を責めず、流れを見直す | 再発防止につながる |

経営も現場も、「怒る」より「観察する」ほうが難しい。
でも、見て・聴いて・考えるリーダーは、信頼を失わずに成果を出します。
感情ではなく事実を見つめる姿勢が、
“叱らずに伸ばす”職場づくりの第一歩だと思います。
まとめ:「見抜く力」が信頼を生む
| Before(感情型) | After(信頼型) |
|---|---|
| 「とにかく注意する」 | 「原因を観察して判断する」 |
| 「ミス=本人の問題」 | 「ミス=仕組みの問題かもしれない」 |
| 「言えば変わる」 | 「聴けば気づく」 |
信頼は“抑止力”にもなる
――注意と信頼は、セットで成り立つ
信頼があれば、注意は響く。
信頼がなければ、注意は刺さる。
これが、現場で私が何度も感じた結論です。
信頼関係のある職場では、
リーダーが一言「これ、次から気をつけよう」と言うだけで、
スタッフは素直に受け止め、行動を変えます。
一方、信頼がない職場では、
同じ言葉でも「怒られた」「否定された」と受け取られ、
心の距離が広がってしまいます。
つまり、注意が“響くか・壊すか”を決めるのは“関係性”の深さなのです。
信頼は“抑止力”になる
注意とは、“信頼を前提にした期待の表現”
注意することは、決して相手を責める行為ではありません。
本来は、「あなたに期待している」「だからこそ伝える」というメッセージ。
信頼のない環境では“批判”に聞こえる言葉も、
信頼のある関係では“応援”として届きます。
| 状況 | 同じ言葉でも伝わり方が違う |
|---|---|
| 信頼がない職場 | 「またミスしたの?」=責められたと感じる |
| 信頼がある職場 | 「次はこうしようか」=成長を促されたと感じる |
「注意しなくても伝わる」職場が最強
理想のチームは、リーダーが注意をする前に、
スタッフ同士が自然にフォローし合う職場です。
- 「あ、これ〇〇さんが困るから先にやっておこう」
- 「このタイミングで声かけた方がいいな」
こうした“自主的な気づき”が生まれるのは、
リーダーが信頼を土台にした関係性を築いているから。
注意の頻度が減っていくほど、
チームの成熟度は上がっている証拠です。
信頼で動くチームと、恐れで動くチームの違い
| 観点 | 信頼で動くチーム | 恐れで動くチーム |
|---|---|---|
| 行動の理由 | チームに迷惑をかけたくない | 上司に怒られたくない |
| 空気感 | 互いに助け合い、会話が多い | ミスを隠し、報告が減る |
| 注意の効果 | 行動がすぐ改善する | 一時的に萎縮するだけ |
| 成長スピード | 自発的に挑戦が増える | 失敗を恐れて動けなくなる |
どちらのチームが長く続くかは、一目瞭然です。
現場で実感した“信頼の抑止力”
以前、私の店で「注意されないと動かない」タイプのスタッフがいました。
その子に対して、ある日私はこう伝えました。
「〇〇さんがいてくれると安心なんだ。だから次も頼むよ。」
それ以来、その子は自分から周囲を気にかけ、
誰よりも早く声を出すようになりました。
信頼を伝えた瞬間、人は変わる。
それがリーダーの“伝える力”だと思います。

あるあるですよね。
信頼を築くための3つの意識
| 観点 | 意識すべき行動 | 効果 |
|---|---|---|
| ① 見ている姿勢を伝える | 小さな変化を言葉にする | 「自分を見てくれている」と感じる |
| ② 期待を具体的に伝える | 「あなたに任せたい」と言葉で示す | 責任感と自信が芽生える |
| ③ 注意後にフォローする | 「さっきの件、助かったよ」と一言伝える | 注意が信頼として残る |
これを繰り返すことで、
“怒らなくても動くチーム”が自然と育っていきます。

「私はこう考えたので、このような行動をしました。改善点ありますか?」
こんなメンバーが増えてくると思います。

注意と信頼は、両輪で回すもの。
注意だけでは摩擦が生まれ、信頼だけでは前に進まない。
でも、信頼のある注意はチームを強くし、
「この人の言葉だから聞こう」と思わせる力を持っています。
店舗経営も人材育成も、“怒る”ではなく“響く”を目指したいですね。
まとめ:信頼は最大の指導力
| 結論 | 内容 |
|---|---|
| 信頼は、注意の下地になる。 | 信頼があるからこそ、注意が「応援」として届く。 |
| 注意は、信頼を育てるチャンス。 | 関係を深める“きっかけ”として捉える。 |
| 信頼は、チームを動かす抑止力。 | 「怒られないため」ではなく、「守りたい関係」で行動する。 |
本記事で扱った「ハラスメントを避けたスタッフ指導」の考え方は、 コンビニにおける人材育成・教育設計の一部です。 人材育成と法令対応の全体的な考え方は、 以下の記事で整理しています。