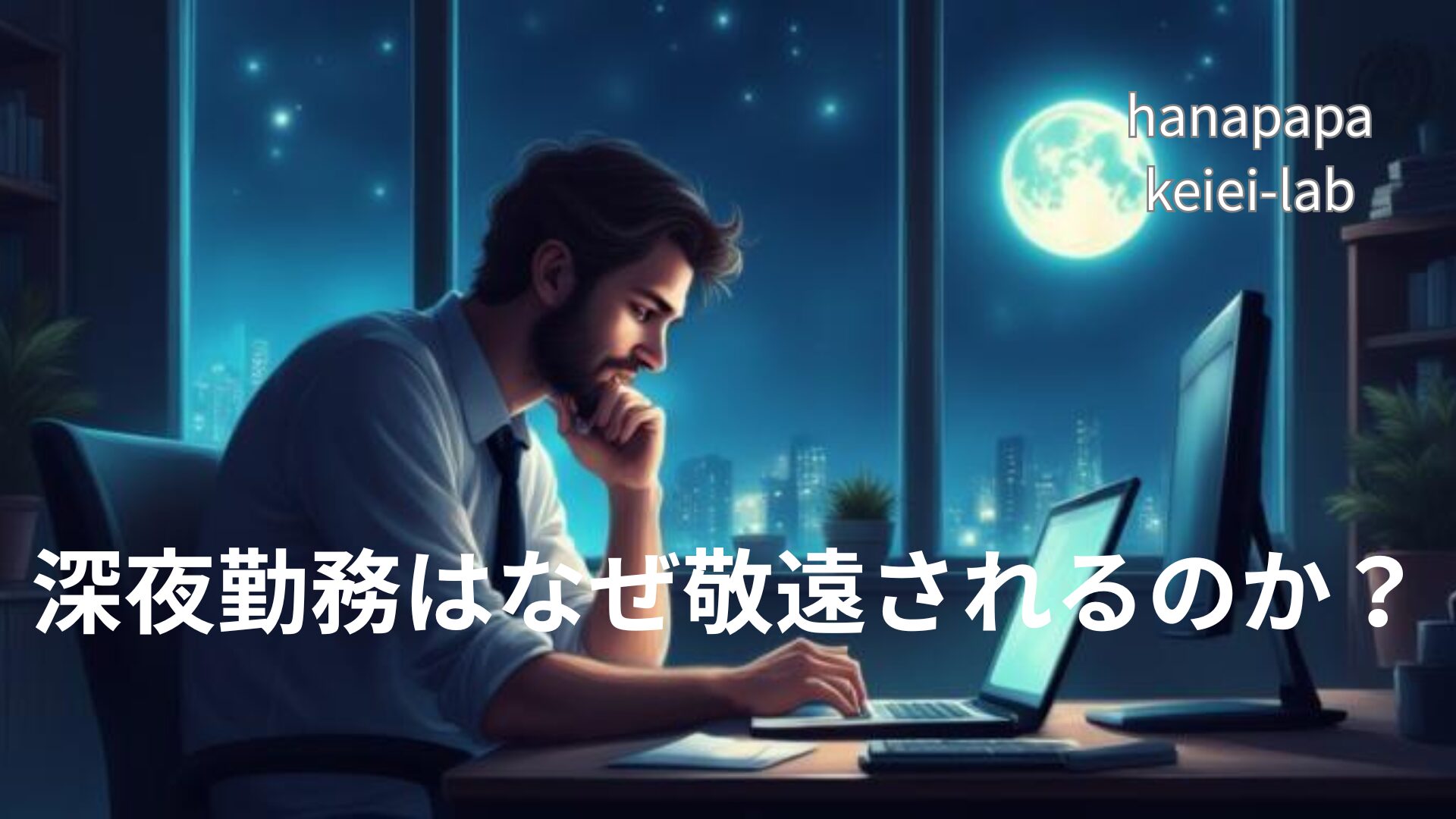マニュアルだけでは人は育たない|“興味”をきっかけにスタッフが伸びる職場づくり

――「マニュアル通りにやってるのに、なぜか成長しない」
そんな悩みを感じたことはありませんか?
最近のコンビニや小売の現場では、教育動画やアプリ指導など、 マニュアルがどんどん充実しています。
それでも現場に立つと、「あの子、どうも伸び悩んでるな…」と感じることがある。
実はその原因、“やり方”ではなく“気持ちの入り口”にあるかもしれません。
今回は、私が実際に経験したスタッフ育成の現場から、
「人が育つ環境づくり」と「興味の活かし方」についてお話ししたいと思います。

「教えること」はできても、「育てること」は別物。
スタッフが“動きたくなる”スイッチは、意外とシンプルなんです。
スタッフ育成の基本は、“適材適所”と“興味の活用”にある
人材確保が難しい時代だからこそ、今いるスタッフに気持ちよく働いてもらう工夫が欠かせません。
特に「教え方」や「関わり方」は、マニュアル以上に重要だと感じています。
マニュアルだけでは人は育たない
マニュアルの限界と“気づき”の瞬間
最近のコンビニチェーンでは、動画マニュアルや写真付き手順書、アプリでの業務確認など、教育ツールがとても充実しています。
一見すると「誰でも同じように仕事ができる」環境が整っているように見えます。
確かに、マニュアルを見れば一通りの作業は理解できます。
レジ操作、商品の前出し、清掃手順――これらは今や、手順通りに進めれば一定の水準に到達できる仕組みです。
「理解」ではなく「納得」が人を動かす
しかし、現場で日々スタッフと関わっていると、こう思う瞬間があります。
「やり方は覚えているのに、動きがぎこちない」
「手順通りやっているのに、なぜかお客様の反応が違う」
つまり、マニュアルは“できるようにする”ためのツールであって、“できるようになる”ためのものではないのです。
たとえば、マニュアルでは「お客様の前を通るときは一礼」と書かれています。
でも、実際に「お客様と目が合って、軽く会釈したら笑顔が返ってきた」
その体験こそが、次の行動意欲につながる“学び”になります。

マニュアルには“10時に掃除をする”って書いてあるから、みんなその時間に掃除をしますよね。でも本当に大事なのは、そこじゃないと思うんです。目の前にゴミが落ちていたら拾う、汚いと感じたらその場で掃除をする――そういう“気づき”の姿勢こそが、仕事の本質なんですよ。
教育体制が整っている今だからこそ、あらためて見直したいのは、
“人が動きたくなる理由”をどう設計するかという視点です。
全員に“同じように教える”ことは難しい
人それぞれの覚えるスピードと得意分野
現場でスタッフを育てていると、誰しも一度は感じると思います。
「同じように教えたはずなのに、なぜできる人とできない人が出てくるんだろう?」
それは、“やる気”や“努力”の問題ではありません。
人にはそれぞれ、覚えるスピード・体力・得意分野が違うだけのこと。
にもかかわらず、全員に同じ指導をしてしまうと、どこかで歪みが生まれます。
適材適所でチームの力を高める
たとえば、飲料の補充作業。
2リットルのペットボトルを何箱も運ぶのは、女性スタッフには体力的に厳しい場合もあります。
その一方で、レジ接客や商品PRになると、表情や声のトーンでお客様を惹きつけるのが上手な方もいる。
大事なのは、「できない」部分を責めることではなく、
“どこで力を発揮できるか”を一緒に探すこと。
補充が苦手なら、レジでお客様との会話を大切にしてもらう。
掃除や整理整頓が得意なら、バックヤード管理を任せてみる。
それぞれの「適材適所」を見つけることが、結果的に店全体の戦力アップにつながります。

どんな仕事に興味があるのか、得意なことや苦手なことは何か――。そんな会話を重ねることで、お互いのことが少しずつわかっていきますよね。こうした日常の会話から関係性を築いていくことも、とても大事だと思います。
店舗経営でよくあるのが、「全員を同じようにできるようにする」という考え方。
でも実際は、全員が同じようにできる店より、
全員が“違う強み”で支え合える店のほうが、長く続きます。
“興味”から始める育成が一番強い
好きなことを入口に教える
スタッフ育成で私が一番意識しているのは、
「その人が興味を持っている仕事から教えること」です。
どんなスタッフにも、「やってみたい」「好きかも」と感じる瞬間があります。
その“興味の芽”を見つけて育てていくことが、成長への一番の近道です。
たとえば、レジに興味があるスタッフには、
接客マナーや操作方法を丁寧に教え、
「お客様とのやりとりって楽しい」と感じてもらう。
お菓子が好きな人なら、
売場づくりやPOPづくりを任せてみる。
掃除や整理整頓が得意なら、
店内清掃やバックヤード管理で力を発揮してもらう。
“好き”が“自信”と“責任感”に変わる流れ
一方で、苦手な作業を無理に教え続けると、
「自分はダメだ」と思い込んでしまうこともあります。
そうなると、意欲が下がるだけでなく、
チーム全体の雰囲気にも影響してしまうのです。
だからこそ、まずは
“できること・好きなこと”からスタートすること。
それが、その人がこの職場で輝くための最初の一歩です。

“好き”を伸ばすと、“自信”が生まれる。
“自信”が育つと、“責任感”に変わる。
育成の本質は、この流れをつくることなんです。
「得意な分野で活躍できる環境をつくる」
この考え方が根づくと、スタッフ同士のサポートも自然に生まれます。
店長が育てるのではなく、チームがチームを育てる空気が生まれていくのです。
苦手を責めず、得意を活かす。人を辞めさせない育成術
「できない」を指摘せず、「できた」を認める
どれだけ丁寧に教えても、途中で辞めてしまうスタッフがいます。
「最近、元気がないな」と思った矢先に退職の連絡。
そんな経験をしたことがある方も多いのではないでしょうか。
私自身、何度もこの「退職の報せ」に胸を痛めてきました。
でもあるとき気づいたのです。
“できないこと”を指摘するより、“できたこと”を認めるほうが、人は長く続く。
スタッフが伸びる理由の多くは、「認めてもらえた」という感覚にあります。
「ありがとう」「助かった」「あれ、上手になったね」――
この一言が、モチベーションを何倍にも変えるのです。
「居場所」がある人は辞めない
スタッフが辞める理由の多くは、「自分の居場所がない」と感じるから。
だからこそ、店長やリーダーは“その人が活きるポジション”を用意してあげることが大切です。
たとえば、発注が苦手なスタッフには、レジでの声かけを任せてみる。
在庫整理が得意な人には、バックヤード管理を任せる。
「この仕事はあなたに任せたい」と言われた瞬間、人は責任感を持ち始めます。
また、できない部分をカバーする仕組みも重要です。
「一人で全部やらせない」こと。
店全体で“助け合いの流れ”をつくることが、人が続く職場の共通点です。

人は仕事で辞めるんじゃない。
“自分の居場所がない”と感じたときに辞めるんです。
だからこそ、マニュアルよりも大切なのは、
スタッフ一人ひとりの「得意」を活かす場を用意すること。
それが結果的に、離職防止だけでなく、店舗全体の安定運営にもつながります。
人が定着すると、育成コストも減り、チームの空気も良くなります。
スタッフが笑顔で働いている店には、自然とお客様の笑顔も増えていくのです。
スタッフに伝わる声かけと、お客様に伝わる言葉づかい
スタッフ育成で欠かせないのが「伝え方の質」です。 同じ内容でも、言い方ひとつでスタッフの受け止め方や行動スピードは大きく変わります。 これはお客様への接客でも同じで、たった一言の柔らかさで印象がガラッと変わります。
現場でよく見てきたのが、“正しいことを言っているのに、伝え方で損をしているケース”です。 注意の場面、申し送りの場面、お客様への声かけ……。 どれも「内容」よりも「口調・言葉選び」が、相手の心に届くかどうかを決めます。
そんな「伝え方」を磨く上で参考になるのが、こちらの外部記事。 部下指導や顧客対応で使える “クッション言葉” が具体例つきで分かりやすくまとめられています。
🔗 ミナモブログ参考記事: 【伝え方のコツ】今日から使えるクッション言葉まとめ
例えば、スタッフへの「もう少し丁寧にして」も、 お客様への「少々お待ちいただけますか?」も、 クッション言葉を少し添えるだけで受け取り方がまったく違います。
店舗は“人対人”のビジネスです。 だからこそ、スタッフへの伝え方と、お客様への言葉づかいは一緒に磨いていく必要があります。 伝え方が柔らかくなると、スタッフの動きも良くなり、接客の雰囲気も自然と明るくなります。
まとめ|“育成”とは、人を動かす環境を整えること
3つの育成ポイント
ここまでお話ししてきたように、
マニュアルや教育ツールがどれだけ整っていても、
人が動くのは「気持ち」が動いたときです。
- 全員を同じように育てようとしない
- 「できた」を認める声かけを大切にする
- “興味”や“得意”から成長のき
この3つを意識するだけで、
スタッフの目の輝きが少しずつ変わっていきます。
そしてその変化は、必ずお客様にも伝わります。

業務量や業務の質を全員一律にすることは、大切な考え方だと思いますし、そう言う人も多いですよね。でも実際には、誰にでも得意・不得意がありますから、完全に同じ水準にそろえるのは難しいと感じます。
育成は“指導”ではなく“設計”
短期的に結果を求めず、
一人ひとりの“興味”を丁寧に拾い上げる。
それが、結果として離職率を下げ、店舗の安定運営につながります。

マニュアルは道しるべ。
でも、人を動かすのは“共感”と“関心”です。
スタッフの成長は、経営の成長。
一人が輝くと、チームが動き出し、
チームが動けば、お店全体の空気が変わります。
今日からできる“小さな声かけ”から始めてみませんか?
本記事で紹介したスタッフ育成のコツは、 コンビニ現場における人材育成・教育設計の一部です。 人材育成と法令対応の全体的な考え方は、 以下の記事で整理しています。