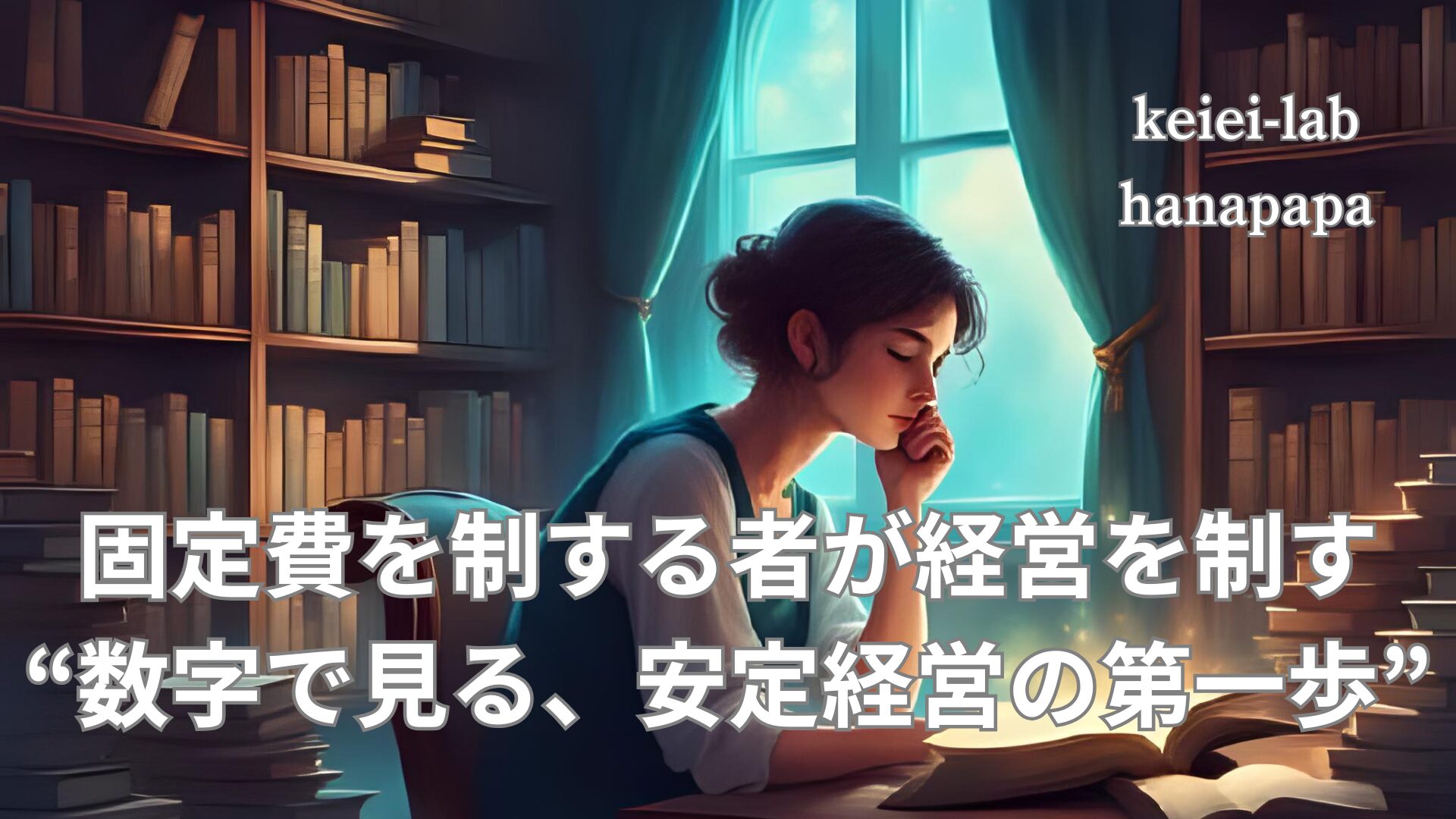【現場エピソード】棚卸しの意味とロスの要因|業者委託と日々の積み重ねの大切さ【経営lab】

――棚卸しと聞くと、「在庫を数えるだけの作業」と思う人も多いかもしれません。
けれど、実際の現場では棚卸しほど“店の精度”が見える瞬間はありません。
私が感じるのは、棚卸しは単なる在庫確認ではなく、
日々の積み重ねを可視化する“経営の健康診断”だということです。
納品チェック、レジ操作、廃棄登録――。
一つひとつの作業が正確に行われていれば、棚卸しで大きなズレは出ません。
逆に言えば、日常の小さなミスが積もった分だけ、ロスとして結果に現れます。
今回は、業者委託で行われる棚卸しの仕組みやロスの主な要因、
そして店側でできる日々の積み重ねの大切さについて、実体験を交えて解説していきます。

棚卸しは「数を合わせる日」じゃない。
「普段の働き方を映す日」なんです。
ではまず、そもそも棚卸しとは何のために行うのか。
そして、業者委託との違いを含めて基本から整理していきましょう。
棚卸しとは何のために行うのか
“在庫を数える作業”ではなく、“日常を見直す時間”
棚卸しとは、店内にある商品の在庫数を実際に数え、
システム上の在庫と差がないかを確認する作業です。
言葉だけ聞くと単純に思えますが、実際の現場ではかなり奥が深い業務です。
コンビニでは通常、棚卸しの多くを専門業者に委託して行います。
ただし、数字を合わせてもそれで終わりではありません。
ズレが発生した原因を追うことで、「どこにロスが生まれやすいか」を見つけるチャンスにもなるのです。
業者棚卸しで見える「結果」より、「過程」を見る
四半期ごとや半年ごとに行われる業者棚卸しでは、
実際の在庫とシステム上の在庫を照らし合わせ、誤差(棚卸し高)を確認します。
この「結果」は、たしかに経営判断の指標になります。
しかし、本当に重要なのはその結果に至るまでの“日々の過程”です。
納品チェック・レジ操作・廃棄登録――このどれかが曖昧なだけでも、
小さなズレが積み重なってロスにつながります。
棚卸しは、単に「数を数える日」ではなく、
自分たちの業務の精度を“数字で振り返る日”なのです。

ロスが発生してしまった場合、その負担はオーナーに返ってきます。つまり、収益がその分減ってしまうということです。だからこそ、日々の業務をしっかり行い、ロスを出さないように意識することが大切ですね。詳しくは下で解説してます。
“数字のズレ”が教えてくれること
棚卸しの数字がピタッと合うと、達成感があります。
一方で、ズレが出ると焦ったり、落ち込んだりしてしまうこともあります。
でも実は、この「ズレ」こそが最大のヒントです。
たとえば、納品数のカウントミス、返品未処理、バーコードのスキャン漏れ。
一見小さなミスですが、これらが積み重なることで、“見えないロス”が増えていきます。
数字がずれたときに、「誰が悪い」ではなく
「どの作業に改善の余地があるか」をチームで考えることが大切です。
こうして一つひとつの作業を丁寧に振り返ることで、
「次の棚卸しは、もう少し誤差を減らそう」とチームの意識も変わっていきます。
数字の裏にある努力こそが、店舗経営の“見えない財産”なのです。
では次に、棚卸しと切り離せないテーマ――
“ロス”が発生する主な原因と、その防止の考え方について見ていきましょう。
ロスの主な要因
ロスは“ミス”ではなく“仕組みの歪み”
棚卸しで数字が合わない原因――つまりロスの正体は、
実は「誰かのミス」というより“仕組みの歪み”にあることが多いです。
日々の業務の中で、ほんの少しの確認漏れや手順のズレが積み重なり、
それが月末・四半期の“数字の誤差”として現れます。
ロスは、現場を責める材料ではなく、
「どこに改善の余地があるか」を教えてくれるメッセージなんです。
よくあるロスの要因と、その背景
ロスにはさまざまな種類があります。代表的なものを挙げると、次のようなものです。
- 万引き:最も分かりやすいロス。防犯カメラ・声かけ・死角対策が基本。
- レジ登録ミス:3個購入なのに1個しかスキャンしていない。
忙しい時間帯ほど、数打ち忘れが発生しやすい。 - 納品ミス:10個発注したのに5個しか届かない、もしくは誤納品。
納品時の数量確認を省くと、気づかないままズレが固定化します。 - 検品漏れ:届いた商品を未検品のまま棚に並べてしまう。
システム上は「入荷済み」になり、実際の在庫と食い違いが発生。 - 廃棄登録ミス:破棄した商品を登録せず処理してしまう。
売上上は存在しているのに、現場にはない――これもロス扱いになります。
どの項目も、ほんの数秒の確認で防げる内容ばかりです。
つまりロスは、“作業量”ではなく“作業精度”で防げるのです。

勤務時間が長くなると、どうしても集中力が切れてぼーっとしてしまいますよね。何百人ものお客様を対応していると、ちょっとしたミスも起こりやすくなります。だからこそ、“早くこなす”よりも“正確にこなす”ことを意識するのが大切。結果的にそれが、最もコスパの高い経営戦略になると思います。
小さな確認が“大きなロス”を防ぐ
たとえば、レジ操作での数打ち忘れは数十円のズレ。
でもそれが1日5回、30日続けば、月に数千円。
1年にすれば、数万円のロスになります。
また、納品時に検品を省略してしまうと、
1つの誤納品で同じ商品がダブり、在庫過多になって廃棄率が上がります。
“少しの確認”を怠ることが、結果的に“大きな損失”を生むのです。
“見逃さない文化”がロスを減らす
ロス対策の本質は、チェックリストよりも“気づける文化”を育てること。
スタッフが「おかしいな」と思った時に、その声を上げられる雰囲気が大切です。
「納品数が違うかも」「この商品、登録されてますか?」――
そんな何気ない声かけが、ロスを未然に防ぐ最大の武器になります。
管理とは、ミスをなくすことではなく、“気づきを拾える環境”をつくることなんです。

商品登録の時など、お客様と会話しながら進めることもありますよね。そんな時は、うっかり入力ミスが起こりやすいので、細心の注意が必要です。お客様との会話も大事、登録を正確に行うことも大事——まさに両立が求められる場面です。避けては通れない、成長のステップですね。
では次に、業者委託で行われる棚卸しの仕組みと、
数字が合わなかった際に発生する“補填”の考え方について整理していきます。
業者棚卸しと補填の仕組み
業者棚卸しは“確認作業”ではなく“信頼確認”
コンビニでは、四半期ごとや半年ごとに専門業者による棚卸しが行われます。
この「業者棚卸し」は、システム上の在庫と実際の在庫を照合し、
ズレがないかを確認する重要な工程です。
数字がピタッと合えば、現場の精度が高い証拠。
逆に誤差が出た場合は、「何が原因か」「どの工程に改善余地があるか」を振り返るきっかけになります。
つまり、棚卸しの目的は「数を合わせる」ことではなく、
“業務への信頼を可視化すること”にあります。
数字が合わなかったときに起きる“補填”
業者棚卸しの結果、システム上の在庫よりも実際の在庫が少なかった場合、
その差額(棚卸し高)はオーナーの自己負担で補填する仕組みになっています。
これはフランチャイズ契約上のルールであり、
本部が商品を卸し、オーナーが販売・管理を担うという役割分担のもと、
「商品管理=経営責任」として位置づけられているからです。
たとえば、業者棚卸しで2万円の在庫差が出た場合、
その金額はオーナーが自己負担で補填する必要があります。
この仕組みは厳しく感じるかもしれませんが、
“経営者としての在庫意識を高める制度”とも言えます。

「棚卸し=責任を問われる日」ではなく、
「管理精度を高めるチャンスの日」と捉えることが大切です。
補填制度の本質は“責任”ではなく“仕組み”
補填制度は決して「罰」ではありません。
本来の目的は、「店舗の在庫管理の仕組みを安定させること」にあります。
たとえば、棚卸しで誤差が出ても、
日常的に納品チェックや返品処理がきちんとできていれば、
次回には確実に改善されます。
逆に「仕組みが整っていない店」は、毎回同じ箇所で誤差が出続ける傾向があります。
重要なのは、「誰の責任か」ではなく「どこを整えるか」という考え方。
チーム全体でプロセスを見直すことで、補填は限りなくゼロに近づきます。

経営者なら当然の義務ですよね。
オーナー管理=数字管理ではなく“現場管理”
棚卸しで重要なのは、数字を追うことだけではありません。
現場を見て、日々の流れを整えることが最も効果的なロス対策になります。
納品時の確認、期限管理、スタッフ教育――
こうした基本の“当たり前”を習慣化できるかどうかが、
棚卸し精度を決定づけます。
オーナー自身が数字だけでなく現場を理解していれば、
スタッフも自然と“意識を持って数を扱う”ようになります。
数字は、信頼のあとからついてくるものです。

在庫を数える前に、“人の意識”を整える。
それが、ロスを減らす一番確実な方法です。
では最後に、日々の棚卸し精度を高めるための習慣づくりと、
“ロスを防ぐ店づくり”の基本をまとめていきましょう。
まとめ:棚卸しは日々の積み重ねがすべて
“数える作業”ではなく“整える習慣”
棚卸しは、業者に委託して定期的に実施されますが、
本当の意味でロスを防ぐには、店側の小さな積み重ねが欠かせません。
納品時の検品、レジ操作の正確さ、廃棄登録の徹底。
そのひとつひとつが「ズレの芽」を摘み取る行動になります。
そして、それを日常業務として自然に続けていくことが、
ロスを最小限に抑える唯一の方法です。
日々の基本が“信頼の数字”をつくる
半年に一度の棚卸しで誤差が出たとき、
その結果だけを見て落ち込む必要はありません。
誤差の裏には、必ず“改善の余地”があるからです。
私の店舗でも、かつては数万円単位のロスを出したことがあります。
でも、そこから「納品チェックの2人体制」や「レジ担当のダブル確認」を徹底するようになり、
翌年には誤差がゼロに近づきました。
改善は、決して一度きりでは終わりません。
毎日の積み重ねこそ、最も確実なロス対策なのです。

数字は結果。
でも、“日々の丁寧さ”がその結果をつくります。
棚卸しの本質は、そこにあるんです。
チームで“丁寧さ”を共有する
ロスを減らすのは、一人の努力ではありません。
スタッフ全員が「確認の大切さ」を理解し、共有していくことが大切です。
「廃棄登録は済んでる?」「納品チェック、もう一度確認しますね」――。
そんな声が自然に出るチームは、数字にも安定感が出ます。
日々のやり取りが“確認文化”を育て、結果的にロスを減らしていくのです。
棚卸しは、日常の“精度”を映す鏡
棚卸しは、数か月に一度のイベントではありません。
毎日の業務そのものが、次の棚卸しの結果をつくっています。
だからこそ、数字を合わせるためではなく、
「ズレを減らすための習慣」を積み上げること。
その意識が根づけば、自然とロスは減り、
スタッフの意識も変わり、店全体が引き締まっていきます。

棚卸しは、未来の準備。
今日の“ひと手間”が、半年後の誤差をゼロにするんです。
廃棄を減らせと言われ続ける現場。でも、売上を作るには一定の“攻め”も必要です。
廃棄率を単なるコストとして見るのではなく、売上を伸ばすための投資という視点から整理した共通入口はこちら。
▶ 廃棄率2〜3%が適正な理由