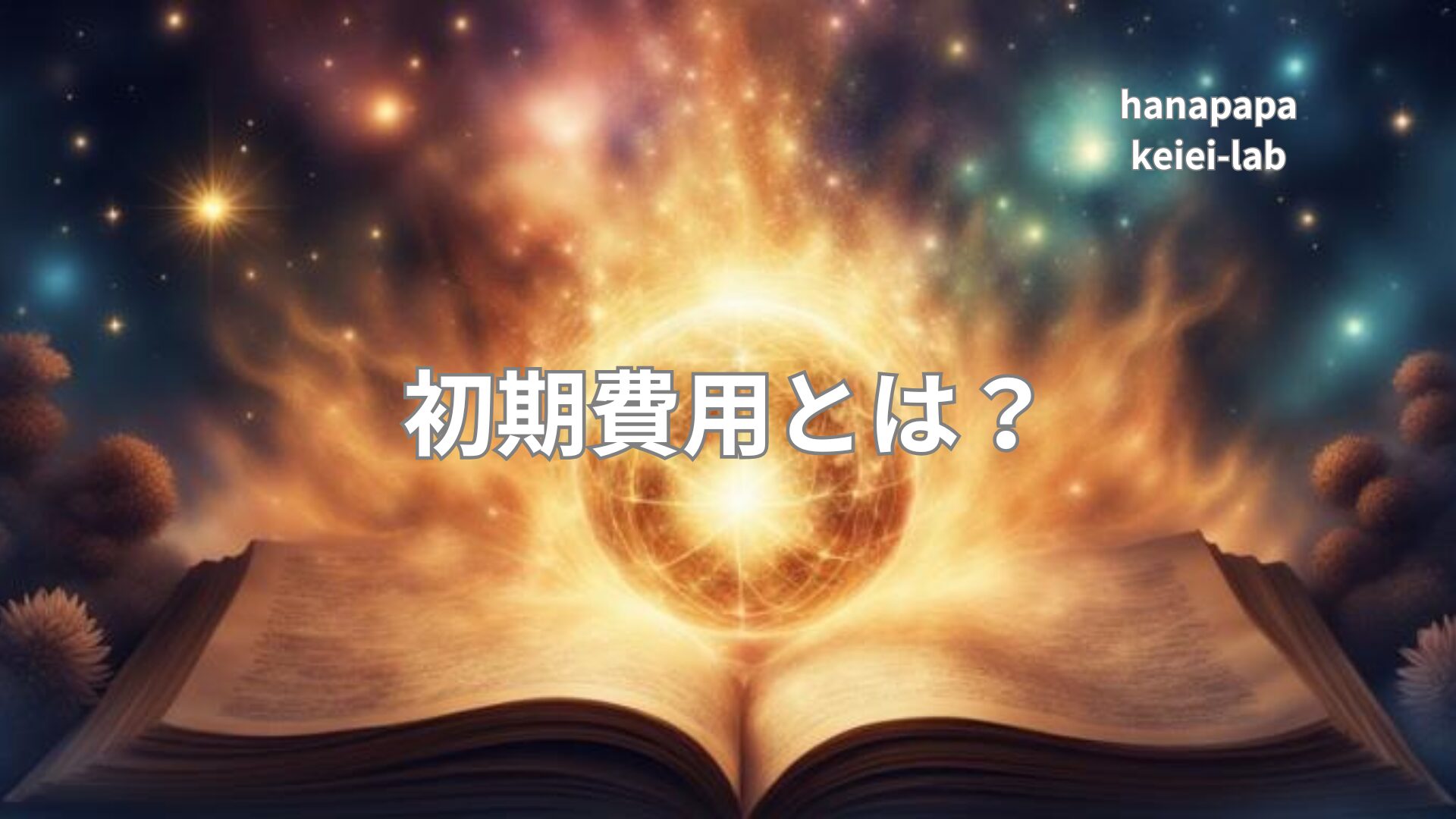本部とオーナーで意見が合わない理由|収益構造の違いと関係構築のコツ

コンビニを経営していると、SV(スーパーバイザー)や本部担当者と
「どうしても話が噛み合わない」「本部の考え方が理解できない」
と感じたことはありませんか?
仕入れ提案やキャンペーン方針、商品投入のタイミングなど、
現場と本部で見ている景色がまるで違うと感じる瞬間があるはずです。
その原因の多くは、実は「収益構造の違い」にあります。
本部とオーナーでは、どこで利益が発生するのかの仕組みが根本的に異なっている。
この違いを理解しないまま議論を重ねると、
「なぜ本部はこんな提案をしてくるのか」「こちらの事情をわかってくれない」
というすれ違いが生まれてしまうのです。
今回は、店舗経営者としてこの構造の違いを正しく理解し、
本部とより建設的な関係を築くための考え方を解説します。

本部とオーナー、どちらが悪いわけでもない。
“見えている数字の違い”を理解するだけで、話が驚くほどスムーズになります。
本部の収益構造:「仕入れ=収益発生」
本部の利益は「仕入れの瞬間」に生まれる
本部(FC本部)の利益はどこで発生しているのでしょうか?
答えは明確で、加盟店が商品を仕入れた時点で収益が計上される仕組みになっています。
つまり、本部にとっては「加盟店が多く仕入れる=利益が増える」という構造です。
このため、“売れる可能性のある商品”を多く仕入れてもらう方向に進みやすくなります。
廃棄は本部の損失にならない
たとえば、店舗がサンドイッチを30個発注した場合、
本部ではその瞬間に30個分の納入利益が発生します。
しかし、実際に売れ残って廃棄になっても、その損失は本部側には直接反映されません。
この仕組み上、本部は“売れるかもしれない商品”をできるだけ仕入れてもらう方向性になりやすいのです。

本部の数字には“廃棄”が反映されません。
現場の苦労が伝わらないのは、この構造が原因なんです。
オーナーの収益構造:「売れた分=収益、廃棄=損失」
オーナーの利益は「販売の瞬間」に生まれる
一方、オーナーの収益構造は非常にシンプルです。
売れた分が利益、廃棄はそのまま損失。
仕入れた時点ではまだ利益は発生しておらず、
お客様が購入して初めて収益となります。
逆に、売れ残って廃棄すれば、その商品の原価分がすべて損失になります。
「仕入れ=リスク」という現場の現実
たとえば、30個仕入れて20個販売し、10個廃棄になった場合、
その10個分の原価がそのまま赤字になります。
つまり、オーナーにとって仕入れは“攻め”ではなく、リスクを伴う判断なのです。
この視点の違いが、本部との意見のズレを生む大きな要因です。

“仕入れを抑えたい”のは守りではなく、リスク管理。
本部と目的は同じでも、見ている数字が違うだけなんです。
本部とオーナーで意見が合わない理由
「利益構造の違い」が意思疎通を難しくする
本部は「売上を伸ばしたい」、
オーナーは「廃棄を抑えて利益を守りたい」。
同じ“売上”という言葉を使っていても、
その意味するところがまったく違うため、意見の食い違いが生じやすくなります。
お互いの“損益分岐点”が違う
たとえば本部が「イベントで○○を強化しましょう!」と提案しても、
オーナーは「前回は廃棄が多かったから慎重にしたい」と考える。
どちらも正しい判断ですが、損益の出るポイント(分岐点)が違うため、
同じ数字を見ても結論が異なってしまうのです。

本部とオーナーのズレは“意見の不一致”ではなく“構造の違い”。
どちらも店を良くしたい気持ちは同じなんです。
本部との関係性をうまく築くための3つのポイント
① まず「収益構造の違い」を理解する
本部とオーナーでは、そもそも利益の仕組みが異なります。
この前提を共有するだけで、相手の提案や判断の“背景”が見えてきます。
たとえば、本部が「新商品の仕入れを強化しましょう」と提案してきたとき、
「また押し売りか…」ではなく、
「本部の利益は“仕入れ時点”に発生するから、そう考えるのか」と冷静に理解できるようになります。

“相手の数字”を理解すると、イライラが減ります。
本部の立場を知ることは、交渉力を高める第一歩です。私の場合、交換条件を提示することもありますよ。
② 感情ではなく「数字とデータ」で会話する
売上・廃棄率・粗利率・時間帯別販売数など、
店舗の実績データをもとに話すことが、最も効果的な対話の手法です。
「なんとなく売れそうだから」ではなく、
「前回の投入では30個中10個が廃棄でした」と具体的に伝えると、
説得力と信頼が格段に高まります。
数字で語ることは、“感情論を超える共通言語”です。

感情で反論するより、数字で説明する方が本部も納得します。
“感情を整理する手段”として数字を使いましょう。
③ 本部を“敵”にせず、「目的共有のパートナー」に
本部とオーナーの最終目標は共通しています。
それは「店舗の売上・利益を伸ばすこと」。
ただし、そのアプローチの手段が異なるだけです。
だからこそ、“対立構造”ではなく、“目的共有の関係”として接することが大切です。
「お互いの数字の見方は違うけれど、目指している方向は同じ」と理解するだけで、
日々のやり取りがぐっとスムーズになります。

本部を“相手にする”のではなく、“味方につける”。
信頼を積み重ねることで、相談できる関係に変わります。お互いにストレスを感じない関係が築けると思います。

数字の見方が違うだけで、気持ちは同じ。
本部との関係は“理解”から始まります
🧩 まとめ:構造のズレを知れば、イライラは減らせる
本部との関係がうまくいかないと、日々の運営ストレスが増えてしまいます。
しかし、「なぜ相手がそう提案するのか?」を構造的に理解するだけで、不要な衝突は減らせます。
店舗経営はひとりではできません。
本部とオーナーが「目的を共有する関係」になれれば、
無理な施策も対話を通して改善でき、長期的な利益を守ることができます。

“構造の違い”を知れば、対立は減ります。
本部との上手な付き合い方も、経営者に必要なスキルの一つです。
💡 最後に
「本部の提案、なんでそう言うんだろう?」と思ったときは、
ぜひこの記事を思い出してください。
数字と立場の違いを理解すれば、関係性は必ず良くなります。
本記事で扱った「本部とオーナーのギャップ」は、 コンビニ現場の運営や仕組み改善に関わるテーマです。 現場改善をPDCAで回す全体像は、以下の記事で整理しています。