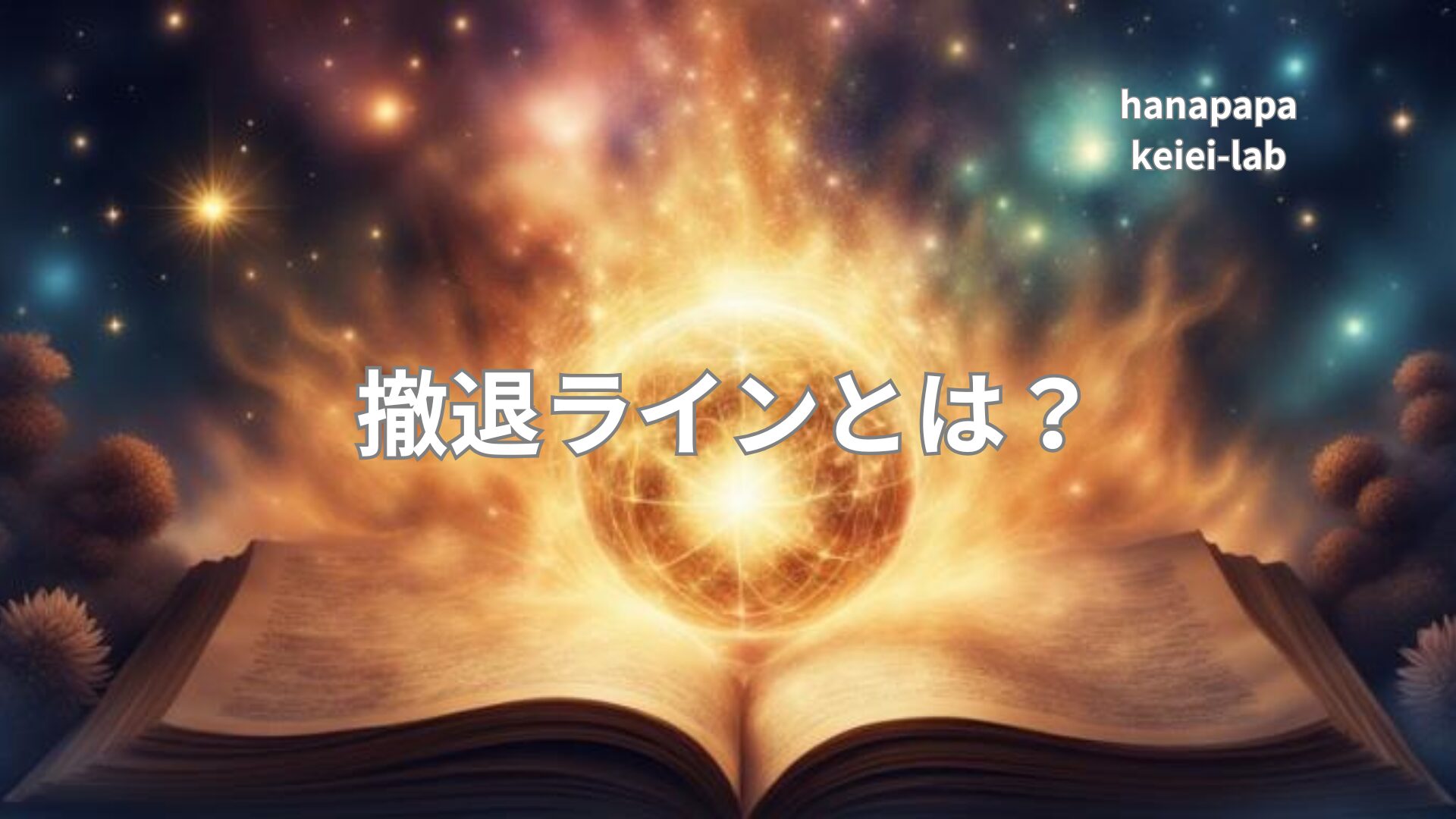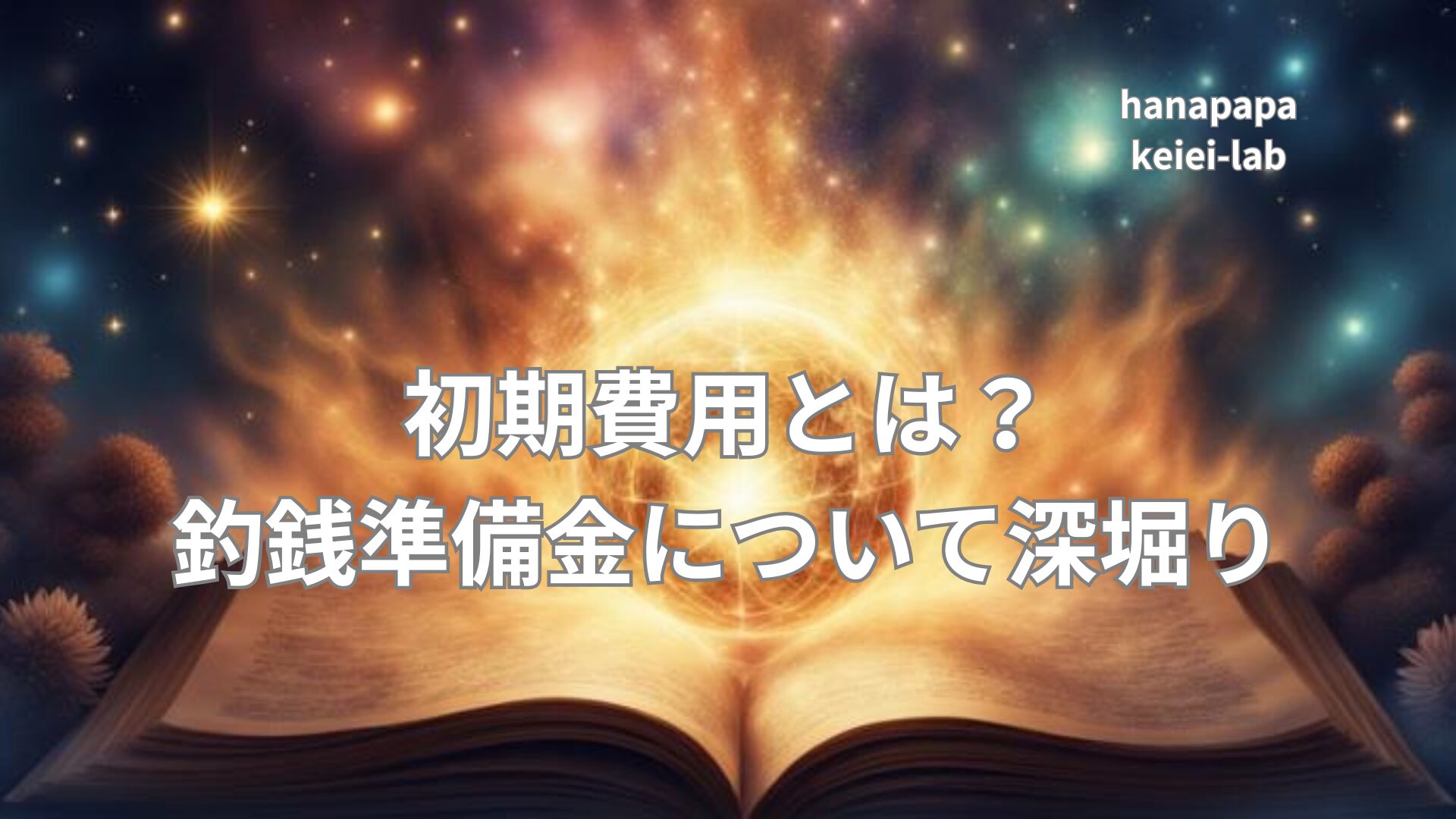【保存版】店舗経営者が絶対に知っておくべき保険と共済制度の使い分け
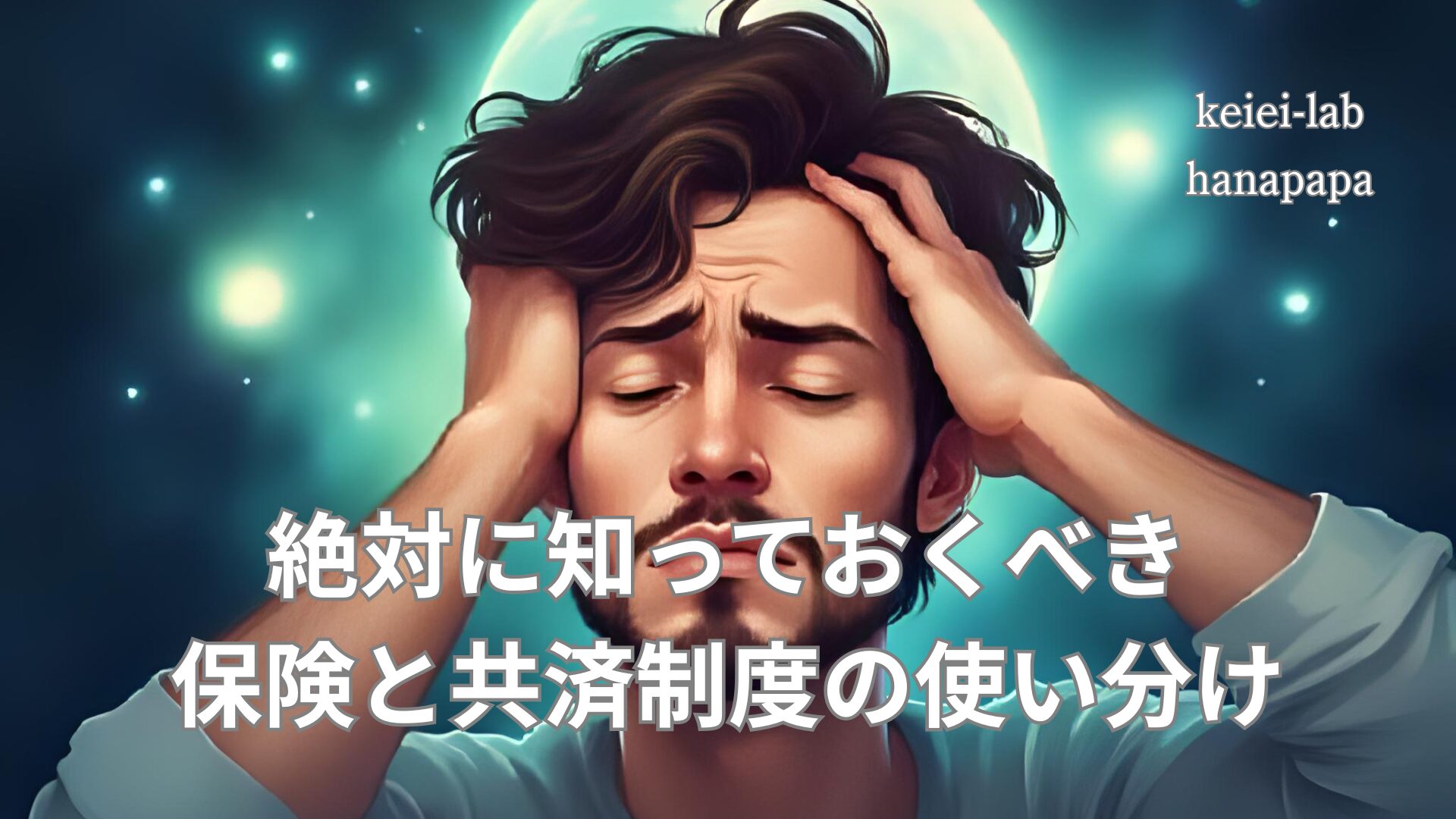
――“入っておけば安心”が、実は一番危ない。
店舗を経営していると、
「この保険は絶対必要です」「今ならお得ですよ」といった保険セールスの話を耳にすることが多いと思います。
しかし、いざ契約してみると――
「結局どの保険が本当に必要なのか分からない」というのが、多くの経営者の本音ではないでしょうか。
保険は“入ること”よりも、“何のために入るか”が重要です。
無駄な契約を減らし、いざという時に確実に守ってくれる制度を選ぶためには、
「法定保険」→「公的制度」→「民間保険」という順で整理することがポイントになります。
この記事では、
- 経営者が必ず入るべき「法定保険」
- 低コストで活用できる「公的共済制度」
- 必要に応じて検討すべき「民間保険」
の3ステップで、“店舗経営に本当に必要な備え”を分かりやすく解説します。

セールスが来たから加入を検討するのではなく、自分の事業に必要な制度はなにかを考え、調べ行動に移しましょう!
1. 必ず加入すべき「法定保険」
――“知らなかった”では済まされない、経営者の義務と責任
まず大前提として、事業を営む以上は法律で加入が義務付けられている保険があります。
これは「任意」ではなく、「やる・やらないの選択肢がないもの」。
加入を怠ると、万が一のときに補償が受けられないばかりか、行政指導や罰則の対象にもなり得ます。
「うちは小規模だから関係ない」は誤解
個人事業主や小規模店舗でも、
パート・アルバイトを1人でも雇えば、法定保険の対象になるケースがあります。
特に労災保険は「従業員1人でも加入義務あり」。
万が一の事故に備えずに営業を続けることは、
“経営リスクの放置”と同じことです。

“知らなかった”では済まされないので、開業時や事業を立ち上げるときには、しっかり経費として計算に入れておきたいですね。
経営者自身も守るための加入形態を確認
経営者本人(個人事業主・法人役員)は、
通常の労災や雇用保険の対象外になるため、
「特別加入制度」などを利用して自らを守る必要があります。
- 労災保険特別加入:自営業者・家族従業員でも加入可能
- 中小企業主特別加入制度:現場作業を行う経営者を対象
- 任意適用の社会保険:役員報酬がある場合は加入対象になることも

私の場合、この後に出てくる小規模企業共済やNISA・iDeCoといった制度は、労災保険の特別加入など“守るための仕組み”としてではなく、“資金を増やす手段”として活用しています。万が一に備えるのではなく、どんな状況にも対応できるお金を育てておく、という考え方ですね。
2. 事業を守るために優先すべき保険
――「万が一」が起きたとき、あなたの店を守ってくれるのは“準備”だけ
法定保険で人と組織を守る基盤を整えたら、
次に考えるべきは、「事業そのものをどう守るか」です。
火災や事故、商品の破損・賠償など、
ひとたびトラブルが発生すれば、数百万円〜数千万円の損害につながるケースも少なくありません。
経営を安定させるためには、「入っておけば安心」ではなく、
“営業を続けるために欠かせない保険”を優先的に整える必要があります。

駐車場などで、ブレーキとアクセルを踏み間違えて店舗に車が突っ込んだ、大雨により店が浸水して商品全損なんてことよくあります。冷ケースがストップしてしまうなど、小さなこともあわせれば、年間で相当の回数おこります。
補償が「費用」ではなく「再起の資金」になる
これらの保険は、「入っておけば安心」ではなく、
“倒れたあとに立ち上がるための資金”を確保する意味があります。
火災・事故・賠償トラブルの後に、
「営業再開できるかどうか」を決めるのは“補償の有無”。
特に個人店舗では、突発的な損害がそのまま経営終了の引き金になることもあります。
一方で、保険により復旧資金を確保していれば、
「一時的な損害」で終わらせることができます。

事業だけじゃなく、家庭でも火災保険に入りますよね。実はこの火災保険、意外と万能なんです。いろんな場面で適用される条件があるので、一度チェックしてみると新しい発見があるかもしれませんよ。
🔹 フランチャイズ・本部契約店舗の注意点
フランチャイズ加盟店や本部管理型店舗の場合、
一部の保険(火災・PL保険など)は本部一括契約に含まれているケースもあります。
ただし、
などが限定的なことも多く、
「本部任せにせず、自店の補償範囲を確認する」ことが経営者の責任です。

現場を見ていると、「火災保険だけで十分」と思っている経営者も少なくありません。
しかし、実際にリスクが起きるのは火災よりも“賠償トラブル”の方が多い。
特にお客様がケガをしたとき、補償対応が遅れると信頼を失うこともあります。私が経験した事例も下のリンクでどうぞ。
3. 公的制度を最大限活用する
――“保険に入る前に知っておくべき”経営者のセーフティネット
民間保険の前に、まず活用すべきは国や中小機構が提供する公的制度です。
これらは、掛金の一部が税制優遇の対象になったり、
無担保・無保証で資金を借りられたりと、
コストを抑えつつ経営者を支える仕組みになっています。
特に、店舗経営者や中小企業主にとって、
“もしものときに経営を立て直す資金”を確保するうえで非常に頼りになる制度です。
公的制度の魅力:コスト効率が高い
これらの制度は、民間保険よりも掛金に対する効果が圧倒的に高いのが特徴です。
- 掛金が全額または一部損金・所得控除の対象
- 共済金を受け取りながら税負担を軽減できる
- 退職金や倒産リスクに備えつつ、実質的な節税効果が得られる
加入優先順位の考え方
1️⃣ まずは法定保険で“最低限”を守る
2️⃣ 次に公的制度で“長期の安心”を確保する
3️⃣ その上で民間保険で“個別リスク”を補う
この順番を守るだけで、
保険コストを抑えながら無駄のない経営防衛ラインを作ることができます。

公的なこういった制度は、税の繰り延べになる部分もありますから、加入する前にどんな仕組みなのかをしっかり確認しておくことが大切ですね。
4. 民間の法人保険はどう考える?
――「勧められたから入る」ではなく、「必要だから選ぶ」
民間保険会社は経営者向けに、
「事業継続」「退職金準備」「節税」などを目的とした
さまざまな法人保険を提案してきます。
たしかに、うまく活用すれば資金対策や節税にもつながります。
しかしその一方で、仕組みが複雑で保険料が高いものも多く、
“内容を理解せずに加入して後悔する”ケースも少なくありません。
「必要性」を判断する3つのチェックポイント
1️⃣ 公的制度や共済で代替できないリスクか?
→ すでに共済制度や助成制度でカバーできる内容なら、重複の可能性あり。
2️⃣ 加入目的が“節税”だけになっていないか?
→ 節税効果は一時的。将来的な解約返戻時の課税も考慮する。
3️⃣ 経営のフェーズに合っているか?
→ 開業初期はキャッシュ重視、中期以降は“事業承継・退職金対策”へシフト。
保険は「安心」ではなく、「判断」から生まれる。
加入するかどうかよりも、“なぜ入るか”を明確にすることが重要です。
注意点:法人保険は「万能」ではない
- 節税効果を強調する商品は、税制改正の影響で制度変更リスクがある
- 解約返戻率は年数によって大きく変動。途中解約で元本割れするケースも
- 契約時は「返戻率」「保険期間」「受取人」を必ず確認

民間保険の多くは“節税効果があります”なんて言葉でセールスしてきますが、実際の節税効果なんて雀の涙ほどなんですよ。まずは正しい知識を身につけることから始めましょう。
まとめ:店舗経営者が選ぶべき保険の優先順位
――“安心のための加入”から、“経営のための備え”へ
保険は「万が一のリスクに備えるためのもの」。
けれど、経営者にとっては単なる“安心材料”ではなく、
「事業を続けるための経営戦略」の一部です。
数多くの保険商品があるなかで、
「どれを選べばいいのか分からない」という声は少なくありません。
そこで大切なのは、順序を間違えないこと。
判断の軸:「必要な保険」は“業態とステージ”で変わる
| 経営ステージ | 主なリスク | 優先すべき保険 |
|---|---|---|
| 開業期 | 設備投資・事故リスク | 法定保険+火災・賠償保険 |
| 安定期 | 資金繰り・退職金・人材定着 | 共済制度+キーマン保険 |
| 成長期 | 事業承継・組織拡大 | 役員退職金保険・D&O保険など |
✔️ 重要なのは「今の経営課題に合った保険」を選ぶこと。
未来のための備えも、タイミングを誤ると“資金の重荷”になりかねません。
実践チェックリスト:今すぐ見直したい5項目
| チェック項目 | 状況 | 対応メモ |
|---|---|---|
| 従業員がいるが、労災・雇用保険が未加入 | ☐ | 早急に労基署・ハローワークで手続き |
| 自身の退職・廃業後の資金備えがない | ☐ | 小規模企業共済の加入を検討 |
| 火災・賠償保険の補償範囲を把握していない | ☐ | 保険証券を見直し・必要に応じて代理店に確認 |
| 保険料が高いまま更新している | ☐ | 同条件で複数社見積もりを比較 |
| “なぜ入っているか分からない保険”がある | ☐ | 加入目的を再定義。不要なら解約も検討 |

保険は、売上を直接生まない“地味な経費”に見えます。
ですが、何かあった時に経営を守れるかどうかは、この地味な部分の差で決まります。
「保険=守り」ではなく、「継続のための仕組み」。
そう考えれば、迷いなく“入る・見直す・選ぶ”判断ができると思います。
最後に:保険は“人を守る経営”の象徴
店舗経営とは、日々の積み重ねの中で多くの判断を下す仕事です。
その中で「備える」という行動は、
お客様・スタッフ・自分自身を大切にする経営姿勢そのもの。
保険を整えることは、“安心を提供する店”を作ること。
それが、経営者にとって最も確実な信頼投資です。
本記事で紹介した保険・共済制度に関する考え方は、 コンビニにおける従業員の福利厚生・労務の一部です。 人材育成や法令対応の全体的な考え方は、 以下の記事で整理しています。