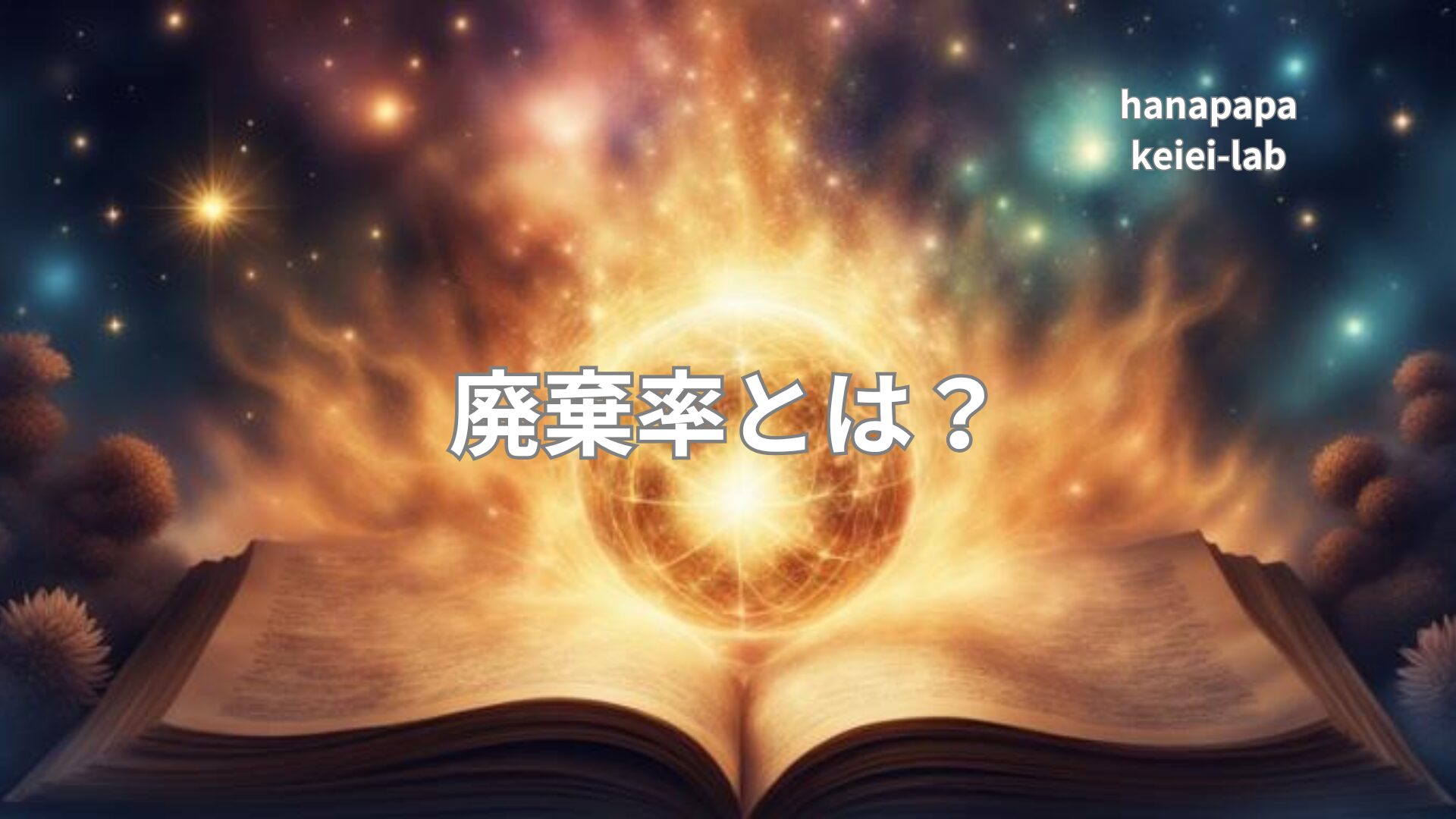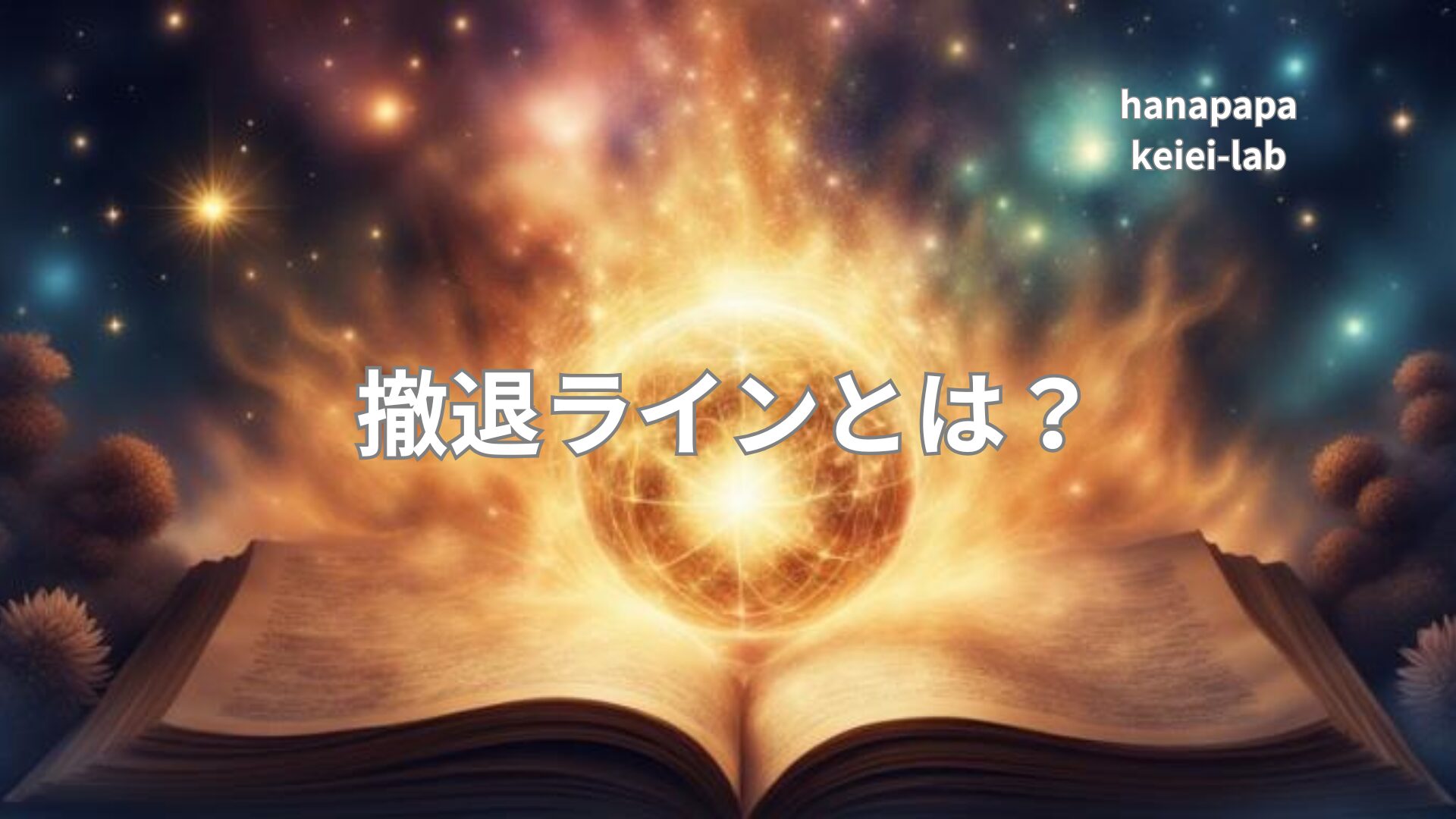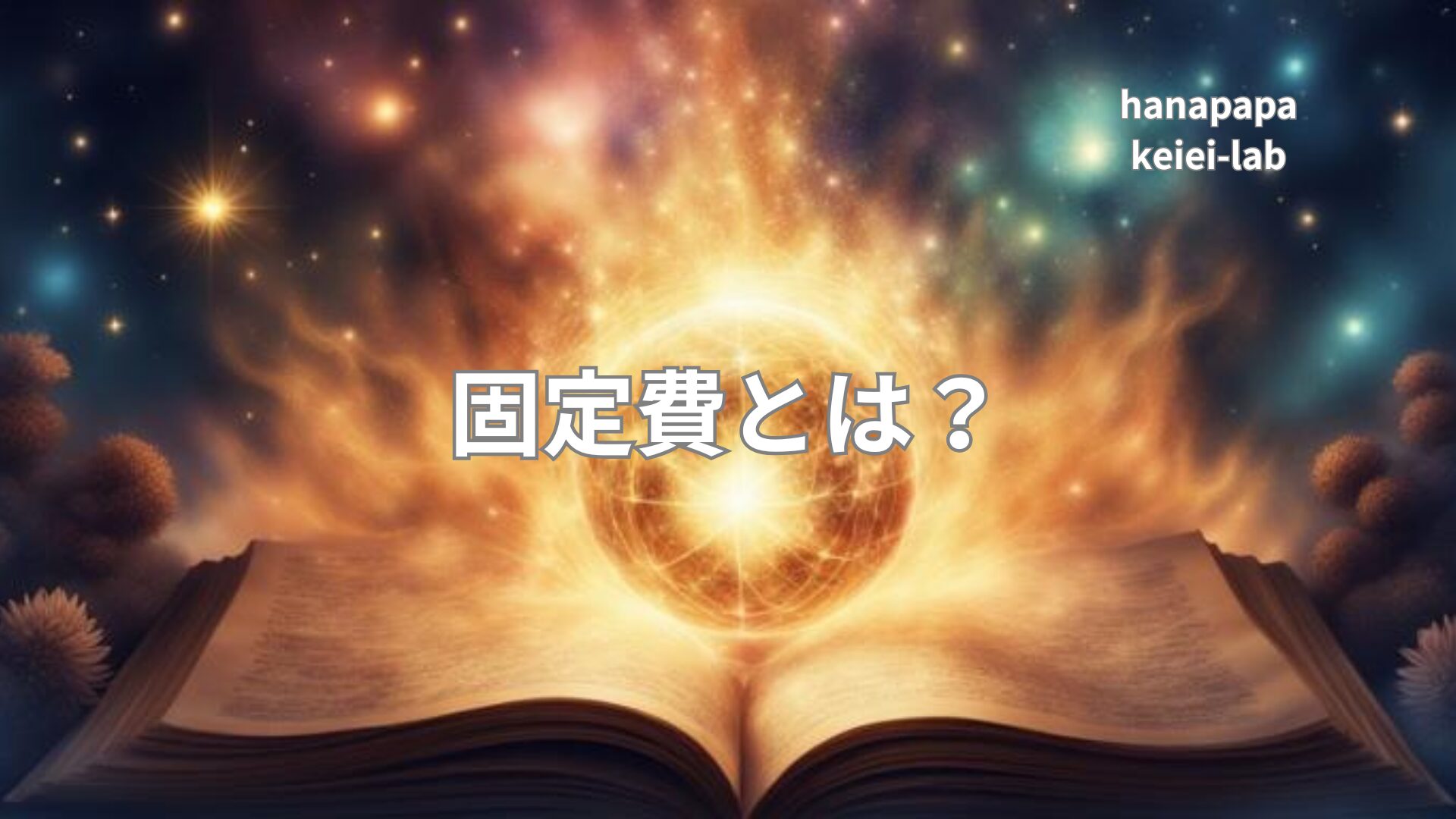発注強制の“名残”はまだある|本部と現場をつなぐ調整力が経営を変える

コンビニ経営をしていると、
「発注って本当に自由なの?」
「本部から強制されることなんてあるの?」
そんな疑問を持たれたことがある方も多いと思います。
ニュースなどでも取り上げられた「発注強制問題」。
「まさかそんなことが現場で本当にあるの?」と感じた方もいるでしょう。
結論から言えば、“ありました”。
私も長年、コンビニ現場で働いてきた中で、
「発注しておかないと本部に怒られる」
「売れ残ると分かっていても入れないといけない」
そんな“無言の圧力”のような空気を感じた時期が確かにありました。
今でこそ社会問題化し、明確な「強制」は減りましたが、
“名残のような空気”は、今も現場に少なからず残っていると感じます。
今回は、この「発注強制」をテーマに、
現場と本部のズレ、そして現場で感じたリアルな視点から、
“対立ではなく調整で乗り越えるヒント”を整理していきます。

現場を守るのは、反発ではなく“見極め”。
本部の意向も現場の声も、どちらも大切にすることが長く続く経営の鍵です。
報道後は厳しくなったけど、今も“名残”はある
“発注強制”は過去の話? それともまだ続いている?
発注強制が社会問題として取り上げられたのは、2019年ごろ。
ニュースでも大きく報道され、
「本部が加盟店に無理な発注をさせていた」という構図が話題になりました。
報道後、多くの本部が「強制」と受け取られないように体制を見直し、
発注に関しては“加盟店判断を尊重する”姿勢を明確に打ち出しました。
それ以来、現場であからさまな圧力や指示が減ったのは確かです。
しかし一方で、「名残のような空気」が完全になくなったわけではありません。
たとえば、
- 「この商品は必ず発注お願いします」
- 「他店はこれだけ入れてますよ」
- 「今回は協力してもらえますか」
こうした“言葉を選んだ指導”が、今も現場に残っているケースがあります。

“言葉では自由”でも、空気が圧になることがある。
本部も現場も、どこまでが“提案”でどこからが“強制”か、見極めが難しいんです。
本部も“変わろう”としている現実
本部側もまた、世論の反応を受けて確実に変わってきています。
現場の自主性を尊重しようという意識は、以前よりずっと強くなりました。
ただ、全国に何千店舗もある中で、
エリアや担当SV(スーパーバイザー)による温度差はまだ残っているのが現状です。
本部が掲げる「柔軟な運営方針」と、
現場での「体感的な圧力」には、少しギャップがある――
それが今の“過渡期”といえるかもしれません。
本部と現場の“温度差”がズレを生む
本部の意図は「売上を伸ばすための提案」。
しかし、現場にいるオーナーから見れば、
「売れ残りリスクを抱えてまで入れるべきか?」という不安もあります。
この“温度差”こそが、トラブルや誤解の原因になるのです。
たとえば、
本部「キャンペーン対象なので、ぜひ入れてください」
オーナー「うちの客層には合わないんですが……」
このように、意見がすれ違うことは今でも少なくありません。
大切なのは、“対立”ではなく“調整”の姿勢です。

本部も“悪意”で言っているわけではない。
お互いの目的を理解できれば、協力の形は変えられます。
契約書を盾に、本部が“態度を変える”こともある
“圧力”ではなく“立場の違い”が生むギャップ
発注強制の問題が社会的に注目されて以降、
本部側も露骨な強要や命令を避けるようになりました。
しかし、現場にいると感じるのは、
“言葉の強制”が減った代わりに“契約を根拠にした圧力”が増えたということです。
たとえば、
- 「契約上、発注を拒否するのは違反になります」
- 「加盟契約に基づく運営ルールですので」
といった、契約書を盾にした言い回しが増えている印象があります。
もちろん、契約内容は経営上のルールであり、
双方が守るべき約束ごとです。
ただ、現場感覚から見ると、“本部の提案=事実上の義務”に感じる瞬間が今もあるのです。

“言葉の圧”はなくても、“仕組みの圧”は残っている。
本部も現場も、立場の違いを理解し合うことが大切です。
本部が「契約」を持ち出す理由
本部が契約を強調するのには、理由もあります。
全国に数千、数万店舗を抱える本部にとって、
公平性を保つこととブランドの一貫性を守ることは重要な使命です。
「一部の店舗だけが独自判断をすると、ブランド全体の信頼に影響する」
というリスクを避けるために、あえて“契約ベースでの統一”を重視しているわけです。
つまり、本部が契約書を出してくる背景には、
単なる圧ではなく全体最適のためのルール維持という意図があるのです。
“本部の論理”と“現場の現実”の間にある温度差
現場側から見ると、
「数字上は正しいけど、実際には売れない」
というケースも少なくありません。
たとえば、
- 地域の客層が年配中心で新商品が動かない
- 降雪地帯やイベント期間外で需要が読みにくい
- 競合店舗との立地差で同じ販促効果が出ない
本部は全国規模でデータを見ていますが、
現場は“目の前のお客様”を見ている。
この“視点の違い”が、発注判断のズレを生む最大の要因です。

“全体を見て言う本部”と、“お客様を見て考える現場”。
どちらも正しい。だからこそ、“調整”が必要なんです。
圧を感じたら、まず“理由”を聞いてみる
現場としては、「また契約か…」と反発したくなる気持ちも分かります。
ただ、そこで感情的になってしまうと、話がこじれてしまいます。
そんな時こそ、
“なぜその指示があるのか”を冷静に確認することが大切です。
- 「なぜその数量が必要なのか?」
- 「他店ではどのような結果が出ているのか?」
- 「代替案はありますか?」
本部の“狙い”や“背景”を理解できれば、
一方的な命令ではなく“共有できる判断”へと変わっていきます。
本部とオーナー、それぞれの立場がある
どちらも“正しい”が、見ている景色が違う
発注に関する考え方のズレは、
本部とオーナーで「見ている視点」や「守るもの」が違うことから生まれます。
- 本部側の立場:売上を伸ばし、ブランド全体を成長させたい
- オーナー側の立場:売れ残りリスクを最小限にして、日々の利益を守りたい
どちらも間違っていません。
むしろ、どちらも正しい――ただ、目的が異なるだけなのです。

“本部の正しさ”と“現場の正しさ”は別物。
どちらが間違っているではなく、“見ている角度”が違うだけです。
本部は「売りたい」、オーナーは「売れるか不安」
たとえば、プロモーション商品の発注。
本部としては、全国的な販売データをもとに「売れるはず」と判断しています。
一方、オーナーから見ると、
「うちの立地や客層ではどうだろう?」という不安が拭えません。
これは、単なる意見の違いではなく、
“売りたい側”と“売る側”の立場の違いが生む自然なギャップです。
どちらも「売上を上げたい」という目的は同じ。
ただし、そこへ向かうアプローチが違うのです。
利益構造の違いが、判断のズレを生む
根本的なズレの原因は、利益の出方の仕組みにあります。
本部は、商品が「出荷された時点」で利益が計上されます(いわゆる売上総利益)。
一方で、オーナーは「売れた時点」ではじめて利益が発生します。
つまり、
- 本部:「どれだけ仕入れたか」で数字を追う
- オーナー:「どれだけ売れたか」で手元の利益が決まる
この構造の違いが、発注判断や販促に対する温度差を生むのです。

“売る前に利益が出る本部”と、“売らないと利益が出ない現場”。
立場が違えば、正義も変わります。
本部の意図を理解しつつ、“現場の現実”を伝える
私は本部の方針に合わせることもありますが、
現場でお客様の声を直接聞いている立場として、
「これは厳しい」と思う提案は、正直に伝えるようにしています。
たとえば、
- 「この商品は売れる層が違います」
- 「この時期は他商品が重なっているので調整したい」
といった現場のリアルを“数字と理由”で返すことで、
“反発”ではなく“改善提案”として受け入れてもらえるケースが増えました。
本部の意向を受け入れつつ、現場での調整がカギ
すべてを拒むより、“調整”で折り合いをつける
店舗経営をしていると、
「本部の方針に全部従うのは違う」
「でも、全部断っていたら関係が悪くなる」
――そんな板挟みになる瞬間が、必ずあります。
そのときに大事なのは、“反発”ではなく“調整”の姿勢です。
たとえば、
- 提案された数量をそのまま入れるのではなく、一部を調整して発注する
- 客層や天候の情報を添えて、理由を明確に伝える
- データをもとに「次回はこの数量で検証したい」と交渉する
こうした“調整の一手間”が、結果として本部との信頼を深めます。

“言われた通り”も“言いなり”も経営ではない。
本部と現場の間に立つ“調整力”こそ、オーナーの腕の見せどころです。
“売れる・売れない”の判断は現場にしかない
どんなに本部がデータを持っていても、
「売れるかどうか」までは現場にしか分かりません。
なぜなら、数字では読み切れない要素――
お客様の動線、時間帯、地域の習慣――
これらは現場でしか見えないからです。
だから私は、本部の提案を受けるときに必ず、
「この店の実情ではどうか?」を軸に考えるようにしています。
“売れない”は失敗ではなく“学び”
発注して売れなかったとき、
「だから入れたくなかったのに」と後悔して終わるのではなく、
“何が原因だったのか”を分析する癖をつけています。
- 客層と商品のミスマッチだったのか
- 販売タイミングが悪かったのか
- POPや売場での見せ方が不足していたのか
失敗の中にも、次に活かせる“改善データ”があります。
これを蓄積していくことで、
“感覚ではなく根拠のある判断”ができるようになっていきます。

失敗を“怒り”ではなく“改善”で返す。
その積み重ねが、現場の信頼をつくります。
“本部と対立しない経営”が結果的に強い
最終的に、長く続く店舗ほど本部との関係が良好です。
それは、“言われるがまま”ではなく、
“対話しながら信頼を積み重ねている”からです。
本部と現場の間には、いつも温度差がある。
でもその“ズレ”こそが、現場の強みです。
現場を知っているオーナーが調整役となり、
「本部の提案をどう現場に合わせるか」を考え抜けるか――
そこが、店舗経営の真価を決めるポイントです。
まとめ:対立じゃなく「調整」が大切
意見が違うのは“悪いこと”じゃない
本部と現場では、考え方や見えている景色が違います。
本部は全国の数字とブランド全体を見て、
現場は地域のお客様と日々の売上を見ている。
そのため、発注や販促の方針で意見が食い違うのは当たり前。
でも、違う意見=対立ではありません。
むしろ、意見の違いは“現場の強みを発揮するチャンス”です。
本部の提案を踏まえながら、自店の実情に合う形へ“調整”する。
その柔軟さが、経営を長く続けるための鍵になります。

“反発”より“調整”。
本部とオーナー、どちらも同じゴールを見ている。
方向が違うだけなんです。
“従うか否か”より、“どう活かすか”を考える
本部の提案をすべて断ってしまうのは簡単です。
でも、それではお互いに信頼が育ちません。
大切なのは、提案を「使えるもの」に変える力。
- どう現場で応用できるか
- どの部分を取り入れ、どこを調整するか
- お客様にどう伝えれば響くか
この視点を持つだけで、“指示を受ける経営”から“提案を活かす経営”へ変わります。
経営の本質は“対話”と“信頼”
結局のところ、経営の本質は「数字」よりも「信頼」です。
本部との関係、スタッフとの関係、お客様との関係――
そのどれもが、対話から生まれる信頼の上に成り立っています。
本部に意見を伝えるときも、感情ではなく“数字と理由”で伝える。
その姿勢を積み重ねることで、
「この人の言葉は信頼できる」と認めてもらえるようになります。
そしてそれが、結果的に自分の店舗を守り、地域のお客様を守る力になるのです。

本部と現場、どちらも“店を良くしたい”気持ちは同じ。
大切なのは、ぶつからずに“歩み寄る力”です。
本記事で扱ったフランチャイズにおける発注プレッシャーの実態は、 コンビニ現場の判断や仕組み改善に関わる課題です。 現場改善・PDCAで回す全体の考え方については、 以下の記事で整理しています。